プロフィール
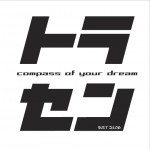
トランスセンデンス
その他
プロフィール詳細
カレンダー
検索
最近の投稿
タグ
- イベント
- 釣果報告
- オセレイト59+
- Enhance65/75
- Batuta67/80
- Dwarve XX
- LateBloomings510+
- Laulau83GT-S
- Botia
- Currentes
- Empinado108
- Pulchra
- Estremo76
- Eta quattro
- Monsterfin70
- Twinslide
- Slowslide
- Galupa
- Trapa
- カランクス
- Shore98S
- レイブルMD
- オリカラルアー
- イギ―タ5インチ
- Chilloutfishing
- スタッフ紹介
- Masaaki Katayama
- Yusuke Takada
- Masayuki Yamane
- Keisuke Doi
- Naomichi Toishi
- Kodai Kimura
- Kimi Hiroyuki Yamane
- Shoya Nakamura
- Ryo Miyaguchi
- Hiromu Matsumura
- Takato Yamada
- Kakeru Baba
- シーバス
- ヒラスズキ
- メバル
- オフショア
- ヒラマサ
- クロマグロ
- GT
- アカハタ
- オオモンハタ
- ロックフィッシュ
- クロダイ・チヌ
- 青物
- バス
- 渓流
- イワナ
- ライギョ
- アカメ
- イトウ
- ビワコオオナマズ
- タマン
- コブダイ
- サワラ
- ホウキハタ
- イソマグロ
- ライトゲーム
- アジング
- ヌマガレイ
- マトウダイ
- スネークヘッド
- バラマンディ
- カショーロ
- ピーコックバス
- パプアンバス
- チョウザメ
- ナマズ類
- アリゲーターガー
- グルーパー
- キングサーモン
- サケ・マス類
- 北海道
- 青森
- 龍飛
- 小泊
- 東北
- 八丈島
- 房総半島
- 首都圏
- 神奈川
- 静岡
- 伊豆半島
- 相模湾
- 相模川
- 名古屋
- 関西
- 琵琶湖
- 久六島
- 高知県
- 玄界灘
- 鹿児島
- 東京湾
- 荒川
- インドネシア
- ボルネオ島
- マレーシア
- パタゴニア
- アメリカ
- タイランド
- メキシコ
- ガイアナ
- コロンビア
- 中米
- 2022年 新製品紹介
- Organon
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:64
- 昨日のアクセス:206
- 総アクセス数:739867
QRコード
▼ 【本音インプレ】パックロッドの強度と使用感をフルタイムバスガイドの視点から
- ジャンル:日記/一般
- (釣果報告, Yusuke Takada, 琵琶湖)
文・写真:ビックリマン高田
昨今のフィッシングスタイルの多様化により、様々なメーカーよりパックロッドが発売されてる。

昔の印象とは違い、1ピースの遜色ない強度と使用感がある…というのはここ数年言われてきたこと。
既存の1ピースや2ピースと変わらないのであれば、コンパクトなほうがいいんじゃない!
っていうのは皆が納得するとこだろうけど、それと同時に「とはいえ継ぎが増えたら強度は落ちるのでは」、「重くなったり、使用感、感度が悪くなるのでは」なんてことも皆思うだろう。
この文章を書いてるビックリマン高田も、パックロッドもといマルチピースロッドメーカーであるトランスセンデンスのプロスタッフということで日頃よりパックロッドを使っている。
というかこのブログがパックロッドメーカーのブログだ(汗)
今回はそんな自分の立場を一旦忘れた上で、パックロッドのリアルについてアングラーの目線で包み隠さずお伝えしたい。
毎月25日以上。1年で300日×平均8〜10時間。
つまり1年で約3000時間ほど、フィールドに立ち続けてるプロアングラーからみたパックロッドの性能をお伝えしようと思う。

▪️強度
結論から言えば、きちんと設計されたパックロッドであれば強度不足を感じることはない。
それはほぼ全ての釣りがそうで(100kgを超えるマグロなどの魚は経験がないので別かもしれないが)、
ヘビーカバーのバスフィッシングやアカメ釣り、GTまでもパックロッドで釣りをしてるが、パックロッドであるがゆえの強度不足やトルク不足を感じたことはない。

設計がキチンとされたパックロッドで釣りに合わせて適正なパワーとロッドのアクションを選べば現場の使用で破損のリスクが高いと感じたことはない。
ロッドが破損する瞬間…というのは自分もそうであるし、仕事柄ゲスト様も含めて色々見てきた。
原因は様々で使用方法(どんな竿でも折れる…ような使い方)であったり、ロッドのパワーセレクトが釣りに合っていない、ラインの設定ミス…などがあるが、
"ロッドの設計が甘い"ことが原因になる破損も中にはある。
しかし、これは1ピースであろうがパックロッドであろうが変わらない。
1ピースでも2ピースでも設計が甘い(必要な強度を出せてなかったり、曲がる部分の設定が間違ってたり)するといとも簡単に折れてしまう。
ただし設定の難しさでいうとパックロッドのほうが難しいという現実もある。
継ぎの部分が曲がらず突っ張ってしまうことが多いのでそこを綺麗に曲がるにはパワーの細かい調整が必要である。

継ぎがない1ピースロッドは継ぎの部分の調整が必要ないので設計はいくぶん楽だ。
あとは工場ベースでの単純強度。ロッドの工場で出る破断の数値でいえば継ぎのない1ピースロッドに軍配があがる。
つまりパックロッドは丁寧に設計しなければ、折れやすいというのは正直なところである。
その代わり正しく設計されたパックロッドであれば連日のパワーフィッシングで酷使されても破損はなく、ワンピースと比べてもなんら遜色のないロッドと言える。

僕も振動や衝撃の大きいバスボートに毎日パックロッドを積んでハードな釣りをしているが、何の問題もなく機能している。
そういう意味では少なくとも僕が使ってるモデルのパックロッドについては安心してもらえるかなとも思う。
※強度不足のロッドがあればバスボートからそっと下ろします(笑)
▪️軽快さ
パックロッドは継ぎがあるので同じパワー、同じ長さ、同じ硬さのものを作ったとすれば当然1ピースのほうが自重は軽く作れる。
とにかく自重軽いロッドを…という人は1ピースを選ぶべきだろう。
しかしロッドというのは単純重量で人間の感じる重さが決まるものではないのだ。
リールをつけた時にバランスがどこにあるか…というのがとても重要なのである。
例えば自重130gというロッドが2本あるとする。1本は少しティップのほうに重心が寄っていて、もう1本はリールシートの上に重心が乗っている。これだけで人間の感じ方は大きく変わる。
てこの原理というやつである。
厳密にいえばロッドを構える角度にもよるのでやりたい釣りに合わせて最適なバランスも変わってくる。
話を戻すと、パックロッドでもバランスを突き詰めれば驚くほど軽快にロッドを操作することが出来る。
強度の問題と似たところがあるが、これは1ピースでもパックロッドも関係ない。
全ての竿は軽快に感じるために、"バランスが良い"という点は欠かせないのである。
バランスが悪い竿は自重が軽い1ピースであっても疲れてしまう。
僕のように長時間釣りを毎日する人間に"疲れない"という要素は非常に重要だ。
皆が"軽っ!"と驚くようなバランスがとれたパックロッドは多数ある。自分がロッドをプロデュースする時はその点をとても重要視している。
つまり軽快さについてもロッド次第…だと思うのだ。

※ちなみに6.2ftのプルクラ62bは自重100g。こうみると自重も大して重くなっていない気がする(笑)
▪️感度
感度について解説するのはとても難しい。
感度は使う糸、シンカーなどによっても大きく変わる。
ボトムをトントンと叩く感度から、ティップが水を掴む目感度、ラインスラックがガイドを叩く感度…etcなど、感度についてはかなり研究したから言いたいことはいっぱいあるのだけれども、しっかり説明しようとするとかなり長くなりそうだし割愛(笑)

結論から言ってしまえば実釣における感度でいえばパックロッドでなんら問題がない。
僕自身試合でも問題なくパックロッドを使うし、それが理由で何かがボヤけてしまうということはない。
感度についてはどちらかといえばその釣りに合ったロッドを選ぶ必要がある。
ガイドセッティングであったり、ティップの硬さであったり…
もし目を閉じてロッドを握って、感度の違いで1ピースかパックロッドかを完全にわかるなんて人が居たらもしかすると感度は違うかもしれない
僕はわからない自信がある(笑)
▪️パックロッドのデメリット
じゃあパックロッドにはデメリットないんかい?って突っ込まれるかもしれないが1つだけある。
それは投げてる途中で継ぎが甘くなったり、回転してしまうことだ。
継ぎが緩んだまま使っていると先が飛んでいったり、刺さりきってない状態で大きな負荷をかけてしまうとそこで折れてしまう。
それゆえにたまに継ぎの確認をしてあげることは必要不可欠である。
そのチェックが面倒くさくて出来ない…という人にはパックロッドはお勧めできない。
以上。パックロッドのリアルなインプレッション。
パックロッドもワンピースもツーピースもしっかりと設計された竿は、実戦で問題なく使えるし大差は生まれない…というのが正直な結論だ。
その代わりパックロッドのほうがその設計に手間がかかり、設計が甘いとダメな竿になりやすいというのも正直な感想である。
ウチは商品を開発するペースはめちゃめちゃ遅い。(すみません)
プロトのどこかを変更したらその部分は徹底的に強度テストしなければ不安で発売することが出来ないし、そのへんの現場チェックはかなりの時間をとって各々アングラーが行なっている。
単純に仕事が遅いのもあるかもしれないけれども(苦笑)間違いのないパックロッドを提供するためにはこれらの肯定が必要だとご理解いただけると嬉しい。
パックロッドの導入に不安を感じている方に少しでも参考になればと。
ちなみにトラセンのPVをぜひ御覧ください。
パックロッドでやりあえる魚たちをズラーッと確認いただけます。
昨今のフィッシングスタイルの多様化により、様々なメーカーよりパックロッドが発売されてる。

昔の印象とは違い、1ピースの遜色ない強度と使用感がある…というのはここ数年言われてきたこと。
既存の1ピースや2ピースと変わらないのであれば、コンパクトなほうがいいんじゃない!
っていうのは皆が納得するとこだろうけど、それと同時に「とはいえ継ぎが増えたら強度は落ちるのでは」、「重くなったり、使用感、感度が悪くなるのでは」なんてことも皆思うだろう。
この文章を書いてるビックリマン高田も、パックロッドもといマルチピースロッドメーカーであるトランスセンデンスのプロスタッフということで日頃よりパックロッドを使っている。
というかこのブログがパックロッドメーカーのブログだ(汗)
今回はそんな自分の立場を一旦忘れた上で、パックロッドのリアルについてアングラーの目線で包み隠さずお伝えしたい。
毎月25日以上。1年で300日×平均8〜10時間。
つまり1年で約3000時間ほど、フィールドに立ち続けてるプロアングラーからみたパックロッドの性能をお伝えしようと思う。

▪️強度
結論から言えば、きちんと設計されたパックロッドであれば強度不足を感じることはない。
それはほぼ全ての釣りがそうで(100kgを超えるマグロなどの魚は経験がないので別かもしれないが)、
ヘビーカバーのバスフィッシングやアカメ釣り、GTまでもパックロッドで釣りをしてるが、パックロッドであるがゆえの強度不足やトルク不足を感じたことはない。

設計がキチンとされたパックロッドで釣りに合わせて適正なパワーとロッドのアクションを選べば現場の使用で破損のリスクが高いと感じたことはない。
ロッドが破損する瞬間…というのは自分もそうであるし、仕事柄ゲスト様も含めて色々見てきた。
原因は様々で使用方法(どんな竿でも折れる…ような使い方)であったり、ロッドのパワーセレクトが釣りに合っていない、ラインの設定ミス…などがあるが、
"ロッドの設計が甘い"ことが原因になる破損も中にはある。
しかし、これは1ピースであろうがパックロッドであろうが変わらない。
1ピースでも2ピースでも設計が甘い(必要な強度を出せてなかったり、曲がる部分の設定が間違ってたり)するといとも簡単に折れてしまう。
ただし設定の難しさでいうとパックロッドのほうが難しいという現実もある。
継ぎの部分が曲がらず突っ張ってしまうことが多いのでそこを綺麗に曲がるにはパワーの細かい調整が必要である。

継ぎがない1ピースロッドは継ぎの部分の調整が必要ないので設計はいくぶん楽だ。
あとは工場ベースでの単純強度。ロッドの工場で出る破断の数値でいえば継ぎのない1ピースロッドに軍配があがる。
つまりパックロッドは丁寧に設計しなければ、折れやすいというのは正直なところである。
その代わり正しく設計されたパックロッドであれば連日のパワーフィッシングで酷使されても破損はなく、ワンピースと比べてもなんら遜色のないロッドと言える。

僕も振動や衝撃の大きいバスボートに毎日パックロッドを積んでハードな釣りをしているが、何の問題もなく機能している。
そういう意味では少なくとも僕が使ってるモデルのパックロッドについては安心してもらえるかなとも思う。
※強度不足のロッドがあればバスボートからそっと下ろします(笑)
▪️軽快さ
パックロッドは継ぎがあるので同じパワー、同じ長さ、同じ硬さのものを作ったとすれば当然1ピースのほうが自重は軽く作れる。
とにかく自重軽いロッドを…という人は1ピースを選ぶべきだろう。
しかしロッドというのは単純重量で人間の感じる重さが決まるものではないのだ。
リールをつけた時にバランスがどこにあるか…というのがとても重要なのである。
例えば自重130gというロッドが2本あるとする。1本は少しティップのほうに重心が寄っていて、もう1本はリールシートの上に重心が乗っている。これだけで人間の感じ方は大きく変わる。
てこの原理というやつである。
厳密にいえばロッドを構える角度にもよるのでやりたい釣りに合わせて最適なバランスも変わってくる。
話を戻すと、パックロッドでもバランスを突き詰めれば驚くほど軽快にロッドを操作することが出来る。
強度の問題と似たところがあるが、これは1ピースでもパックロッドも関係ない。
全ての竿は軽快に感じるために、"バランスが良い"という点は欠かせないのである。
バランスが悪い竿は自重が軽い1ピースであっても疲れてしまう。
僕のように長時間釣りを毎日する人間に"疲れない"という要素は非常に重要だ。
皆が"軽っ!"と驚くようなバランスがとれたパックロッドは多数ある。自分がロッドをプロデュースする時はその点をとても重要視している。
つまり軽快さについてもロッド次第…だと思うのだ。

※ちなみに6.2ftのプルクラ62bは自重100g。こうみると自重も大して重くなっていない気がする(笑)
▪️感度
感度について解説するのはとても難しい。
感度は使う糸、シンカーなどによっても大きく変わる。
ボトムをトントンと叩く感度から、ティップが水を掴む目感度、ラインスラックがガイドを叩く感度…etcなど、感度についてはかなり研究したから言いたいことはいっぱいあるのだけれども、しっかり説明しようとするとかなり長くなりそうだし割愛(笑)

結論から言ってしまえば実釣における感度でいえばパックロッドでなんら問題がない。
僕自身試合でも問題なくパックロッドを使うし、それが理由で何かがボヤけてしまうということはない。
感度についてはどちらかといえばその釣りに合ったロッドを選ぶ必要がある。
ガイドセッティングであったり、ティップの硬さであったり…
もし目を閉じてロッドを握って、感度の違いで1ピースかパックロッドかを完全にわかるなんて人が居たらもしかすると感度は違うかもしれない
僕はわからない自信がある(笑)
▪️パックロッドのデメリット
じゃあパックロッドにはデメリットないんかい?って突っ込まれるかもしれないが1つだけある。
それは投げてる途中で継ぎが甘くなったり、回転してしまうことだ。
継ぎが緩んだまま使っていると先が飛んでいったり、刺さりきってない状態で大きな負荷をかけてしまうとそこで折れてしまう。
それゆえにたまに継ぎの確認をしてあげることは必要不可欠である。
そのチェックが面倒くさくて出来ない…という人にはパックロッドはお勧めできない。
以上。パックロッドのリアルなインプレッション。
パックロッドもワンピースもツーピースもしっかりと設計された竿は、実戦で問題なく使えるし大差は生まれない…というのが正直な結論だ。
その代わりパックロッドのほうがその設計に手間がかかり、設計が甘いとダメな竿になりやすいというのも正直な感想である。
ウチは商品を開発するペースはめちゃめちゃ遅い。(すみません)
プロトのどこかを変更したらその部分は徹底的に強度テストしなければ不安で発売することが出来ないし、そのへんの現場チェックはかなりの時間をとって各々アングラーが行なっている。
単純に仕事が遅いのもあるかもしれないけれども(苦笑)間違いのないパックロッドを提供するためにはこれらの肯定が必要だとご理解いただけると嬉しい。
パックロッドの導入に不安を感じている方に少しでも参考になればと。
ちなみにトラセンのPVをぜひ御覧ください。
パックロッドでやりあえる魚たちをズラーッと確認いただけます。
- 2022年9月20日
- コメント(0)
コメントを見る
トランスセンデンスさんのあわせて読みたい関連釣りログ
fimoニュース
登録ライター
- 新年初買
- 6 日前
- rattleheadさん
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 9 日前
- 濵田就也さん
- メガバス:ドッグXJr.COAYU
- 11 日前
- ichi-goさん
- 野生の本能を刺激する
- 15 日前
- はしおさん
- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…
- 23 日前
- hikaruさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- 今夜は釣れた 長潮
- サカバンパスピス
-
- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!
- ハマケン















最新のコメント