▼ 春から初夏にかけての色んなベイトとゲロからの考察
まあ春から初夏にかけて色んな種類の生き物が
シーバスのエサとなる時期で、冬と比べてもその種類は様々。
ここではそんな時期に食っているシーバスが吐いた内容物や
ベイトから色々と想像を巡らせたいと思います。
まずは春の代表格 「バチ」


大きなバチから小さなバチまでシーズンや場所によってその性質は様々。
ただ、バチといってもそれだけを食っているケースもあれば
バチ以外のものも同時間帯かかなり近い時間帯に食っていることも
よくあるケース。

↑これはバチとアミ(薄ピンクぽいやつ)左端にハクのMIX。
アミに関してはすでに白か薄ピンク状態で死後時間が経過しているため
バチと同時かどうかはわからないが、左端のハクがフレッシュなので
バチとハクは同時間帯に食っていたと思われる個体。
ちなみにルアーはベイソールミノー73S。
ピンに着いている魚だったため手あたり次第流れてくるベイトを
食っていたと考えられる。

↑はフレッシュなバチと15~20cmクラスのイナッコが出てきた個体。
真ん中やや右上に見えるのがイナッコで
少し消化しかけていることからバチの時合の前段階で食われていたと
想像できる。

↑これは消化しかけたバチとオレンジ色に染まったエビ。
ピンク色のものは小魚の内臓かもはやわからないMIX状態。
たしか割と浅いところで掛けたため
ボトム付近にエビがいてもおかしくない状況下で
近い時間帯に食っていたと思われる。
次は「ハク」
ボラの幼魚で2,3cmまでのかなり小さい時のことを指して呼ぶハク。
まさに3,4月の今が最もハクシーズンで一番厄介なサイズ感のベイト。

ハクもそれだけを食っているシーバスもいればそうじゃないケースもあり
状況や場所によって様々。
↓これはオーソドックスなハクだけ食っているシーバス。



バチどう同時間帯に食われたり、アミと同時間帯に食われたり
色んなベイトとのMIXが頻繁におこるベイトの一つ。

↑これはハクの群れの中にハクより一回り大きく
薄いブルーの背中のように見えるのが稚鮎。
4~5月にかけて稚鮎の入りが多い年はこんな混在の群れを見ることができ
こうなると比較的釣りやすい印象。
「稚鮎」
これも春の代表的なベイトで
年によってかなり入ってくる数にムラがあるベイト。

イワシとの見方の違いは色も違うが
夜の場合、ライトを点けるとイワシは目が光るのでそれでわかる。
稚鮎を照らしてもイワシのように目は光らない。

これがたくさん入ってくれる年はハクだけたくさんいる年に比べて
遥かに釣りやすく釣れるルアーにも幅が出てくるので
できれば毎年たくさん入って来て欲しいのが本音。
東京の港湾にも河川にもたくさんいるので食われるシーンは時々目撃する。
「アミ」
体長 数ミリ~10ミリほどのイサザアミ。
これを偏食するのは冬~夏にかけてと幅広く
春~初夏の港湾では色んなベイトに混ざって
食われていることの多いベイト。

冬~春は偏食が強くアミしか出てこないことも多く

潮のタイミングでバチが出る潮だと
バチと一緒に出てくることもよくあるケース。

↑はまだ透明なフレッシュのアミとフレッシュなバチが出てきたパターン。
同時間帯に両方を食っている可能性が高い個体。

↑これはすでに消化しきって液状化したバチスープとアミ。
釣ったのが上げだったので下げでバチを食って
上げでアミを食っていた個体。
「イワシ」
春になりプランクトンが増えてくると入る可能性が高くなるイワシ。

↑の写真は青みがかった背中に光った目のイワシと
薄茶色の背中でやや体腔のあるサッパの混在した群れ。


イワシが入るとなんだかんだイワシばっかり食っていることが多いが
今年のようにハクが多い年はそうしたベイトと混在した内容物が出ることも。
イワシが入るとおのずと釣りやすくなる有難いベイトの一つ。
「ハゼ」

春~夏にかけて育ってくるデキハゼ。
5月ごろには5cmくらいのサイズのハゼも見られ運河や河川などで大量に沸くハゼ。
群れのイワシやサッパ、ハクやイナッコなどが居ない場合もハゼが付くような
地形のポイントを狙えば居着きでハゼやエビを食っているシーバスが獲れる。
レアケースだが、大雨後は酸欠になったハゼが水面に浮き
それにボイルすることもあり、ハゼパターンなのにトップということも。
またハゼの仲間でチチブ属も貴重なベイトの一つ。


ハゼ並みにたくさんいるものの縄張り意識が強いのか
ハゼよりもゴロタや壁際など何か隠れるところがあるようなところに
密接していることがほとんどなのでそうしたところを攻めれば攻めるほど
チチブを食っているシーバスをキャッチする確率が高い。
そうしたところはエビも豊富にいるのでチチブやハゼと同時にエビが出てくることも。
春のイレギュラーなベイトとしては
「メゴチ」


春に運河の中で釣った時に吐き出したメゴチ。
ミニエントでボトム付近を探っていた時に釣った個体。
「シャコ」

初夏に運河ではなくやや水深のある港湾の岸壁のボトム付近で掛けた
シーバスから出てきたベイト。
たしかブレード系のルアーでボトムを探っていたときに掛けた魚が吐きだしたシャコ。
それ以外に今まで食っているシーンを見たり吐いたりしたことがあるのは
サイマキやガザミ、テッポウエビにイカ。
季節柄、色んなレアベイトがいるけどそれだけ暖かくなると
種類も豊富になってきて色んなベイトを食うシーバスが出てくる季節ということ。
まだまだ解明されていないベイトパターンが存在しているかも!?
とはいえまずはハクを何とかしないとですな
シーバスのエサとなる時期で、冬と比べてもその種類は様々。
ここではそんな時期に食っているシーバスが吐いた内容物や
ベイトから色々と想像を巡らせたいと思います。
まずは春の代表格 「バチ」


大きなバチから小さなバチまでシーズンや場所によってその性質は様々。
ただ、バチといってもそれだけを食っているケースもあれば
バチ以外のものも同時間帯かかなり近い時間帯に食っていることも
よくあるケース。

↑これはバチとアミ(薄ピンクぽいやつ)左端にハクのMIX。
アミに関してはすでに白か薄ピンク状態で死後時間が経過しているため
バチと同時かどうかはわからないが、左端のハクがフレッシュなので
バチとハクは同時間帯に食っていたと思われる個体。
ちなみにルアーはベイソールミノー73S。
ピンに着いている魚だったため手あたり次第流れてくるベイトを
食っていたと考えられる。

↑はフレッシュなバチと15~20cmクラスのイナッコが出てきた個体。
真ん中やや右上に見えるのがイナッコで
少し消化しかけていることからバチの時合の前段階で食われていたと
想像できる。

↑これは消化しかけたバチとオレンジ色に染まったエビ。
ピンク色のものは小魚の内臓かもはやわからないMIX状態。
たしか割と浅いところで掛けたため
ボトム付近にエビがいてもおかしくない状況下で
近い時間帯に食っていたと思われる。
次は「ハク」
ボラの幼魚で2,3cmまでのかなり小さい時のことを指して呼ぶハク。
まさに3,4月の今が最もハクシーズンで一番厄介なサイズ感のベイト。

ハクもそれだけを食っているシーバスもいればそうじゃないケースもあり
状況や場所によって様々。
↓これはオーソドックスなハクだけ食っているシーバス。



バチどう同時間帯に食われたり、アミと同時間帯に食われたり
色んなベイトとのMIXが頻繁におこるベイトの一つ。

↑これはハクの群れの中にハクより一回り大きく
薄いブルーの背中のように見えるのが稚鮎。
4~5月にかけて稚鮎の入りが多い年はこんな混在の群れを見ることができ
こうなると比較的釣りやすい印象。
「稚鮎」
これも春の代表的なベイトで
年によってかなり入ってくる数にムラがあるベイト。

イワシとの見方の違いは色も違うが
夜の場合、ライトを点けるとイワシは目が光るのでそれでわかる。
稚鮎を照らしてもイワシのように目は光らない。

これがたくさん入ってくれる年はハクだけたくさんいる年に比べて
遥かに釣りやすく釣れるルアーにも幅が出てくるので
できれば毎年たくさん入って来て欲しいのが本音。
東京の港湾にも河川にもたくさんいるので食われるシーンは時々目撃する。
「アミ」
体長 数ミリ~10ミリほどのイサザアミ。
これを偏食するのは冬~夏にかけてと幅広く
春~初夏の港湾では色んなベイトに混ざって
食われていることの多いベイト。

冬~春は偏食が強くアミしか出てこないことも多く

潮のタイミングでバチが出る潮だと
バチと一緒に出てくることもよくあるケース。

↑はまだ透明なフレッシュのアミとフレッシュなバチが出てきたパターン。
同時間帯に両方を食っている可能性が高い個体。

↑これはすでに消化しきって液状化したバチスープとアミ。
釣ったのが上げだったので下げでバチを食って
上げでアミを食っていた個体。
「イワシ」
春になりプランクトンが増えてくると入る可能性が高くなるイワシ。

↑の写真は青みがかった背中に光った目のイワシと
薄茶色の背中でやや体腔のあるサッパの混在した群れ。


イワシが入るとなんだかんだイワシばっかり食っていることが多いが
今年のようにハクが多い年はそうしたベイトと混在した内容物が出ることも。
イワシが入るとおのずと釣りやすくなる有難いベイトの一つ。
「ハゼ」

春~夏にかけて育ってくるデキハゼ。
5月ごろには5cmくらいのサイズのハゼも見られ運河や河川などで大量に沸くハゼ。
群れのイワシやサッパ、ハクやイナッコなどが居ない場合もハゼが付くような
地形のポイントを狙えば居着きでハゼやエビを食っているシーバスが獲れる。
レアケースだが、大雨後は酸欠になったハゼが水面に浮き
それにボイルすることもあり、ハゼパターンなのにトップということも。
またハゼの仲間でチチブ属も貴重なベイトの一つ。


ハゼ並みにたくさんいるものの縄張り意識が強いのか
ハゼよりもゴロタや壁際など何か隠れるところがあるようなところに
密接していることがほとんどなのでそうしたところを攻めれば攻めるほど
チチブを食っているシーバスをキャッチする確率が高い。
そうしたところはエビも豊富にいるのでチチブやハゼと同時にエビが出てくることも。
春のイレギュラーなベイトとしては
「メゴチ」


春に運河の中で釣った時に吐き出したメゴチ。
ミニエントでボトム付近を探っていた時に釣った個体。
「シャコ」

初夏に運河ではなくやや水深のある港湾の岸壁のボトム付近で掛けた
シーバスから出てきたベイト。
たしかブレード系のルアーでボトムを探っていたときに掛けた魚が吐きだしたシャコ。
それ以外に今まで食っているシーンを見たり吐いたりしたことがあるのは
サイマキやガザミ、テッポウエビにイカ。
季節柄、色んなレアベイトがいるけどそれだけ暖かくなると
種類も豊富になってきて色んなベイトを食うシーバスが出てくる季節ということ。
まだまだ解明されていないベイトパターンが存在しているかも!?
とはいえまずはハクを何とかしないとですな
- 2021年5月3日
- コメント(1)
コメントを見る
大野ゆうきさんのあわせて読みたい関連釣りログ
fimoニュース
登録ライター
- スミス:ディプシードゥMAX
- 6 日前
- ichi-goさん
- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…
- 7 日前
- hikaruさん
- 新年初買
- 12 日前
- rattleheadさん
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 15 日前
- 濵田就也さん
- 野生の本能を刺激する
- 22 日前
- はしおさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪
- ハマケン
-
- 流れの釣り
- Kazuma




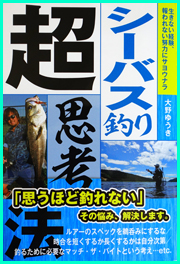
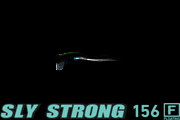




















最新のコメント