プロフィール

APIA
大阪府
プロフィール詳細
カレンダー
検索
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:10
- 昨日のアクセス:348
- 総アクセス数:6769094
タグ
- アピアスタッフ日記
- 中井佑一郎
- 製品情報
- 釣行記
- RED中村
- 村岡昌憲
- 濱本国彦
- 献上真也
- 金丸竜児
- 北添貴行
- ウッティーダ
- 平林・特命係長
- 安田ヒロキ
- ショ~ゴ!!
- 梶谷傳則
- 永島規史
- 藤本昌大
- 中嶋康文
- 阪中豊博
- 鈴木達也
- 宇津木善生
- 皇帝
- 営業:中平
- 井戸川真吾
- シーバス
- ライトゲーム
- ロックフィッシュ
- ショアジギング
- インフォメーション
- フィッシングショー
- 試投会
- イベント
- APIA TV
- 凄腕
- Foojin'Z
- Foojin'AD
- JAILBREAKER 92MX
- GRANDAGE
- GRANDAGE STD C88M
- Foojin'R
- Foojin'BB
- QUATTRO BLACK
- BLACKLINE/EXTREAM
- Legacy'SC
- STAYGOLD
- Legacy'BLUELINE
- Brute'HR
- Foojin'XXCRAZYCARRY 103MHX
- VENTURA
- PUNCH LINE
- PUCH LINE MUSCLE
- PUCH LINE 130
- PUNCH LINE 45/60
- LAMMTARRA・BADEL
- BADEL105
- LAMMTARRA GIANT177
- BAGRATION
- GABLIN125F
- ハイドロアッパー
- HYDROUPPER90S
- HYDRO UPPER 55S
- HYDRO UPPER SLIM 100S
- H bait:エイチベイト
- エルドール115F
- DOVER120F
- DOVER99F
- DOVER99S
- DOVER82S
- DOVER120F Riva
- New bit-V(12-26)
- bit-V/bit-V32
- LUCK-V
- LUCK-V Ghost
- GOLD ONE
- PRONTO
- ARCH HEAD
- SEIRYU HYPER
- SEIRYU
- ENRYU
- BRIGANTE160SW
- CHINUPARA DODGE
- CARBONWADINGNET Ⅲ
- Xband
- 青物
- GRANDAGE LITE
- DOVER 46SS
- OTHERS
- 開発
- 国盗り合戦
- DOVER70FSR
- HYDOROUPPER100S
- Z stage(ゼータステージ)
- 池田延夫
- 大津昂彦
- 加藤 宏崇
▼ ロッドのお話 その3 by 松本
アピアの松本です。
2013年も残すところあと僅かとなりました。
本年も格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
本年中の御愛顧に心より御礼申し上げますと共に、
来年も弊社製品の変わらぬご支援ご愛顧のほど、
よろしくお願い申し上げます。
と、カタいご挨拶はおいておきまして・・・アピアで仕事を始めて早4ヶ月。
まだまだ、新人ぶり(?)をいたるところで発揮しておりますが、今年は色々な意味で本当に多くの方に支えられ、一年を終えることができました。
この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
来年も頑張ってまいりますので、何卒、お願い申し上げます。
さて、いろいろな作業が佳境を迎えております・・・。
で、昨日は小職がブログ当番だったのをすっかり忘れて、
うっかり穴を開けてしまいました・・・。
このところ連日、カタログのテキストライティングが続いていたこともあり、その流れでやたらと文字の多いログになってしまいましたが、ご興味のある方はお付き合い願います。
私が携わる製品において、いつも留意していることがあります。それはロッド(ブランク)にはそれぞれの用途・目的に対して必要な要素の具現化に際して、ゴールデンカノン(黄金比率)ともいうべき必要な‘質量’というものがある、という考えに基づき、‘リフティングパワーと高い破損荷重強度を備えたモノであること’の上に成り立つ、‘トータルバランスの高さからなる軽量感、使用感の良さ’があることに重きを置いているということです。
ちなみに、ロッドの製造業において、基本的にはブランクを構成しているカーボンに対する弾性率の割合表記に関する規格規定(何トンが何%というものですね)というものが無いので、少しでも高弾性素材を含んでいれば‘高弾性のブランクです’、と謳うことができる(できちゃう?)のですが、実際、このへんは個々のメーカーさんのスタンスによりけりです。
例えるなら、24(t)トンが9割、35(t)トンが1割でも‘高弾性ロッドです!’と、言えてしまうワケです。
もちろん、弊社ではブランクが命である以上、死んでもそんなことは言いませんが。(ちなみに往年の人気素材・ボロンについても‘ボロンロッド’と表記するには
○%以上の含有率が必要、という規定がありましたが、だいぶ前に廃止されました。)
今回は、コスト・品質の両面からロッドメーカー/アングラーとしての視点を以て、確かな見極めが必要なロッドメイキングのプロセスに介在する色々な‘選択’、その一つとしてのロッドの継ぎ目(フェルール)について触れてみたいと思います。
まずはこちらの写真をご覧くださいませ。

左側がスピゴットフェルール(印籠継ぎ)、
右側がフェラライトフェルール/プットオーバーフェルール
(逆並継ぎ)です。
妄想戦士の私には何だかステキな響きですが、以下略・・・。
そして、それぞれの相違について。

少し分かりにくいかもしれませんが、上の写真の左側が印籠継、右側が逆並継ぎのそれぞれの接合(嵌合:カンゴウ)部となり、左側の、ブランクに‘ペグ’(接合のための‘芯’:別のブランク)が挿入されているというのがスピゴットの特徴です。対して逆並継は接合部付近のブランクそのものに、着脱される別のブランクを接合するというのが特徴です。いずれの場合も接合部には脱着のための加工(研磨・塗膜であったり、カーボンシートが余分に巻いてある)がなされています。
まずは、接合した状態での‘継ぎ目のスキマ’について。2つ上の写真でご覧いただけるものを基本として、接合部に10~15mmのマージンをとっております。(固着・抜けの防止のため)
新品の状態では、経年変化によるフェルール部のスリ減り(肉痩せ)を想定して、あらかじめ長めにマージンを見越した研磨加工、セッティングを施しております。
使用(着脱/抜き差し)を繰り返すうち、フェルール部の脱着もより滑らかになっていきます。ごく稀にお客様よりお問い合わせをいただく‘肉痩せ’(着脱を繰り返すうちに、差込シロが深くなる現象)に関しましても5mm程度のスキマがあれば、実際の使用において、継ぎ目が抜けてしまうような事はございません。
*一般の使用においては相当回数の脱着を想定しております。刺さり過ぎるのでは?など不具合を感じられる場合、がたつきや異音についてもお気づきの点がございましたら、弊社製品取扱店さままでご相談ください。
次に一昔前には良く耳にした、スピゴットフェルール(印籠継ぎ)とフェラライトフェルール(並継ぎ)という構造上の差異による性能の優劣に関して。
まず、本題に入る前に、製造方法の違いについてご説明。
ロッドの製作過程において、お聞きしたことのある物の一つに‘マンドレル(鉄芯)’というものがございます。ブランクを窯で焼成する際、カーボンシートを巻きつけるための鉄の棒、ルアー製作などで言えば、金型に当たるものなのですが、例えば同じレングス、パワー、アクションのシーバスロッドを製作するとして、印籠継と逆並継ぎ、接合部の相違によって、このマンドレルも全く別個の物を用います。
エンジニア的な視点から捉えると、設計の自由度(アクション・パワー)が高いのは逆並継になります。2本継ぎのロッドであれば、#1(1番:穂先)と#2(2番:元竿)の一対のマンドレルを用意することで、ある程度、ロッドアクションやパワーの変更をすることが容易です。
ところが、接合部の#1、#2の2本のブランク径がより近似する印籠継は、専用のマンドレルが必要となるため、ロッドアクションやパワーを大きく変更しようとすると、マンドレルごと変更しなければならなくなることがあるのです。このため、印籠継のロッド製作と言うのは必然的にコストがかかります。
一昔前までは、スピゴットフェルール(印籠継ぎ)のロッドに、使用上の優位点まで盛り込まれていることが多かったのですが、実際には、現在の設計・製造技術においては接合の種類によって、‘抜け’やロッドアクションの優劣が左右されることはございません。
一時には、見かけを印籠継のように仕上げているような商品も市場に多く見受けられましたが、全体の曲がりを一瞥することで判断できるものもあります。(元竿から穂先へのパワーの伝達、ベンドカーブがスムーズでないものなどは瞬間的な負荷に脆く折れやすいものなどがあったりします。)
印籠継のロッドが高価格帯・上級機種に採用されることが多いのは製竿工程のあらゆるプロセスにおいて高い精度が要求される部分が多いというのがその理由のひとつであり、適材適所は勿論ございますが、弊社としては価格に応じて、より難易度の高いものを採用することで、ロッドとしての価値観を感じていただきやすいよう留意しております。
もちろん、用途・目的に応じた最適な構造を採択するのが大前提ではあります。
以上のことから、弊社では印籠継と逆並継という構造上の相違によって生じるアクションや着脱性などに関する差異はほとんど認められないと結論を出しております。(もちろん、印籠継にはブランクの細身化によるキャストフィールの向上など、メリットもございますが、極端にハイテーパーのブランク製作などには不向きであったりという側面もあります。)
と、上記のお話を踏まえた上での余談ですが、前述の同レングス・パワー・アクションのロッドをそれぞれのフェルールで製作すると、必然的に逆並継の方がバランスをとり易くなります。スピゴットはペグの自重が元竿の先端に掛かることで、バランスを逸してしまうことも起こりえます。(当然、そうならないように軽量バランスを考慮するのが高い設計技術・製竿技術といえます)
これらのことも、印籠継のロッド製作は手間が掛かる・難易度が高い、ということが言える要因のひとつです。
弊社では設計の自由度の高さや加工の容易度など、フィッシングロッドとしての本質を考慮すればメリットが少なくない逆並継で高い性能を享受できるところ、あえて印籠継を採用しているのものが多いですが、これらは高い製竿技術によるものに他なりません。
但し、ここもロッドとして求める要素、必要な特性やコストの確かな見極め、要・不要をしっかりと吟味して、‘何を選択すべきか’をどのように結論付けるのかが肝要なのです。
また最後に、冒頭でも少し触れましたが、前々回の小職のログ絡みでご質問いただくことが多かったものとして、皆さんもよく耳にされる・気になる‘弾性率’(○トンカーボンていうアレです)について、 何トンが低弾性で、何トンからが中弾性、何トン以上が高弾性という表記に関するお問い合わせをいただきました。
この辺の認識については、釣具業界では割と曖昧に表現されていますが、例えば、弊社では35t以上からを高弾性としております。
ちなみに炭素繊維製品の力学的性能別分類(日本炭素繊維協会さんなどで定められている)からすれば、おおよそ24t.、26t./30t.などは標準弾性/中弾性、35(t)、40(t)が高弾性、弊社では使用しませんが、60t以上が超高弾性、16tは低弾性とされます。カタログなどでのロッドのテイストに関する表記については、それぞれの特性を端的に表したモノとなっております。
また、19(t)てないの?とか31(t)てないの?と思われる方もおられるかも知れませんが、おおよそ上記したようなところがプリプレグ(カーボンシート)供給メーカーさんの一般的な製造規格となっています。
誤解のないようお伝えしておきたいのは、高弾性だからイイ、ということではナイ、ということです。
素材原価としては、一般的に高弾性のものが高価とされておりますが、一概にそうでないものもあり、目的・用途に応じて素材を吟味・選定し、その特性をきちんと引き出してあげることが肝要だというのは、以前にもお話させていただいたとおりです。
さらに一つの道具(ロッド)としてきちんと成り立たないと素材のよさやその特性も伝わらないという思いのもと、日々、ロッドメイキングに勤しんでおります。
例によって、まとまりのない文章になってしまいましたが、次回はややこしいお話ではなく、とある製品について触れてみたいと思います。
それでは皆さま、良い年の瀬をお過ごしくださいませ。
来年もより良いロッドメイキングに努めてまいりますので、これからのアピアに是非、ご期待ください!
2013年も残すところあと僅かとなりました。
本年も格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
本年中の御愛顧に心より御礼申し上げますと共に、
来年も弊社製品の変わらぬご支援ご愛顧のほど、
よろしくお願い申し上げます。
と、カタいご挨拶はおいておきまして・・・アピアで仕事を始めて早4ヶ月。
まだまだ、新人ぶり(?)をいたるところで発揮しておりますが、今年は色々な意味で本当に多くの方に支えられ、一年を終えることができました。
この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
来年も頑張ってまいりますので、何卒、お願い申し上げます。
さて、いろいろな作業が佳境を迎えております・・・。
で、昨日は小職がブログ当番だったのをすっかり忘れて、
うっかり穴を開けてしまいました・・・。
このところ連日、カタログのテキストライティングが続いていたこともあり、その流れでやたらと文字の多いログになってしまいましたが、ご興味のある方はお付き合い願います。
私が携わる製品において、いつも留意していることがあります。それはロッド(ブランク)にはそれぞれの用途・目的に対して必要な要素の具現化に際して、ゴールデンカノン(黄金比率)ともいうべき必要な‘質量’というものがある、という考えに基づき、‘リフティングパワーと高い破損荷重強度を備えたモノであること’の上に成り立つ、‘トータルバランスの高さからなる軽量感、使用感の良さ’があることに重きを置いているということです。
ちなみに、ロッドの製造業において、基本的にはブランクを構成しているカーボンに対する弾性率の割合表記に関する規格規定(何トンが何%というものですね)というものが無いので、少しでも高弾性素材を含んでいれば‘高弾性のブランクです’、と謳うことができる(できちゃう?)のですが、実際、このへんは個々のメーカーさんのスタンスによりけりです。
例えるなら、24(t)トンが9割、35(t)トンが1割でも‘高弾性ロッドです!’と、言えてしまうワケです。
もちろん、弊社ではブランクが命である以上、死んでもそんなことは言いませんが。(ちなみに往年の人気素材・ボロンについても‘ボロンロッド’と表記するには
○%以上の含有率が必要、という規定がありましたが、だいぶ前に廃止されました。)
今回は、コスト・品質の両面からロッドメーカー/アングラーとしての視点を以て、確かな見極めが必要なロッドメイキングのプロセスに介在する色々な‘選択’、その一つとしてのロッドの継ぎ目(フェルール)について触れてみたいと思います。
まずはこちらの写真をご覧くださいませ。

左側がスピゴットフェルール(印籠継ぎ)、
右側がフェラライトフェルール/プットオーバーフェルール
(逆並継ぎ)です。
妄想戦士の私には何だかステキな響きですが、以下略・・・。
そして、それぞれの相違について。

少し分かりにくいかもしれませんが、上の写真の左側が印籠継、右側が逆並継ぎのそれぞれの接合(嵌合:カンゴウ)部となり、左側の、ブランクに‘ペグ’(接合のための‘芯’:別のブランク)が挿入されているというのがスピゴットの特徴です。対して逆並継は接合部付近のブランクそのものに、着脱される別のブランクを接合するというのが特徴です。いずれの場合も接合部には脱着のための加工(研磨・塗膜であったり、カーボンシートが余分に巻いてある)がなされています。
まずは、接合した状態での‘継ぎ目のスキマ’について。2つ上の写真でご覧いただけるものを基本として、接合部に10~15mmのマージンをとっております。(固着・抜けの防止のため)
新品の状態では、経年変化によるフェルール部のスリ減り(肉痩せ)を想定して、あらかじめ長めにマージンを見越した研磨加工、セッティングを施しております。
使用(着脱/抜き差し)を繰り返すうち、フェルール部の脱着もより滑らかになっていきます。ごく稀にお客様よりお問い合わせをいただく‘肉痩せ’(着脱を繰り返すうちに、差込シロが深くなる現象)に関しましても5mm程度のスキマがあれば、実際の使用において、継ぎ目が抜けてしまうような事はございません。
*一般の使用においては相当回数の脱着を想定しております。刺さり過ぎるのでは?など不具合を感じられる場合、がたつきや異音についてもお気づきの点がございましたら、弊社製品取扱店さままでご相談ください。
次に一昔前には良く耳にした、スピゴットフェルール(印籠継ぎ)とフェラライトフェルール(並継ぎ)という構造上の差異による性能の優劣に関して。
まず、本題に入る前に、製造方法の違いについてご説明。
ロッドの製作過程において、お聞きしたことのある物の一つに‘マンドレル(鉄芯)’というものがございます。ブランクを窯で焼成する際、カーボンシートを巻きつけるための鉄の棒、ルアー製作などで言えば、金型に当たるものなのですが、例えば同じレングス、パワー、アクションのシーバスロッドを製作するとして、印籠継と逆並継ぎ、接合部の相違によって、このマンドレルも全く別個の物を用います。
エンジニア的な視点から捉えると、設計の自由度(アクション・パワー)が高いのは逆並継になります。2本継ぎのロッドであれば、#1(1番:穂先)と#2(2番:元竿)の一対のマンドレルを用意することで、ある程度、ロッドアクションやパワーの変更をすることが容易です。
ところが、接合部の#1、#2の2本のブランク径がより近似する印籠継は、専用のマンドレルが必要となるため、ロッドアクションやパワーを大きく変更しようとすると、マンドレルごと変更しなければならなくなることがあるのです。このため、印籠継のロッド製作と言うのは必然的にコストがかかります。
一昔前までは、スピゴットフェルール(印籠継ぎ)のロッドに、使用上の優位点まで盛り込まれていることが多かったのですが、実際には、現在の設計・製造技術においては接合の種類によって、‘抜け’やロッドアクションの優劣が左右されることはございません。
一時には、見かけを印籠継のように仕上げているような商品も市場に多く見受けられましたが、全体の曲がりを一瞥することで判断できるものもあります。(元竿から穂先へのパワーの伝達、ベンドカーブがスムーズでないものなどは瞬間的な負荷に脆く折れやすいものなどがあったりします。)
印籠継のロッドが高価格帯・上級機種に採用されることが多いのは製竿工程のあらゆるプロセスにおいて高い精度が要求される部分が多いというのがその理由のひとつであり、適材適所は勿論ございますが、弊社としては価格に応じて、より難易度の高いものを採用することで、ロッドとしての価値観を感じていただきやすいよう留意しております。
もちろん、用途・目的に応じた最適な構造を採択するのが大前提ではあります。
以上のことから、弊社では印籠継と逆並継という構造上の相違によって生じるアクションや着脱性などに関する差異はほとんど認められないと結論を出しております。(もちろん、印籠継にはブランクの細身化によるキャストフィールの向上など、メリットもございますが、極端にハイテーパーのブランク製作などには不向きであったりという側面もあります。)
と、上記のお話を踏まえた上での余談ですが、前述の同レングス・パワー・アクションのロッドをそれぞれのフェルールで製作すると、必然的に逆並継の方がバランスをとり易くなります。スピゴットはペグの自重が元竿の先端に掛かることで、バランスを逸してしまうことも起こりえます。(当然、そうならないように軽量バランスを考慮するのが高い設計技術・製竿技術といえます)
これらのことも、印籠継のロッド製作は手間が掛かる・難易度が高い、ということが言える要因のひとつです。
弊社では設計の自由度の高さや加工の容易度など、フィッシングロッドとしての本質を考慮すればメリットが少なくない逆並継で高い性能を享受できるところ、あえて印籠継を採用しているのものが多いですが、これらは高い製竿技術によるものに他なりません。
但し、ここもロッドとして求める要素、必要な特性やコストの確かな見極め、要・不要をしっかりと吟味して、‘何を選択すべきか’をどのように結論付けるのかが肝要なのです。
また最後に、冒頭でも少し触れましたが、前々回の小職のログ絡みでご質問いただくことが多かったものとして、皆さんもよく耳にされる・気になる‘弾性率’(○トンカーボンていうアレです)について、 何トンが低弾性で、何トンからが中弾性、何トン以上が高弾性という表記に関するお問い合わせをいただきました。
この辺の認識については、釣具業界では割と曖昧に表現されていますが、例えば、弊社では35t以上からを高弾性としております。
ちなみに炭素繊維製品の力学的性能別分類(日本炭素繊維協会さんなどで定められている)からすれば、おおよそ24t.、26t./30t.などは標準弾性/中弾性、35(t)、40(t)が高弾性、弊社では使用しませんが、60t以上が超高弾性、16tは低弾性とされます。カタログなどでのロッドのテイストに関する表記については、それぞれの特性を端的に表したモノとなっております。
また、19(t)てないの?とか31(t)てないの?と思われる方もおられるかも知れませんが、おおよそ上記したようなところがプリプレグ(カーボンシート)供給メーカーさんの一般的な製造規格となっています。
誤解のないようお伝えしておきたいのは、高弾性だからイイ、ということではナイ、ということです。
素材原価としては、一般的に高弾性のものが高価とされておりますが、一概にそうでないものもあり、目的・用途に応じて素材を吟味・選定し、その特性をきちんと引き出してあげることが肝要だというのは、以前にもお話させていただいたとおりです。
さらに一つの道具(ロッド)としてきちんと成り立たないと素材のよさやその特性も伝わらないという思いのもと、日々、ロッドメイキングに勤しんでおります。
例によって、まとまりのない文章になってしまいましたが、次回はややこしいお話ではなく、とある製品について触れてみたいと思います。
それでは皆さま、良い年の瀬をお過ごしくださいませ。
来年もより良いロッドメイキングに努めてまいりますので、これからのアピアに是非、ご期待ください!
- 2013年12月28日
- コメント(1)
コメントを見る
APIAさんのあわせて読みたい関連釣りログ
GAN CRAFT(ガンクラフト) ルアー ジョインテッドクローマグナム230SS
posted with amazlet at 17.11.29
GAN CRAFT(ガンクラフト)
fimoニュース
登録ライター
- スミス:ディプシードゥMAX
- 7 日前
- ichi-goさん
- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…
- 8 日前
- hikaruさん
- 新年初買
- 14 日前
- rattleheadさん
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 16 日前
- 濵田就也さん
- 野生の本能を刺激する
- 23 日前
- はしおさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪
- ハマケン
-
- 流れの釣り
- Kazuma


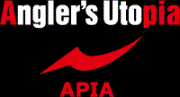









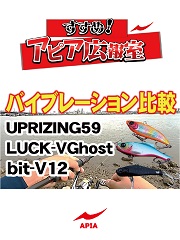




偶然の産物は単発で終わることが多いですが、御社から創り出された作品達は、やはりトータルバランスを意識して設計されていたのですね。
私はまさにこのトータルバランスに惚れました。
貴方の様な職人が、私の手元に作品を届けてくれる事を感謝します。
その信念は、決して曲げないで下さい。
Odin2