プロフィール

rattlehead
東京都
プロフィール詳細
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:126
- 昨日のアクセス:190
- 総アクセス数:2230866
タグ
QRコード
検索
▼ 活性の違いにおける曳波の使い分け
- ジャンル:ニュース
- (元style-攻略法)
バチシーズンも終わるって頃に、まだバチかよという意見はごもっとも。
まあ、今年はあんな状況だったんで、仕方ないじゃないっすか。
来年に向けてのイメトレ時期だと割り切って下さい(笑)
さて、表題の件。
バチ時って、活性の有る無しがシーズン通して最も解り易いタイミングだと思う。
というのは、私のホームは水深が結構あるせいか人通りが多いせいか、秋にライズするポイントって本当に限られている。
明け方にライズしてる事は結構あるんだけど、朝弱いのよ…(泣)
レンジ入れる釣りの場合でも入れ食いになる事が多々あるが、それは「活性」によるものか「上手く嵌った」だけなのか定かじゃない。
その点、バチシーズンは視覚・聴覚で活性が確認出来るので、誰でもが判断し易いと思う。
で、このバチ活性って、活性が高い/低いに2つのパターンがある。
一つは、辺り一面で餌に狂ってライズしてる状態。berserkと言いますか。簡単に言えば「集団活性」。
ベイトと一緒で、「適当に突っ込んでりゃ餌口に入るだろ」位の状況で水面を割っているシーンを思い起してくれれば。
(勿論、魚はちゃんと狙ってるんだろうけど)
これは全面トリッキーになった時に起こり易い現象。
「こんなに魚居るのかよ…」と己の無力さを感じる瞬間でもある(爆)
もう一つは、言うなれば「個体活性」。
一番判り易いのが、ライズ音。
同じ捕食でも派手に出てるのは活性が高いし、小さなライズリングのみの時は低い。
「サイズの違いじゃね?」というのは全くの見当違いで、サイズ差の場合は音質が変わります。
派手と地味でも音質は違いますが、その辺りを口で説明するのは非常に困難で…
以前「カクテルパーティー効果」という話をした事がありますが、それの延長で、慣れてくるとその違いがはっきりと判ると思います。
「これは(ルアーを)食ってくるライズ音」「これは微妙(だけど投げる)」「狙うだけ無駄(でも投げる(爆))」みたいに。
それだけでも、ヒット率がぐっと上昇します。
で、本題。
その場の状況判断が出来たとしても、ただ闇雲にルアーを投げていても非効率極まりない。
あ、くれぐれも言っておきますが、私、バチでシンペンの釣りは一切やりません。
なので、シンペンだと闇雲に投げた方が効率が良いかも知れませんので、それはご自身で判断して下さい。
そこで行うのが「曳波の使い分け」。
以前「寄せの曳波」と「食わせの曳波」という話は書きました。
そのコンセプトは変わってませんが、ルアーが変わった為、更に細分化されてしまっているという(爆)
で、あの時は二次元での話で終わりましたが、今回は三次元での話になります。
簡単に図解すると、こんな感じ。イメージwは伝わるかと。
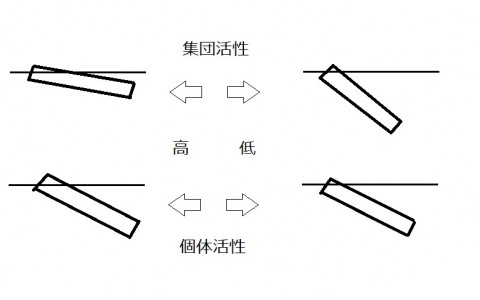
何が言いたいかというと、高活性時にはルアーを浮かせ、低活性時には若干沈める。
が、沈め方が異なって、集団活性が高い時にはリアを軽くし、個体活性時が高い時は全体を軽くする。
因みに、調整幅は0.02g毎+現地チェック。
私がバチに使うのは#10~#6のトリプルフックなのだが、メーカー/針種の違いで大体0.02g違いで揃えられる。
これに、#0~#3のリングを組み合わせて使うと、大概の調整は可能となる。
で、これをその時の状況に応じて使い分けるって訳。
当然高/低2種ではなく、その中間だって幾つか存在する。それに色違いとかやってると…
こんなんやってっから、他のルアーが使えなくなるんだよっっ(爆)
多分上の図を見て、気付いた方は多いと思うので先に書いておきます。
頭が出てるのだから、水を受ければ必然的にリアが浮くか、ヘッド形状によっては潜るよね?と。
だから巻きスピード=リズム感が必要なのです
これは以前から公言してますが、私が人より少しだけ優れてると思われるのは、キャスト精度と音感。
任意で一定のスピードで巻く事が出来れば、後は風の影響だけ考えて調整すれば良い。
それでも調整出来ない場合の為に、細かく調整を施した多くの同種ルアーを持ち込む訳です。
これが、ここ数年廃盤トップ1と2しか使ってない理由です。
で、この様なチューニングをする根拠を少し。
個体活性の場合、当初は「上まで出てこないんだから、針位置を下げれば掛かるんじゃね?」という助平心(笑)
で、2~3㎜レンジを下げてみたら、結構釣れるようになる。(これがトップのレンジはミリ単位と言ってる根拠)
それなら、と、針位置だけを下げてみると、面白い事に全然反応が悪い。
って事で、方向性は判ったが、それが微細な曳波による物か、水面下の存在感による物かは不明(←今後の検証材料w)
もしかすると、レンジを下げる→水受け面積が大きくなる→ルアーが動く→ボディの波動?www
集団活性の場合、ほぼほぼ全面トリッキーの時に起こる事から、当初は「トリッキーっぽくケツ振れば良いんじゃね?」という、これまた助平心(笑)
シンペンならば基本ケツ振りなので、何も考えないで良い。
が、その頃から「絶対に沈めねぇ」を信条としていた事もあり、「ならリアを軽くすればケツ振るんじゃね?」と。
そこから調整を入れ始めたら、面白い現象が。
水面上の表面積は上がっているのに、「細い曳波」が立つようになった。
これはヘッド形状からくる恩恵かと思うが、それによりトリッキー独特の細かい波紋に近い曳波が出る様に。
狙い通りリアも僅かだが振れてくれ(これまた波動?www) 、全面ライズ時に最も釣れるチューニングに。
そして、現在に至ります。
勿論上記の物は廃盤トップ1・2のヘッド形状・比重・サイズから出た結果であり、他のルアーでどうなるかは全く判りません。
「他のルアーでもやれよ」と言われるかも知れませんが、まだこのルアーで検証しなければならない事が多々あり、そんな余裕はありません。
ただ、例え一つのルアーだとしても明らかな結果が出ている訳で、それが他にも応用出来れば…という意図で書いてみました。
参考になれば幸いです♪
まあ、今年はあんな状況だったんで、仕方ないじゃないっすか。
来年に向けてのイメトレ時期だと割り切って下さい(笑)
さて、表題の件。
バチ時って、活性の有る無しがシーズン通して最も解り易いタイミングだと思う。
というのは、私のホームは水深が結構あるせいか人通りが多いせいか、秋にライズするポイントって本当に限られている。
明け方にライズしてる事は結構あるんだけど、朝弱いのよ…(泣)
レンジ入れる釣りの場合でも入れ食いになる事が多々あるが、それは「活性」によるものか「上手く嵌った」だけなのか定かじゃない。
その点、バチシーズンは視覚・聴覚で活性が確認出来るので、誰でもが判断し易いと思う。
で、このバチ活性って、活性が高い/低いに2つのパターンがある。
一つは、辺り一面で餌に狂ってライズしてる状態。berserkと言いますか。簡単に言えば「集団活性」。
ベイトと一緒で、「適当に突っ込んでりゃ餌口に入るだろ」位の状況で水面を割っているシーンを思い起してくれれば。
(勿論、魚はちゃんと狙ってるんだろうけど)
これは全面トリッキーになった時に起こり易い現象。
「こんなに魚居るのかよ…」と己の無力さを感じる瞬間でもある(爆)
もう一つは、言うなれば「個体活性」。
一番判り易いのが、ライズ音。
同じ捕食でも派手に出てるのは活性が高いし、小さなライズリングのみの時は低い。
「サイズの違いじゃね?」というのは全くの見当違いで、サイズ差の場合は音質が変わります。
派手と地味でも音質は違いますが、その辺りを口で説明するのは非常に困難で…
以前「カクテルパーティー効果」という話をした事がありますが、それの延長で、慣れてくるとその違いがはっきりと判ると思います。
「これは(ルアーを)食ってくるライズ音」「これは微妙(だけど投げる)」「狙うだけ無駄(でも投げる(爆))」みたいに。
それだけでも、ヒット率がぐっと上昇します。
で、本題。
その場の状況判断が出来たとしても、ただ闇雲にルアーを投げていても非効率極まりない。
あ、くれぐれも言っておきますが、私、バチでシンペンの釣りは一切やりません。
なので、シンペンだと闇雲に投げた方が効率が良いかも知れませんので、それはご自身で判断して下さい。
そこで行うのが「曳波の使い分け」。
以前「寄せの曳波」と「食わせの曳波」という話は書きました。
そのコンセプトは変わってませんが、ルアーが変わった為、更に細分化されてしまっているという(爆)
で、あの時は二次元での話で終わりましたが、今回は三次元での話になります。
簡単に図解すると、こんな感じ。イメージwは伝わるかと。
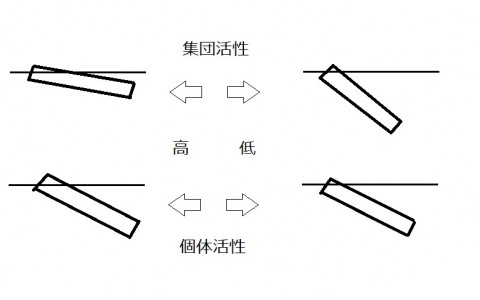
何が言いたいかというと、高活性時にはルアーを浮かせ、低活性時には若干沈める。
が、沈め方が異なって、集団活性が高い時にはリアを軽くし、個体活性時が高い時は全体を軽くする。
因みに、調整幅は0.02g毎+現地チェック。
私がバチに使うのは#10~#6のトリプルフックなのだが、メーカー/針種の違いで大体0.02g違いで揃えられる。
これに、#0~#3のリングを組み合わせて使うと、大概の調整は可能となる。
で、これをその時の状況に応じて使い分けるって訳。
当然高/低2種ではなく、その中間だって幾つか存在する。それに色違いとかやってると…
こんなんやってっから、他のルアーが使えなくなるんだよっっ(爆)
多分上の図を見て、気付いた方は多いと思うので先に書いておきます。
頭が出てるのだから、水を受ければ必然的にリアが浮くか、ヘッド形状によっては潜るよね?と。
だから巻きスピード=リズム感が必要なのです
これは以前から公言してますが、私が人より少しだけ優れてると思われるのは、キャスト精度と音感。
任意で一定のスピードで巻く事が出来れば、後は風の影響だけ考えて調整すれば良い。
それでも調整出来ない場合の為に、細かく調整を施した多くの同種ルアーを持ち込む訳です。
これが、ここ数年廃盤トップ1と2しか使ってない理由です。
で、この様なチューニングをする根拠を少し。
個体活性の場合、当初は「上まで出てこないんだから、針位置を下げれば掛かるんじゃね?」という助平心(笑)
で、2~3㎜レンジを下げてみたら、結構釣れるようになる。(これがトップのレンジはミリ単位と言ってる根拠)
それなら、と、針位置だけを下げてみると、面白い事に全然反応が悪い。
って事で、方向性は判ったが、それが微細な曳波による物か、水面下の存在感による物かは不明(←今後の検証材料w)
もしかすると、レンジを下げる→水受け面積が大きくなる→ルアーが動く→ボディの波動?www
集団活性の場合、ほぼほぼ全面トリッキーの時に起こる事から、当初は「トリッキーっぽくケツ振れば良いんじゃね?」という、これまた助平心(笑)
シンペンならば基本ケツ振りなので、何も考えないで良い。
が、その頃から「絶対に沈めねぇ」を信条としていた事もあり、「ならリアを軽くすればケツ振るんじゃね?」と。
そこから調整を入れ始めたら、面白い現象が。
水面上の表面積は上がっているのに、「細い曳波」が立つようになった。
これはヘッド形状からくる恩恵かと思うが、それによりトリッキー独特の細かい波紋に近い曳波が出る様に。
狙い通りリアも僅かだが振れてくれ(これまた波動?www) 、全面ライズ時に最も釣れるチューニングに。
そして、現在に至ります。
勿論上記の物は廃盤トップ1・2のヘッド形状・比重・サイズから出た結果であり、他のルアーでどうなるかは全く判りません。
「他のルアーでもやれよ」と言われるかも知れませんが、まだこのルアーで検証しなければならない事が多々あり、そんな余裕はありません。
ただ、例え一つのルアーだとしても明らかな結果が出ている訳で、それが他にも応用出来れば…という意図で書いてみました。
参考になれば幸いです♪
- 2020年6月1日
- コメント(9)
コメントを見る
rattleheadさんのあわせて読みたい関連釣りログ
fimoニュース
| 14:00 | 解禁を迎えたサクラマス初挑戦 |
|---|
| 08:00 | ハゼパターンにディモル70必須ですね |
|---|
登録ライター
- ヨーヅリ:トビマルJr.(フレ…
- 2 日前
- ichi-goさん
- 『あと1センチ・・・』 2026/2…
- 6 日前
- hikaruさん
- フィッシングショー大阪2026行…
- 10 日前
- ねこヒゲさん
- 新年初買
- 27 日前
- rattleheadさん
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 1 ヶ月前
- 濵田就也さん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪
- ハマケン
-
- 流れの釣り
- Kazuma























最新のコメント