プロフィール

みやけ
東京都
プロフィール詳細
検索
タグ
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:3
- 昨日のアクセス:181
- 総アクセス数:1233960
QRコード
▼ Solid Chaser ~華麗なる名脇役達~ 番外編
- ジャンル:日記/一般
- (華麗なる名脇役達)
連日大雪のニュースが続く日本列島ですが、東京でも日によっては、最高気温が5℃を切るような厳しい寒さが続いています。
南国出身ということもあり、暑さには滅法強いのですが、何年経っても東京の冬はダメですね。
さて、そんな厳しい冬の時期なのですが、季節は確実に進んでおり、先日家の前の自販機にて水を買った際にちょっくら隅田川を見てくると

※写真は2011年度のものです
まさにバチソーメン状態
そうか。この日は後中潮2日目。
最もバチの抜ける日にちでした。
春の一大イベント、バチ抜け。
さて、今回は、このバチ抜けの釣りにて活躍?するはず、使いこなせば心強い味方になってくれるであろう、あるタックルを紹介したいと思います。
~番外編 その1 Exsence S803L/F-s Solid Chaser

私の中でのメインとなるロッド選びの基準としては「1オンス程度のルアーを強いキャストで振りぬき、キッチリ操作が出来るか」ということを一つの指標としています。
シーズン中は基本的に荒川を中心に回る自分なのですが、スタイル的に潮位や各条件を掛け算しながら美味しい場所を自転車でランガンで叩いていく、ということを行っております。普段のログでは書きづらいのですが、おおよそ2時間を1セットとして、季節のベイトを大前提としながら各セットごとに潮位によってポイントを変え釣りを組み立てているのです。
結果的に、2時間ごとのタームの中で50㎝のシャローから水深10mを超えるディープへ移動する。そういった組み立てに対応できるためにも、条件が変わった場合でもある程度対応できるよう、7㎝のミノーから30gのブレードまで扱えるように「大は小を兼ねる」という考えの元ロッドを選んでいる前提があります。
蛇足になりますが、この LABRAX 86ML はその典型。

8、6Fという操作性と遠投性のバランスの取れたレングスに、MAXウエイト35gとほとんどのルアーに対応できる強さを持ち合わせており、5年前に購入して以来、今でも愛用している1本です。
さて、話を戻しますが、バチ抜けの釣りについて。
ご存じの通り、シーバスの捕食の仕方の問題で、非常にショートバイトの発生しやすい釣りであることが特徴で、そのためにティップの柔らかいロッドを選択することが、対処法の一つであることは今さら語ることはないでしょう。
ただ、実際のところは、殆どのケースでこのLABRAX 86ML にて対応出来てしまうのも事実です。鶴見川・多摩川・そして荒川というフィールド。ここらでの釣りは、勿論ショートバイトで乗らない魚に泣いたことも多々ありますが、これはLABRAX 86MLのせいではないのです。
要は、こういったシャローにおけるバチの釣りは、流れの中にて遠くで掛けることが前提になっていますので、バイトの起こる距離が遠い分ラインのたるみがクッションとなるため、ロッドのティップの硬さがそれほど問題にはなりません。逆に言えば、強い流れの中でルアーを流した場合には、ティップの柔らかい竿だと柔らかさの分だけ吸い込まれてしまい、結局のところその柔らかさは生かせないのです。
上記内容を逆から読めば、自ずと分かると思うのですが、ティップが硬めの竿が不利になる場面とはどのような場所でしょうか?
大きくは二つで、
◆至近距離(ピックアップ)でのバイトが出やすい三面護岸の地形
◆流れの緩い場所
言い換えれば、このような地形こそが、ソフトティップのロッドの特性が活きやすい条件といえますので、その事を前提条件としてお考え頂ければと思います。
さて、ここからは具体的なスペックについて述べていきます。
Solid Chaserはその名前の通り、先端の20cm程にソリッドの構造となっており、極端に先の柔らかい調子に仕上げられています。

写真で見てみると、先端部白い所が、いかに柔らかいかよく分かるかと思います。

バチに固執している魚の特徴としては小魚を食べて切るときほど大きく口を開けず吸い込みが弱くなる傾向があり、また全体のサイズも中~小型が増えるため、ハリの掛かりが浅くなったり、掛かりにくい傾向があります。
この極端に柔らかいティップのお陰で、先に述べた、ラインの弛みのクッションが作れない状況の場合でも、ティップが入ってやることでフッキングの確率を上げてやることが出来るのです。
また、ティップが極端に柔らかいことの別なメリットとしては、手で感じられないルアーの動きを目で見て感じることが出来る、ということです。例えば、ワンダー60のような超小型のシンペンをアップに投げて流した場合に、ルアーの泳ぎをリーリングで感じとるのは至難の技でしょう。しかし、ティップの入りを見ながら巻いてやることでルアーが最低限水を受けているか感じることができます。言い方を変えるなら、ティップの入り具合にて釣れるリトリーブが出来ているかを判別することが出来るのです。
それと、忘れてはいけないのが、ソリッドティップのロッドならではのテクニック、ワームやシンペンといった引き抵抗の弱いルアーでの八の字メソッドがあります。八の字メソッドは、足元で食い渋る魚を急激な軌道の変化にてリアクション的に食わせてしまう方法ですが、ソリッドティップのロッドにて八の字を書くことでティップがしなやかにルアーの動きに追従することにより、ワーム等引き抵抗の弱いルアーでも水から飛び出さず泳がせることが可能で、また足元で食った際にもショックを吸収し乗せ切ることが可能になります。これがチューブラーのロッドだとティップの反発の強さから、水の中にロッドを入れないとルアー水から飛び出してしまったり、魚が食っても乗せ切れないという事態が多発します。
なお、このテクニックを使う際には、レバーブレーキ付きのリールを使うことで、足元で食った魚と一旦距離を取ることが出来ますので、おススメです。
さてさて…
そんな超ソフトなソリッドティップのロッドですが、逆に欠点としては
『感度の悪さ』、『操作性の低さ』という2点が挙げられます。
Solid Chaserの最も見逃せないポイントは、それを可能な限り低減している点にあります。
通常、ソリッドティップのロッドに関しては素材としてはグラスを使用しています。これは使えば直ぐに分かることですが、グラスソリッドの場合その弾性の低さこそか乗り易さの秘密なのですか、ショックを吸収し過ぎる傾向があり、結果として感度の悪い竿となってしまうのが特徴でした。
一方で、Solid Chaserに関してはタフテックソリッドというカーボン繊維を編み合わせた素材を使用しており、高い震動伝達性能を保っています。よってグラスソリッドにありがちな「気がついたら魚が乗っていた」、ということではなく『ティップが曲がり混む瞬間を目で見つつ、手元にアタリを感じつつ、合わせを入れる』ことが可能です。
また、ソリッドセクションを若干短めにしている点も、その感度の良さの要因ではないかと思います。震動伝達性能という意味では、殆ど通常のチューブラーティップのロッドと同じ感覚ではないでしょうか。
また、ティップの部分は極端に柔らかいもののベリー以下は非常にしっかりとしたブランクスを使用しています。
カーボンをクロス状に巻いたハイパワーX、スパイラルXという構造によって、強い反発力とハリを実現した超高弾性のブランクス特性を持っており、パワーや飛距離は勿論のこと、高いキャストアキュラシー性も実現しています。

ざっと特徴を記載してみましたが、チューブラー構造のロッドと限りなく同じ感覚にて使用できるように、設計されている点が大きなメリットです。
ただ、やはり基本は超柔らかいソリッドティップを装着していることには変わりないので、引き抵抗の強いルアーを使用した場合はティップが入り込んでしまい、竿本来の有効なレングスを生かすことが出来なくなってしまいます。
そういう意味では、やはり引き抵抗の弱いルアーを近距離で食わせることに特化したロッドであることには間違いなく、汎用性を捨てることで、特殊な条件で威力を発揮するアイテムであることに変わりないでしょう。
なので、1本で様々な条件に立ち向かっていくのであれば、チューブラーティップのロッドの方が遥かにメリットも大きいのです。そもそも、ソリッドティップのロッドだからといって乗らないバイトも多々ありますので。
まぁ、道具マニアや、お金が余って仕方ない(笑) って方なら止めませんが、ちょっと気になるから買ってみる、というには価格的にも安いものではありませんし、ロッドとしての汎用性はありません。実際、中古屋には良くソリッドティップのロッドも置かれていますが、使いこなせない(もしくは肌に合わない)ので手放す人も多いのではないでしょうか。
でも、逆を言うならば、シーバスをある程度やり込み、各条件によってどういった釣りになるか大筋で正確に予測が出来るようになり、
釣行前からあらかじめ、どの条件?どういう場所で?どのルアーを使って?どう食わせる?のシュミレーションが出来る人には心強い武器となってくれるアイテムです。
さて、湾奥のバチ抜けの最盛期はあと2か月半ほど…
今年の春、貴方は、どう戦いますか?笑
南国出身ということもあり、暑さには滅法強いのですが、何年経っても東京の冬はダメですね。
さて、そんな厳しい冬の時期なのですが、季節は確実に進んでおり、先日家の前の自販機にて水を買った際にちょっくら隅田川を見てくると

※写真は2011年度のものです
まさにバチソーメン状態
そうか。この日は後中潮2日目。
最もバチの抜ける日にちでした。
春の一大イベント、バチ抜け。
さて、今回は、このバチ抜けの釣りにて活躍?するはず、使いこなせば心強い味方になってくれるであろう、あるタックルを紹介したいと思います。
~番外編 その1 Exsence S803L/F-s Solid Chaser

私の中でのメインとなるロッド選びの基準としては「1オンス程度のルアーを強いキャストで振りぬき、キッチリ操作が出来るか」ということを一つの指標としています。
シーズン中は基本的に荒川を中心に回る自分なのですが、スタイル的に潮位や各条件を掛け算しながら美味しい場所を自転車でランガンで叩いていく、ということを行っております。普段のログでは書きづらいのですが、おおよそ2時間を1セットとして、季節のベイトを大前提としながら各セットごとに潮位によってポイントを変え釣りを組み立てているのです。
結果的に、2時間ごとのタームの中で50㎝のシャローから水深10mを超えるディープへ移動する。そういった組み立てに対応できるためにも、条件が変わった場合でもある程度対応できるよう、7㎝のミノーから30gのブレードまで扱えるように「大は小を兼ねる」という考えの元ロッドを選んでいる前提があります。
蛇足になりますが、この LABRAX 86ML はその典型。

8、6Fという操作性と遠投性のバランスの取れたレングスに、MAXウエイト35gとほとんどのルアーに対応できる強さを持ち合わせており、5年前に購入して以来、今でも愛用している1本です。
さて、話を戻しますが、バチ抜けの釣りについて。
ご存じの通り、シーバスの捕食の仕方の問題で、非常にショートバイトの発生しやすい釣りであることが特徴で、そのためにティップの柔らかいロッドを選択することが、対処法の一つであることは今さら語ることはないでしょう。
ただ、実際のところは、殆どのケースでこのLABRAX 86ML にて対応出来てしまうのも事実です。鶴見川・多摩川・そして荒川というフィールド。ここらでの釣りは、勿論ショートバイトで乗らない魚に泣いたことも多々ありますが、これはLABRAX 86MLのせいではないのです。
要は、こういったシャローにおけるバチの釣りは、流れの中にて遠くで掛けることが前提になっていますので、バイトの起こる距離が遠い分ラインのたるみがクッションとなるため、ロッドのティップの硬さがそれほど問題にはなりません。逆に言えば、強い流れの中でルアーを流した場合には、ティップの柔らかい竿だと柔らかさの分だけ吸い込まれてしまい、結局のところその柔らかさは生かせないのです。
上記内容を逆から読めば、自ずと分かると思うのですが、ティップが硬めの竿が不利になる場面とはどのような場所でしょうか?
大きくは二つで、
◆至近距離(ピックアップ)でのバイトが出やすい三面護岸の地形
◆流れの緩い場所
言い換えれば、このような地形こそが、ソフトティップのロッドの特性が活きやすい条件といえますので、その事を前提条件としてお考え頂ければと思います。
さて、ここからは具体的なスペックについて述べていきます。
Solid Chaserはその名前の通り、先端の20cm程にソリッドの構造となっており、極端に先の柔らかい調子に仕上げられています。

写真で見てみると、先端部白い所が、いかに柔らかいかよく分かるかと思います。

バチに固執している魚の特徴としては小魚を食べて切るときほど大きく口を開けず吸い込みが弱くなる傾向があり、また全体のサイズも中~小型が増えるため、ハリの掛かりが浅くなったり、掛かりにくい傾向があります。
この極端に柔らかいティップのお陰で、先に述べた、ラインの弛みのクッションが作れない状況の場合でも、ティップが入ってやることでフッキングの確率を上げてやることが出来るのです。
また、ティップが極端に柔らかいことの別なメリットとしては、手で感じられないルアーの動きを目で見て感じることが出来る、ということです。例えば、ワンダー60のような超小型のシンペンをアップに投げて流した場合に、ルアーの泳ぎをリーリングで感じとるのは至難の技でしょう。しかし、ティップの入りを見ながら巻いてやることでルアーが最低限水を受けているか感じることができます。言い方を変えるなら、ティップの入り具合にて釣れるリトリーブが出来ているかを判別することが出来るのです。
それと、忘れてはいけないのが、ソリッドティップのロッドならではのテクニック、ワームやシンペンといった引き抵抗の弱いルアーでの八の字メソッドがあります。八の字メソッドは、足元で食い渋る魚を急激な軌道の変化にてリアクション的に食わせてしまう方法ですが、ソリッドティップのロッドにて八の字を書くことでティップがしなやかにルアーの動きに追従することにより、ワーム等引き抵抗の弱いルアーでも水から飛び出さず泳がせることが可能で、また足元で食った際にもショックを吸収し乗せ切ることが可能になります。これがチューブラーのロッドだとティップの反発の強さから、水の中にロッドを入れないとルアー水から飛び出してしまったり、魚が食っても乗せ切れないという事態が多発します。
なお、このテクニックを使う際には、レバーブレーキ付きのリールを使うことで、足元で食った魚と一旦距離を取ることが出来ますので、おススメです。
さてさて…
そんな超ソフトなソリッドティップのロッドですが、逆に欠点としては
『感度の悪さ』、『操作性の低さ』という2点が挙げられます。
Solid Chaserの最も見逃せないポイントは、それを可能な限り低減している点にあります。
通常、ソリッドティップのロッドに関しては素材としてはグラスを使用しています。これは使えば直ぐに分かることですが、グラスソリッドの場合その弾性の低さこそか乗り易さの秘密なのですか、ショックを吸収し過ぎる傾向があり、結果として感度の悪い竿となってしまうのが特徴でした。
一方で、Solid Chaserに関してはタフテックソリッドというカーボン繊維を編み合わせた素材を使用しており、高い震動伝達性能を保っています。よってグラスソリッドにありがちな「気がついたら魚が乗っていた」、ということではなく『ティップが曲がり混む瞬間を目で見つつ、手元にアタリを感じつつ、合わせを入れる』ことが可能です。
また、ソリッドセクションを若干短めにしている点も、その感度の良さの要因ではないかと思います。震動伝達性能という意味では、殆ど通常のチューブラーティップのロッドと同じ感覚ではないでしょうか。
また、ティップの部分は極端に柔らかいもののベリー以下は非常にしっかりとしたブランクスを使用しています。
カーボンをクロス状に巻いたハイパワーX、スパイラルXという構造によって、強い反発力とハリを実現した超高弾性のブランクス特性を持っており、パワーや飛距離は勿論のこと、高いキャストアキュラシー性も実現しています。

ざっと特徴を記載してみましたが、チューブラー構造のロッドと限りなく同じ感覚にて使用できるように、設計されている点が大きなメリットです。
ただ、やはり基本は超柔らかいソリッドティップを装着していることには変わりないので、引き抵抗の強いルアーを使用した場合はティップが入り込んでしまい、竿本来の有効なレングスを生かすことが出来なくなってしまいます。
そういう意味では、やはり引き抵抗の弱いルアーを近距離で食わせることに特化したロッドであることには間違いなく、汎用性を捨てることで、特殊な条件で威力を発揮するアイテムであることに変わりないでしょう。
なので、1本で様々な条件に立ち向かっていくのであれば、チューブラーティップのロッドの方が遥かにメリットも大きいのです。そもそも、ソリッドティップのロッドだからといって乗らないバイトも多々ありますので。
まぁ、道具マニアや、お金が余って仕方ない(笑) って方なら止めませんが、ちょっと気になるから買ってみる、というには価格的にも安いものではありませんし、ロッドとしての汎用性はありません。実際、中古屋には良くソリッドティップのロッドも置かれていますが、使いこなせない(もしくは肌に合わない)ので手放す人も多いのではないでしょうか。
でも、逆を言うならば、シーバスをある程度やり込み、各条件によってどういった釣りになるか大筋で正確に予測が出来るようになり、
釣行前からあらかじめ、どの条件?どういう場所で?どのルアーを使って?どう食わせる?のシュミレーションが出来る人には心強い武器となってくれるアイテムです。
さて、湾奥のバチ抜けの最盛期はあと2か月半ほど…
今年の春、貴方は、どう戦いますか?笑
- 2012年2月8日
- コメント(6)
コメントを見る
みやけさんのあわせて読みたい関連釣りログ
fimoニュース
登録ライター
- フィッシングショー大阪2026行…
- 1 日前
- ねこヒゲさん
- ラッキークラフト:LV-0
- 4 日前
- ichi-goさん
- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…
- 13 日前
- hikaruさん
- 新年初買
- 19 日前
- rattleheadさん
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 21 日前
- 濵田就也さん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪
- ハマケン
-
- 流れの釣り
- Kazuma



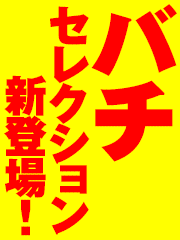
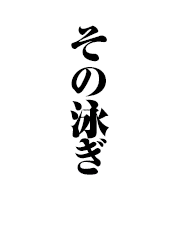
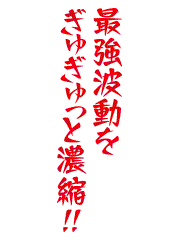

















河川の流れがある場所がメインならある程度硬いロッドでもいいもいう事が分かり安心しました。ただ、バラしまくると、どうしてもソリッドティップのロッドが気になったりしますね。バラし対策としてロッドの前にLB買ってしまいましたが、テクトロなどの至近距離バトルでなければそれほど使う必要がないという結論に辿りつきました。やはり、道具は強み、弱みを理解した上で使わないと本来のパフォーマンスはだせないですね。
おーじろう