プロフィール

工藤
その他
プロフィール詳細
カレンダー
検索
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:268
- 昨日のアクセス:323
- 総アクセス数:4768520
▼ ルアー選びのイロハ8 ミノー2
- ジャンル:日記/一般
ミノーの話しの続きです。
ミノーは小魚をイミテート(動作を真似る)するルアーなので、必然的に細身のボディーになります。
そしてアクションも小魚のようにボディーを左右に振りながら動くので、ルアーに擦れていない人が見れば「すごい、魚みたいだ」と思うはずです。
そう、人から見れば・・・です。
実はそんな泳ぎをする小魚はいませんので、あくまでも人から見てどう思うのか?が基準です。
そして釣れるアクションなんてものは、基本的に決まったものが在るわけではありません。
が、しかし、その時々で釣れるルアーの差別は発生します。
たとえば同じサイズのミノーを隣の人が投げていてバカスカと良い釣りをされたので、併せて似たようなルアーにしたけどこちらは全く・・・なんてことは普通に発生します。
では何が違ったのか。
まず、人が違うので「スピードやラインの弛み」などの「やっている事が違う」という事があります。
というか、これが殆どだったりします。
ですが、今回はルアーの話しなのでそこはちょっといておき、ルアーは似ているから同じ?ではないという事を私なりに「ルアー選びの判断基準」にしている部分を少し掘りこんで話してみます。
まず、同じサイズであるという事が前提、仮に110mmのミノーとします。
しかしAというルアーとBというルアーがあった場合に、そのルアーは何が違うかのいくつかの要素があります。
まず、一番最初に私が気にするのは体積とその配分比率です。
全体の体積とはボリュームですね。
正面から見て、体高があり、横幅もあれば、それは体積が多いという事で、ボリュームがあるルアーとなります。
ボリュームが多いとどうなるか。
まず、ルアー自体が大きく感じます。
当たり前のこと過ぎてピンときませんが、同じ長さ110mmだとしてもこのボリューム感を意識すると「アクションが強いor弱い」という違いを感じると思います。
まず、見かけの話しとして。
そして「体積が多い=より多くの空気を抱え込んでいる」と言えます。
ルアーは通常、ABS樹脂を張り合わせ、その中にウェイトだのエイトかんだのの金属パーツが入っています。
もちろん張り合わせ部は高い気密性を保つ(超音波溶着or溶剤での接着があり、メーカーによって異なる)ので、その中には空気が入っています。
通常の淡水の比重は1なのに対し、ABSは1.01~1.04とちょい重め程度。
それに対して鉛だのタングステンだのスチールだのが入ると、当然重たいので沈んでしまいますが、ABSが空気を包み込むことで浮力を持たせています。
だから見かけ上でまず体積の多さ(ボリューム)を確認します。
そしてフローティングなのか、シンキングなのか。
もしもボリュームがあるのにシンキングの場合は、それ相当の重さの金属がボディーの中に入っています。
逆にボリュームの割に重量が軽い場合もあります。
これが何に影響するかというと、アクションの強さ(今回はめんどっちいから波動と表現しますw)に影響します。
例外(この後説明するいくつかの要素による)は沢山ありますが、まずは体積に対して重量が軽い(フローティング)場合は、基本的にアクションは強めに出ます。
言葉でいうとブリブリ泳ぐ。
逆に体積に対して重たい(シンキング)場合は、アクションは逆に「遅くゆっくり小さく」という方向になります。
シーバスではあまり使わないですが、クランクベイトなんかは「軽くて浮力がある」という典型です。
ボディーに対して重くしたものは、シーバスのシンキング系ミノーのほとんどがそれにあたります。
では次のチェックするべき要素。
それは、水受けの量です。
前回も少し話をしましたが、ミノーはリップという突起が魚のあごの位置についています。
このリップとは、アイが糸に引っ張られると、最も水の抵抗を受ける部位となっています。
ルアーを正面から見て、水流に対して壁のような方向に面を持っていると思います。
さすがにこれは図を描かないとかな。
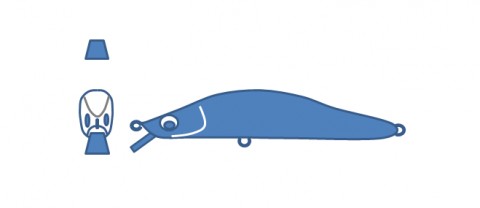 という事で、ちょっと考えてみて下さい。
という事で、ちょっと考えてみて下さい。
どうしてミノーは、巻くとアクションをするのか。
次回はロールとウォブリング
つづく
ミノーは小魚をイミテート(動作を真似る)するルアーなので、必然的に細身のボディーになります。
そしてアクションも小魚のようにボディーを左右に振りながら動くので、ルアーに擦れていない人が見れば「すごい、魚みたいだ」と思うはずです。
そう、人から見れば・・・です。
実はそんな泳ぎをする小魚はいませんので、あくまでも人から見てどう思うのか?が基準です。
そして釣れるアクションなんてものは、基本的に決まったものが在るわけではありません。
が、しかし、その時々で釣れるルアーの差別は発生します。
たとえば同じサイズのミノーを隣の人が投げていてバカスカと良い釣りをされたので、併せて似たようなルアーにしたけどこちらは全く・・・なんてことは普通に発生します。
では何が違ったのか。
まず、人が違うので「スピードやラインの弛み」などの「やっている事が違う」という事があります。
というか、これが殆どだったりします。
ですが、今回はルアーの話しなのでそこはちょっといておき、ルアーは似ているから同じ?ではないという事を私なりに「ルアー選びの判断基準」にしている部分を少し掘りこんで話してみます。
まず、同じサイズであるという事が前提、仮に110mmのミノーとします。
しかしAというルアーとBというルアーがあった場合に、そのルアーは何が違うかのいくつかの要素があります。
まず、一番最初に私が気にするのは体積とその配分比率です。
全体の体積とはボリュームですね。
正面から見て、体高があり、横幅もあれば、それは体積が多いという事で、ボリュームがあるルアーとなります。
ボリュームが多いとどうなるか。
まず、ルアー自体が大きく感じます。
当たり前のこと過ぎてピンときませんが、同じ長さ110mmだとしてもこのボリューム感を意識すると「アクションが強いor弱い」という違いを感じると思います。
まず、見かけの話しとして。
そして「体積が多い=より多くの空気を抱え込んでいる」と言えます。
ルアーは通常、ABS樹脂を張り合わせ、その中にウェイトだのエイトかんだのの金属パーツが入っています。
もちろん張り合わせ部は高い気密性を保つ(超音波溶着or溶剤での接着があり、メーカーによって異なる)ので、その中には空気が入っています。
通常の淡水の比重は1なのに対し、ABSは1.01~1.04とちょい重め程度。
それに対して鉛だのタングステンだのスチールだのが入ると、当然重たいので沈んでしまいますが、ABSが空気を包み込むことで浮力を持たせています。
だから見かけ上でまず体積の多さ(ボリューム)を確認します。
そしてフローティングなのか、シンキングなのか。
もしもボリュームがあるのにシンキングの場合は、それ相当の重さの金属がボディーの中に入っています。
逆にボリュームの割に重量が軽い場合もあります。
これが何に影響するかというと、アクションの強さ(今回はめんどっちいから波動と表現しますw)に影響します。
例外(この後説明するいくつかの要素による)は沢山ありますが、まずは体積に対して重量が軽い(フローティング)場合は、基本的にアクションは強めに出ます。
言葉でいうとブリブリ泳ぐ。
逆に体積に対して重たい(シンキング)場合は、アクションは逆に「遅くゆっくり小さく」という方向になります。
シーバスではあまり使わないですが、クランクベイトなんかは「軽くて浮力がある」という典型です。
ボディーに対して重くしたものは、シーバスのシンキング系ミノーのほとんどがそれにあたります。
では次のチェックするべき要素。
それは、水受けの量です。
前回も少し話をしましたが、ミノーはリップという突起が魚のあごの位置についています。
このリップとは、アイが糸に引っ張られると、最も水の抵抗を受ける部位となっています。
ルアーを正面から見て、水流に対して壁のような方向に面を持っていると思います。
さすがにこれは図を描かないとかな。
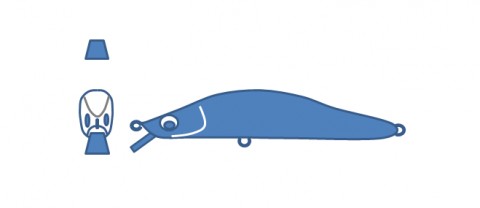 という事で、ちょっと考えてみて下さい。
という事で、ちょっと考えてみて下さい。どうしてミノーは、巻くとアクションをするのか。
次回はロールとウォブリング
つづく
- 2021年10月26日
- コメント(0)
コメントを見る
fimoニュース
登録ライター
- ムスッとしてたら
- 21 時間前
- はしおさん
- ヨーヅリ:トビマル
- 22 時間前
- ichi-goさん
- 『ワームの釣りは、向い風が吉…
- 1 日前
- hikaruさん
- 44th 早い話がイマジネーション
- 8 日前
- pleasureさん
- フィッシングショー大阪2026行…
- 20 日前
- ねこヒゲさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪
- ハマケン
-
- 流れの釣り
- Kazuma















