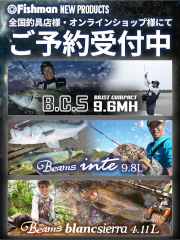プロフィール

工藤
その他
プロフィール詳細
カレンダー
検索
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:1958
- 昨日のアクセス:433
- 総アクセス数:4681632
▼ ハンドメイドルアー 手順書2
- ジャンル:日記/一般
作業手順書
【1 削りだし工程】
ルアーのもとになる形を決め、部材から削り出す
材料 バルサ3mm ボールペン 棒ヤスリ 瞬間接着剤 両面テープ ナイフ(もしくは電動糸鋸)
1 作る物を決める
大きさ・レンジ・形・アクション等、作りたいものを最初に決める。
必要に応じて紙に書きだし、出来るだけ完成イメージを明確にする。
2 バルサにアウトラインを書く
それなりに適当
3 アウトラインに沿って切り出しをする
これが、同じものをまとめて作る際のマスターとなるので、ちょっと大事。

4 マスター寸法を測り、5~10%程度の余裕をもって長方形に切り出す

ルアーのフロントアイからテールアイ方向へ木目を揃える
ナイフで切り出す場合は、垂直に刃を入れる。
今回は5個のミノーを作るので、10枚の切り出し。
(&後から違うパターンも作りたいので、合計20枚の切り出し)
のちの工程で、ばらばらになるとバルサの目が揃いにくいので、番号を振っておくと便利。
5 マスターを用いてアウトラインを引き、余剰分をカットする

ラインぎりぎりを狙えば、後工程のシェイプは楽。
削りすぎて小さくなった場合は、再利用不可となる。
どっちもどっちなので、自分の技量に見合った削りをすること。
ただし、ルアーの底面になる部分だけは、丁寧にアウトラインギリギリで切り出す事。
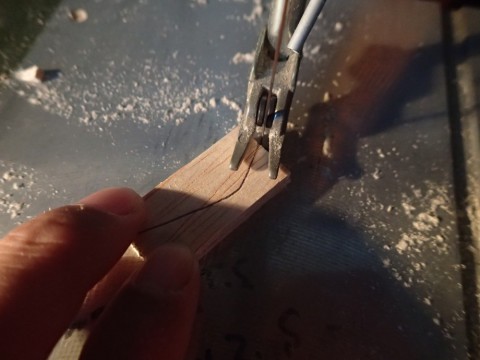
この工程はカッターでも十分できる。
また、電動糸鋸を引くと条件によりバリが出るが、後に削る部位なので気にしない。
6 10枚(マスター含み)のバルサを、両面テープで張り合わせる

切り出し時のバラつきによる最小部位が、マスターよりも小さくない(へこまない)事を確認。
テープをケチると後加工で動いてしまいやりにくい。
テープを使いすぎると、剥がすときにバルサを持っていく事がある。

どっちもどっち。
ごく少量の瞬間接着剤でも可能だが、小さいルアーには向かない。
必要に応じて、万力で挟み込むが、その際に一枚捨て板を両脇に入れて凹みを防ぐ。
なお、張り合わせ時は、次工程の「基準面を作る」を考慮し、底面合わせが基本。
7 基準面を作る
この先の削り工程は、10枚の板を均一に加工する為に、平らな机の上で固定して行う事が望ましい。
その為に、まず最初に基準面(机と接する)となるルアー底部を平らに加工(削る)する。

基準なので、とても大事な作業。
8 上部面の切削
机と板の間に異物がないことを確認し、フラットになった状態で棒ヤスリでマスターに合わせて削る。
(写真ミスってない)
ルアーに対し、出来る限り水平・直角・平行を保つこと。(10枚を均一に作る為)
9 フロントアイ部分の切削
前面を正面から確認し、合板(5個分10枚)の両端の大きさが同じになっていることを確認する。

特にフロントアイ部位の線と背中の線が平行に見える事が大事。
なってない場合は、前工程からやり直す。
問題ない場合は、フロントアイとリップの間(顎の部分)を水平に棒ヤスリで削る。
アイの頂点と、底部の線が平行になるようにする。
10 テールアイ部分の切削
フロントアイと同じく、各線を合わせるイメージで行う。
11 両面テープをはがす
この時に、工程4で番号を書いておけば、ばらばらになっても組み合わせが解る。
番号を書いていない場合は、組み合わせごとに張り合わせておく。
ココまで、ざっくり1時間。
第1工程まとめ
ここまでが最初の工程。
もしも同時複数生産をせず一個取りで作る場合は、工程4~7は要らない。
ちょっと補足。
バルサは部位によって密度にばらつきが多い(比重が違う)のはよく知られている。
その為に、できるだけ近くの部位から、右・左の面を取り出すことで、重量バランスを合わせやすくなる。
もっと精度を上げるなら、重量測定を行って組み合わせを作るのが良い。
当然、左右の重さ・体積が同じならば比重も同じになり、ルアーもまっすぐ泳ぐ。
また、この後を含めた全ての工程で(芯センター)が出ていると、流れで破綻しにくくなるので大事。
正直、形状云々言うのは、まずこれ出来てからかも・・・
この次は、内部構造と切削2
ここまでの工程で出たバルサの削り屑は捨てないで保管する事。
つづく
【1 削りだし工程】
ルアーのもとになる形を決め、部材から削り出す
材料 バルサ3mm ボールペン 棒ヤスリ 瞬間接着剤 両面テープ ナイフ(もしくは電動糸鋸)
1 作る物を決める
大きさ・レンジ・形・アクション等、作りたいものを最初に決める。
必要に応じて紙に書きだし、出来るだけ完成イメージを明確にする。
2 バルサにアウトラインを書く
それなりに適当
3 アウトラインに沿って切り出しをする
これが、同じものをまとめて作る際のマスターとなるので、ちょっと大事。

4 マスター寸法を測り、5~10%程度の余裕をもって長方形に切り出す

ルアーのフロントアイからテールアイ方向へ木目を揃える
ナイフで切り出す場合は、垂直に刃を入れる。
今回は5個のミノーを作るので、10枚の切り出し。
(&後から違うパターンも作りたいので、合計20枚の切り出し)
のちの工程で、ばらばらになるとバルサの目が揃いにくいので、番号を振っておくと便利。
5 マスターを用いてアウトラインを引き、余剰分をカットする

ラインぎりぎりを狙えば、後工程のシェイプは楽。
削りすぎて小さくなった場合は、再利用不可となる。
どっちもどっちなので、自分の技量に見合った削りをすること。
ただし、ルアーの底面になる部分だけは、丁寧にアウトラインギリギリで切り出す事。
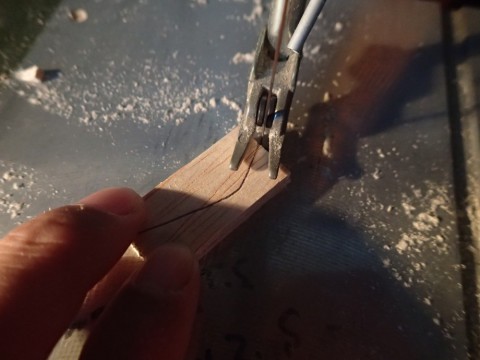
この工程はカッターでも十分できる。
また、電動糸鋸を引くと条件によりバリが出るが、後に削る部位なので気にしない。
6 10枚(マスター含み)のバルサを、両面テープで張り合わせる

切り出し時のバラつきによる最小部位が、マスターよりも小さくない(へこまない)事を確認。
テープをケチると後加工で動いてしまいやりにくい。
テープを使いすぎると、剥がすときにバルサを持っていく事がある。

どっちもどっち。
ごく少量の瞬間接着剤でも可能だが、小さいルアーには向かない。
必要に応じて、万力で挟み込むが、その際に一枚捨て板を両脇に入れて凹みを防ぐ。
なお、張り合わせ時は、次工程の「基準面を作る」を考慮し、底面合わせが基本。
7 基準面を作る
この先の削り工程は、10枚の板を均一に加工する為に、平らな机の上で固定して行う事が望ましい。
その為に、まず最初に基準面(机と接する)となるルアー底部を平らに加工(削る)する。

基準なので、とても大事な作業。
8 上部面の切削
机と板の間に異物がないことを確認し、フラットになった状態で棒ヤスリでマスターに合わせて削る。
(写真ミスってない)
ルアーに対し、出来る限り水平・直角・平行を保つこと。(10枚を均一に作る為)
9 フロントアイ部分の切削
前面を正面から確認し、合板(5個分10枚)の両端の大きさが同じになっていることを確認する。

特にフロントアイ部位の線と背中の線が平行に見える事が大事。
なってない場合は、前工程からやり直す。
問題ない場合は、フロントアイとリップの間(顎の部分)を水平に棒ヤスリで削る。
アイの頂点と、底部の線が平行になるようにする。
10 テールアイ部分の切削
フロントアイと同じく、各線を合わせるイメージで行う。
11 両面テープをはがす
この時に、工程4で番号を書いておけば、ばらばらになっても組み合わせが解る。
番号を書いていない場合は、組み合わせごとに張り合わせておく。
ココまで、ざっくり1時間。
第1工程まとめ
ここまでが最初の工程。
もしも同時複数生産をせず一個取りで作る場合は、工程4~7は要らない。
ちょっと補足。
バルサは部位によって密度にばらつきが多い(比重が違う)のはよく知られている。
その為に、できるだけ近くの部位から、右・左の面を取り出すことで、重量バランスを合わせやすくなる。
もっと精度を上げるなら、重量測定を行って組み合わせを作るのが良い。
当然、左右の重さ・体積が同じならば比重も同じになり、ルアーもまっすぐ泳ぐ。
また、この後を含めた全ての工程で(芯センター)が出ていると、流れで破綻しにくくなるので大事。
正直、形状云々言うのは、まずこれ出来てからかも・・・
この次は、内部構造と切削2
ここまでの工程で出たバルサの削り屑は捨てないで保管する事。
つづく
- 2018年2月6日
- コメント(0)
コメントを見る
fimoニュース
| 20:00 | あれ?リールの巻取り量とラインの太さ |
|---|
| 16:00 | 釣りデートは釣りではない |
|---|
登録ライター
- Summer Heat
- 23 時間前
- はしおさん
- エクストリーム:ビリンバウ1…
- 1 日前
- ichi-goさん
- 島根バケツなるものを作ってみた
- 9 日前
- papakidさん
- イワシの状況をカモメの動きで…
- 25 日前
- BlueTrainさん
- 天気予報は複数用いるべし
- 27 日前
- 濵田就也さん
本日のGoodGame
シーバス
-
- ビックベイトでリベンジ❗
- グース
-
- 狙い撃ち
- 野原 修