プロフィール

シノビー
秋田県
プロフィール詳細
カレンダー
検索
タグ
タグは未登録です。
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:105
- 昨日のアクセス:98
- 総アクセス数:695657
QRコード
▼ ミノーの話をしよう。
- ジャンル:ニュース
ルアーフィッシングで使うルアーと言えば?

と聞けば、「ミノー」と答えるだろう。
釣りをしたことない人達にルアーと言えば?と聞けば、「ミノー」を指差し、「これがルアー」だと答える方もいらっしゃるほど、ルアーフィッシングには無くてはならないものです。
そこで、私の観点から、ミノーと言うルアーの話をしてみたいと思います。
ミノーの歴史とは?
ミノーの始まりは、1800年代のイギリスのファントムミノー(Phantom Minnow)と言われていて、現在のミノーとは形こそ違いますが、小魚をイミテートしたれっきとしたミノーなのです。
ミノーの中で歴史的に有名なのは1936年にフィンランドで生まれたRapalaの創設者ラウリ・ラパラが漁師として魚を採るために生まれてきた「ラパラ」ですね。
皆さんも1度は目にしたことが有ると思います。

因みに私が、初めてシーバスを釣ったルアーも、ラパラ ラトリンラップ レッドヘッドでした。
ミノーの構造とは?
簡単なミノーの説明をしたいと思います。
ミノーは小魚に似せたボティーに、リップと呼ばれる突起をボティーに付け、そこに水の抵抗を受けさせ、受けた水が左右に逃げ出し、ロールアクションや、ウォブリングアクションを産み出すようになります。

ロールアクションと言うのは、ミノーのアイを中心に、転がるような形の動きをすることす。

ウォブリングアクションと言うのは、ミノーの尻尾と頭の半分程の位置を中心に、左右に動く事を意味しています。
当然、どっちか一方だけというものでは無く、必ずどちらも動きの中には入っており、ロールが強め、ウォブリングが強めと言う事になります。
ミノーの泳ぎはボディーで
決まる!
ミノーというのは、どうしてもリップに目が行きがちになりますが、実はボディーでかなりの所が決まります。
ざっと形を見ると、様々な形があります。
背中が盛り上がっているものと、寸胴な形のもの。
正面から見て、丸いものと、四角いもの等が有りますよね?

背中の盛り上がりは、ボディー自体の水受けの強さを見極められます。
頭部から背中にかけて、水を受けるため、体高が高いものはレンジが入りやすい事が多いです。
ボディーの丸さは、ローリングアクションに影響します。
角が無いことにより、よりロールアクションが出やすくなります。
更にボディーだけでは、ただ浮いてしまいますので、ウエイトを付けなくてはいけません。
簡単に、「固定重心」と「重心移動」があります。

重心移動するならば、その構造。
往年の「マグネット」、ボディーに段差を設けウエイトを固定するタイプ、「AR-C」、「サイレントウエイトオシレートシステム」等があります。
移動するウエイトが、ある程度、動くようであれば、ボディーバランスを崩しやすくなります。
ですから、マグネット等で固定されている、または、ある程度ミノーを動かしても音がしないものは、安定したアクションが、想像できます。
更に、ウエイトの位置も重要です。
低重心ですと、ロールアクションが出やすい位置となります。
また、頭部寄りか、尻尾寄りか。
これによっても、アクションに差が出ます。
尻尾寄りになるにしたがい、ウォブリングアクションはでにくくなります。
まだまだ、様々な要素が有りますが、「ボティー形状」「ウエイト方式」「重心位置」この3要素の組み合わせで、ボティーは決まります。
ある程度のアクションはここで決まります。
リップはボティーを
動かすエンジン!
ボティーを動かすのは、やはりリップです。
ここでは、形状、角度、位置と言ったところを説明したいと思います。
まずは、形状。

基本的に、長方形の形はローリングが出やすい形状で、扇型になるとウォブリングが強めに出ます。


長さは、長くなればなるほど、深度は深くなります。
そして、角度。

角度を立たせるとウォブリングが強めに出やすい傾向です。
寝かせるとローリングが出やすくなります。
最後は位置。


アイからの位置になりますが、離れるとウォブリングが強めに、近付くとローリングが出やすいと言う事が多いです。
泳がす前に動きを想像しよう!
ミノーは色々な要素から泳ぎが成り立っています。
私の説明も、諸説様々なものがあり、間違っていると言うメーカーの方やアングラーの方もいらっしゃると思います。
ですが、私が今まで説明してきた内容は、ルアーを作る事をビルダーさんと真剣にしてきた事で培ったものです。
そして、もっと多くの要素を含んでいる、深いルアーがミノーなのです。
シーバスルアーは、本当に多くの種類のミノーが出ました。
私がラトリンラップや、CDラパラで釣っていた時代とは大違いです。
釣れると言われる泳ぎもある程度、浸透し定着してきています。
そんな中の新商品を購入するとき、当たって砕けろで購入しても、釣ることができる時代。
もうひとつステップアップして、パッケージの中のまま、泳ぎが想像できるアングラーを目指してみてはいかがでしょうか?
釣りの幅も広がり、今まで使っていたミノーの新たな釣りが広がるかもしれませんよ?
※ミノーの構造、動きは非常に多くの説がありますし、要素が多いですので、一つの参考として御紹介しております。言っていることと違うと言ったクレームは承りませんので、御理解下さい。

インスタグラムやってます↑

と聞けば、「ミノー」と答えるだろう。
釣りをしたことない人達にルアーと言えば?と聞けば、「ミノー」を指差し、「これがルアー」だと答える方もいらっしゃるほど、ルアーフィッシングには無くてはならないものです。
そこで、私の観点から、ミノーと言うルアーの話をしてみたいと思います。
ミノーの歴史とは?
ミノーの始まりは、1800年代のイギリスのファントムミノー(Phantom Minnow)と言われていて、現在のミノーとは形こそ違いますが、小魚をイミテートしたれっきとしたミノーなのです。
ミノーの中で歴史的に有名なのは1936年にフィンランドで生まれたRapalaの創設者ラウリ・ラパラが漁師として魚を採るために生まれてきた「ラパラ」ですね。
皆さんも1度は目にしたことが有ると思います。

因みに私が、初めてシーバスを釣ったルアーも、ラパラ ラトリンラップ レッドヘッドでした。
ミノーの構造とは?
簡単なミノーの説明をしたいと思います。
ミノーは小魚に似せたボティーに、リップと呼ばれる突起をボティーに付け、そこに水の抵抗を受けさせ、受けた水が左右に逃げ出し、ロールアクションや、ウォブリングアクションを産み出すようになります。

ロールアクションと言うのは、ミノーのアイを中心に、転がるような形の動きをすることす。

ウォブリングアクションと言うのは、ミノーの尻尾と頭の半分程の位置を中心に、左右に動く事を意味しています。
当然、どっちか一方だけというものでは無く、必ずどちらも動きの中には入っており、ロールが強め、ウォブリングが強めと言う事になります。
ミノーの泳ぎはボディーで
決まる!
ミノーというのは、どうしてもリップに目が行きがちになりますが、実はボディーでかなりの所が決まります。
ざっと形を見ると、様々な形があります。
背中が盛り上がっているものと、寸胴な形のもの。
正面から見て、丸いものと、四角いもの等が有りますよね?

背中の盛り上がりは、ボディー自体の水受けの強さを見極められます。
頭部から背中にかけて、水を受けるため、体高が高いものはレンジが入りやすい事が多いです。
ボディーの丸さは、ローリングアクションに影響します。
角が無いことにより、よりロールアクションが出やすくなります。
更にボディーだけでは、ただ浮いてしまいますので、ウエイトを付けなくてはいけません。
簡単に、「固定重心」と「重心移動」があります。

重心移動するならば、その構造。
往年の「マグネット」、ボディーに段差を設けウエイトを固定するタイプ、「AR-C」、「サイレントウエイトオシレートシステム」等があります。
移動するウエイトが、ある程度、動くようであれば、ボディーバランスを崩しやすくなります。
ですから、マグネット等で固定されている、または、ある程度ミノーを動かしても音がしないものは、安定したアクションが、想像できます。
更に、ウエイトの位置も重要です。
低重心ですと、ロールアクションが出やすい位置となります。
また、頭部寄りか、尻尾寄りか。
これによっても、アクションに差が出ます。
尻尾寄りになるにしたがい、ウォブリングアクションはでにくくなります。
まだまだ、様々な要素が有りますが、「ボティー形状」「ウエイト方式」「重心位置」この3要素の組み合わせで、ボティーは決まります。
ある程度のアクションはここで決まります。
リップはボティーを
動かすエンジン!
ボティーを動かすのは、やはりリップです。
ここでは、形状、角度、位置と言ったところを説明したいと思います。
まずは、形状。

基本的に、長方形の形はローリングが出やすい形状で、扇型になるとウォブリングが強めに出ます。


長さは、長くなればなるほど、深度は深くなります。
そして、角度。

角度を立たせるとウォブリングが強めに出やすい傾向です。
寝かせるとローリングが出やすくなります。
最後は位置。


アイからの位置になりますが、離れるとウォブリングが強めに、近付くとローリングが出やすいと言う事が多いです。
泳がす前に動きを想像しよう!
ミノーは色々な要素から泳ぎが成り立っています。
私の説明も、諸説様々なものがあり、間違っていると言うメーカーの方やアングラーの方もいらっしゃると思います。
ですが、私が今まで説明してきた内容は、ルアーを作る事をビルダーさんと真剣にしてきた事で培ったものです。
そして、もっと多くの要素を含んでいる、深いルアーがミノーなのです。
シーバスルアーは、本当に多くの種類のミノーが出ました。
私がラトリンラップや、CDラパラで釣っていた時代とは大違いです。
釣れると言われる泳ぎもある程度、浸透し定着してきています。
そんな中の新商品を購入するとき、当たって砕けろで購入しても、釣ることができる時代。
もうひとつステップアップして、パッケージの中のまま、泳ぎが想像できるアングラーを目指してみてはいかがでしょうか?
釣りの幅も広がり、今まで使っていたミノーの新たな釣りが広がるかもしれませんよ?
※ミノーの構造、動きは非常に多くの説がありますし、要素が多いですので、一つの参考として御紹介しております。言っていることと違うと言ったクレームは承りませんので、御理解下さい。

インスタグラムやってます↑
- 2019年11月27日
- コメント(0)
コメントを見る
fimoニュース
| 14:00 | 解禁を迎えたサクラマス初挑戦 |
|---|
| 08:00 | ハゼパターンにディモル70必須ですね |
|---|
登録ライター
- ヨーヅリ:トビマルJr.(フレ…
- 2 日前
- ichi-goさん
- 『あと1センチ・・・』 2026/2…
- 6 日前
- hikaruさん
- フィッシングショー大阪2026行…
- 10 日前
- ねこヒゲさん
- 新年初買
- 27 日前
- rattleheadさん
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 30 日前
- 濵田就也さん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪
- ハマケン
-
- 流れの釣り
- Kazuma


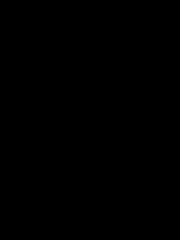














最新のコメント