プロフィール

カリアゲ
埼玉県
プロフィール詳細
カレンダー
検索
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:26
- 昨日のアクセス:47
- 総アクセス数:232390
QRコード
▼ 実証 ザリガニパターン 〜衝撃の実釣編〜
- ジャンル:釣行記
- (シーバス)
鱸はザリガニを捕食するのか?
前回ログで鱸が河川に遡上し、そこで淡水に棲む餌を捕食という話はしました
http://www.fimosw.com/u/kariage/yunrsdw922xn2e
今回は小河川農業排水における鱸のザリガニ捕食行動の検証をしたいと思います
検証場所は、直接東京湾に流入する一級河川の支流の支流、
の、さらに支流
河川課が定める河川の種別によると準用河川に分類されています
この川の水源は利根川です、
利根川の分流より利水され、農業用水として用水路を通り、使い切れなかった水が通る排水路になります、

両サイドをシートパイルで護岸された2面護岸水路で、

場所によりH鋼が渡り、一見すると生活排水路のように見えます

しかし生活排水の流入はほとんどなく、
かわりに田んぼで使った水が各所から排水溝や塩ビパイプにより、この川に排水されています

この川で鱸が釣れはじめるのは例年5月のGW頃からですがピークを迎えるのは6月に入ってから
この川のすぐ下流の一級河川との合流点で鱸が釣れはじめるのが3月の初旬ということは、
田植えの時期に餌を求め、この農業排水路に入り込んできているのではないかと予想されます

田んぼ脇の溝にはザリガニがたくさんいました

田んぼからの排水が落ちるポイントで鱸を狙ってみたいと思います、
普段はこのインレットにルアーを通し釣果をあげていますが、
使用しているのは7〜9cmの小魚型
釣れる魚のポジショニングにより排水から落ちる餌を捕食しているのは間違いないと思われますが
これでは、ルアーを魚と捉えているのか、
エビやドジョウと思い捕食しているのかもしれません、
釣れた鱸の腹を割り胃の内容物を確認するのが
最も間違いのない方法ですが、食べない鱸をキープするわけにもいきません
ストマックポンプで胃の内容物を確かめるという方法もありますが、
もっと簡単な方法があります、
ザリガニを餌にして、餌釣りをすれば良いのです
これで釣れれば鱸はザリガニを食べている
ただし、一つ条件があります
排水の落水地点にダイレクトにザリガニを落とすのは禁止です、
なぜなら、それで釣れてしまった場合、
鱸が排水から落ちてくるもの全てを口に入れるという反射行動の可能性があります、
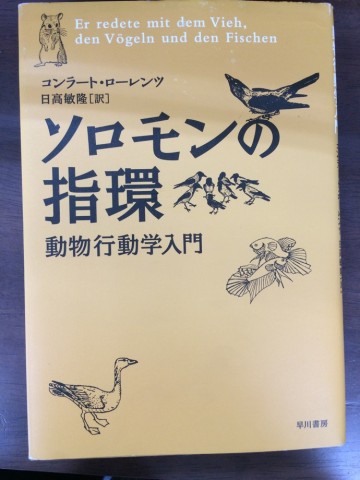
ノーベル賞学者、コンラート・ローレンツの著書
ソロモンの指輪の中に魚の血という章があります
この中でのトウギョとはベタ、
宝石魚として扱われているカワスズメダイとはイトヨなどのトゲウオ科の魚の事でしょう
この魚の捕食行動について書かれている部分で
マウスブルーダーの南米産宝石魚が口の中に子供が居るにもかかわらず落下してきた餌を捕食してしまうという事例が描写されています、
私も以前飼育していたインカ50と呼ばれるアピストグラマに何とか水槽内で増殖してしまう貝を食べさせようとして、ペレット状の餌と交互に与えてみたことがあります、
最初のうちは一度口には含むものの数秒で吐き出していました、
しかし、ピンセットで貝を拾い、軽く潰し貝の身を露出させて与えたところ、貝を食べるようになりました、
落下物を捕食対象としていたが貝は異物であった
しかし貝の味を覚えたアピストはその後普通に貝も捕食するようになったということでしょう
以上の事から田んぼの排水の落水地点に餌を落とせば、とりあえず口に入れてしまうという反射行動によるものである可能性があるので
落水地点から少し離して着水させスイミングさせるとこにします
準備したものは

餌となるザリガニ、中型を選びました
針付けしづらそうなのでマッカチンと呼ばれる大型は避けました

一つテンヤ
マルキューのオーバルテンヤを使用します
スイミングで使いたいので最軽量の2.2号を使用
タックルはいつも小河川用に使用しているもの
抜き上げ前提なのでPE1.5号に30lbを接続

尾羽根をカットし針先を腹側に抜きます
マゴ針は頭の先にチョン掛け
予定通り、田んぼからの排水近くにアンダーキャストします、
着水の衝撃で餌のザリガニがズレない様に注意しました、
1投目からアタリがありましたがニゴイでした

これも想定内です、
コイ科の魚の中でも特に動物性の餌が好きなニゴイが同じところにいるのは当たり前です

次の排水でもニゴイでした
このままニゴイ天国で餌のザリガニが無くなるかと思った3カ所目の排水で

本命がきました!
ニゴイが連発したのでレンジを水面付近に変えたのが良かったのかもしれません、

その後もう1本追加し、採取したザリガニが無くなったので、この日の検証は終了
一つテンヤを用いた水面付近のスイミングで鱸が釣れたということは、
間違いなく鱸はザリガニを捕食対象としていることで間違いありません、
これで小河川の農業排水口で釣った魚をザリガニパターンで釣ったと言って良いと思います
そして、私の持論としてパターンとは再現性があって然るべき、と思っています
1回の釣行で釣れたからと言ってパターンと名付けるには早計
今まで色々なパターンをともに開拓してきた盟友であり幼なじみのソル友、カリアゲ研究所の名誉職員C-25君を誘い、
次の日も検証実験をしました

やはり同じポイント、同じ釣り方で釣れました

驚いたのはこの日のサイズ
70クラスが連発しました
過去にこの水路でのレコードは60ちょっとが数本で、このサイズは釣った事がありません
水深は僅か40〜50cmなので大型は入ってこないと勝手に推測していましたが
これは驚愕でした、
今までルアーでは食わせられなかったサイズの魚でもザリガニでなら食わせられるという事かもしれません、
今後のルアー選択アクション等、考えが必要になりますが、
今回非常に有意義な検証ができたのではないでしょうか
次はカエルパターンの検証したいとおもいます
鱸のポカン釣り
カエル触れないけど(笑)
- 2015年6月4日
- コメント(10)
コメントを見る
カリアゲさんのあわせて読みたい関連釣りログ
fimoニュース
| 00:00 | [再]冬なのに秋の様なミノーでボコボコだった釣行 |
|---|
| 1月22日 | 大晦日大決戦2025 ベタ凪のタチウオジギング |
|---|
| 1月22日 | 26年初モノはまさかまさかな… |
|---|
| 1月22日 | 遊び心は別格 酒豪らしいネーミングのルアー |
|---|
登録ライター
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 3 日前
- 濵田就也さん
- Requiescat in pace
- 3 日前
- rattleheadさん
- メガバス:ドッグXJr.COAYU
- 5 日前
- ichi-goさん
- 野生の本能を刺激する
- 9 日前
- はしおさん
- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…
- 17 日前
- hikaruさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!
- ハマケン
-
- 最近の釣果に感謝
- Kazuma





















最新のコメント