プロフィール

古賀 亮介‐snif
福岡県
プロフィール詳細
カレンダー
検索
タグ
アーカイブ
▼ フィネスジギングな夜~インクス研修番外編①
- ジャンル:釣行記
- (ログ)
瀬戸内での初日から二日目のお話。
そもそもこの旅は、コレがスタートだった。
加来さんが冬に呼子に来られた折、フィネスジギングがイマイチ機能しない呼子のマイポイントで、じゃぁ、本式の瀬戸内式ってのは一体どんなトコでやってるのかと、しつこく聞いてみたのがそもそもこのツアーのキッカケ。
水深があって、流れがあって、底餌があって。
そのファクターだけじゃいまひとつ、ちょっと何かが足りてないような気がしていて、
これは行ってみないと分からないよね。じゃぁ、おいでよ。っていうやりとりだったかと思う。
連れて行っていただいたのは、瀬戸内のどこにでもあるような、灯り付きの堤防だった。
まずポイントの分析。
・オレンジの灯が外洋に効いている、
・明確な潮流の変化が足元からしっかりある。
・港内はそこそこ深いけど、そんなに大規模でもない。
船溜まりがあって、港内にも灯りはそこそこある。
・ベイトのストック量、回遊量は『釣れる漁港』のそれだった。
・水深は、僕の認識の中の一般的なもので、足元の敷石が満潮時に5mあるなし、そこから落ちて付け根が10~20m。港内向きはそのままミオ筋と繋がっていて、外洋向きは払い出す潮によって削られているような印象。
外洋向きでも堤防根元側は根元による程、ブレイクが沖目に寄って行く地形になってた。
地形だけ見ていくと、呼子にもいっぱいあるよねって程度。
ここ最近、闇場でアジを釣ってる場所、結構それに当てはまるんだけど、灯りってのがまた一つキーなんだろう。
やはり灯りの有無ってのが、その瀬戸内のピンと呼子の違いで、
底餌の溜まる外洋向きのストック場を見ていくのが今後の方針。
灯りの無いとこでも多少効くんだろうけど、灯り着いてるとこ…探すしかねぇな。と。
一通り、現場の地形と潮を見てみると、堤防先端からまっすぐ沖目に三角形の潮目が出ている。
出る潮入る潮、周回潮流。それらでバランスの良い流れのタイミングでキレイな三角形。
やはりこうだよね。京泊と同じやね。
手に取るように自然と釣りが見えてくる。
タックルは流れの強さ、地形も見ながら現場合わせ。
底餌も潮によって位置が変わるだろうから、それをイメージして、潮ヨレの壁、壁の延長線上にあるブレイクラインにメバルの群は着くだろう。
流速が変われば浮いてくる個体も居て、そいつらは潮の壁に沿ってホバリングして浮上してくる。(はず)
加来さんに色々とアドバイス貰いながら、レンジとフォール姿勢を気にしながら、重さとラインの太さを流速に合わせてジグをリフト&フォール。
初日は潮も良く流れて、ストロークの長いフォールにガッツンガツン当ってくれた。
上げ潮の止まる直前、潮目の奥、ボトムまで一貫してフリーなスピニングスローでのマダイを皮切りに、

その前後には良いサイズの白メバルがポンポンと。

軽いラッシュも堪能。

この体高。
ディープのシロメバル、しっかりイカナゴに付いてるのもあって、
非常に良く引いてくれました。

ハイシーズンに少し遅れて釣ってるのもあってか、
少しのピン、立ち位置と流す角度の違いによっては、クロメバルも混じる。

加来さんの掛ける魚に結構クロが混じってたのを見ると、
ディープのオープンエリアにありながら、
コンディションの良いシロに狙いを絞ると、
打つべきピンはそう広くない様子。
群自体が潮で流れる餌に付いているので、スイッチの入る個体はその流れの一番良いトコに陣取ってるやつ。
彼ら自身が小規模な群で刻々と移動して定位ピンを変えるのか、
はたまた喰わないだけで、群自体は大きく潮向きの良い位置にいるヤツにだけスイッチが入っていたのかは、2日間では掴みきれなかった。
シーズン終盤である事を鑑みれば前者であるが、そこは想像の域を出ない。
それはともかく、どうもジグの動きの質で、
食う食わないってのも確かに出てきているようだった。
初日、やや活性の高い瞬間は、シーライドミニの得意とする、
スライド系の、割と動きの幅の大きめのアクションが効いているようだった。
イカナゴが追われてボトムや表層に向かって、3次元的にエスケープしている様子をイメージして演出した、長めの距離をバックスライドするような動きを入れた直後にバイトが集中した。
大幅なリフトから、ロッドストロークをしっかりと活かしての、
ほぼゼロテンションのロングフォール。
使ったジグはシーライドミニの9gとバイスライダーの10gだった。
より潮に噛ませたい時にシーライドミニ、潮を切って入れていきたい時にバイスライダーのリアウエイトセッティングっていう風な使い分け。
軽めでは潮の速い時間は釣りにならなかったのと、
例えそれを頑張ってレンジに入れてボトム潮流に乗せ、
小刻みに動かしながらヘコヘコとスローに漂わせながらドリフトを掛けていても、
アタリは少なく、ピンを外れたところで、狙いと違うコンディション、サイズの群が反応するばかりであったのだ。
潮がタルくなって、あまり流れない時間にボトムワインドを掛けると連発もした。
フォローベイトはやはりこれだろう。
(このワインドの釣りも、動画として残ってるのでDVDに入るはず)
ちなみに、急流の時のワインドは釣れなくないけど微妙で、圧倒的にジグに反応が良かった。
それに対して二日目は、状況が一転。
まとまった雨による、強めの水潮と、潮流も前日とは違い、とても緩かった。
他にも何か要素がありそうだったけど、魚の活性が極端に落ちていた。
この日、状況を見ながらワインドで始めた加来さんには良い魚が連発する。
その裏パターンに徹していた僕には、前半はアタリもほとんどなかった。
撮影中もジグにはミスバイトばかり。
潮が流れない中、シーライドミニのウエイトを3gまで落として、着底後、ワンピッチだけリフトした後は、テンションを入れてゆっくり流してみた。
それで最初の1匹目が出て、次のキャスト辺りで徐々に潮が流れ始める。
この日、キーとなる潮が動き出してから、釣りが続行不可能になる暴風に達するまでの小一時間。その終盤に見つけた魚は、ボトムから50cm程度のレンジを出来るだけキープしてドリフトを掛ける釣りが連れてきてくれたものだった。

ベイトタックルでより、レンジを細かくスローに刻むイメージで操作してたけど、
後から考えると、スピードを落としてもっと中層からその上までも、じっくり流してやれば、少し違った答えが出たのかもしれない。そんな時間はなかったけど(^^;
いよいよ暴風が吹く荒れ始め、それと同時に入ってきたアジの群。

それまでその位置、レンジには全く気配を感じなかったから、
吹き荒れだした風で押されたベイトを追って入ってきた群。
ポロポロと、非常にイージーだったから、コレはコレで楽しかった。
瀬戸内の変わりやすい潮流も考慮すると、この日の道具立ては4本になった。
リーダーの太さは細かいレンジを釣り分けようと試行錯誤。
マダイが出る事を考えれば、2号に固定しときたい感じでしたけどね。
スタンダードな流速1
rod GRF-85PEスペシャル
reel アブREVO-MGX2500
line PE0.5号+フロロ1.75~2.0号
スタンダードな流速2
rod プロトベイト65
reel アブREVO-LT
line PE0.4号+フロロ1.5~2.0号
潮がタルくてスローな時間用1
rod ウエダpro4ex 4S610SL/プロト60UL
reel ダイワ2004
line PE0.3号+フロロ1.5号
潮がタルくてスローな時間用2
rod ウエダpro4ex TFL-64EX-R
reel アブREVO-MGX2000
line フロロ0.6号直結
リグはメインがメタルジグ。
ボトムワインドも相当効くのは、状況的に間違いなくて、
フォローベイトとして常にスタンバイ。
潮流に合わせて魚の活性が変動していく事が多いはずなので、
それを目安に使い分けていくのが良いだろう。
使用したメタルは4種類。

右からシーライドミニ、爆釣ジグ、バイスライダーの3種に、
上はご当地メタルジグ、ブリスのメバジーも使用。
このメバジー、去年までは福岡唐津界隈でも買えたんだけど、
最近めっきり見なくなった。
この釣りには、どうしてもフロントバランスの並行姿勢で
ドリフトが決められるジグが選択肢の一つとして欲しくなる。
シーライドミニのテンション掛け気味バックスライドが割と近い仕事をするんで代用も出来なくはないんだけど、
潮流の強めのディープでレンジキープしながらのドリフトを、
より高次元にやっていくには、この4種類がどれも必要なんだなぁ。
補充しとこ。
そもそもこの旅は、コレがスタートだった。
加来さんが冬に呼子に来られた折、フィネスジギングがイマイチ機能しない呼子のマイポイントで、じゃぁ、本式の瀬戸内式ってのは一体どんなトコでやってるのかと、しつこく聞いてみたのがそもそもこのツアーのキッカケ。
水深があって、流れがあって、底餌があって。
そのファクターだけじゃいまひとつ、ちょっと何かが足りてないような気がしていて、
これは行ってみないと分からないよね。じゃぁ、おいでよ。っていうやりとりだったかと思う。
連れて行っていただいたのは、瀬戸内のどこにでもあるような、灯り付きの堤防だった。
まずポイントの分析。
・オレンジの灯が外洋に効いている、
・明確な潮流の変化が足元からしっかりある。
・港内はそこそこ深いけど、そんなに大規模でもない。
船溜まりがあって、港内にも灯りはそこそこある。
・ベイトのストック量、回遊量は『釣れる漁港』のそれだった。
・水深は、僕の認識の中の一般的なもので、足元の敷石が満潮時に5mあるなし、そこから落ちて付け根が10~20m。港内向きはそのままミオ筋と繋がっていて、外洋向きは払い出す潮によって削られているような印象。
外洋向きでも堤防根元側は根元による程、ブレイクが沖目に寄って行く地形になってた。
地形だけ見ていくと、呼子にもいっぱいあるよねって程度。
ここ最近、闇場でアジを釣ってる場所、結構それに当てはまるんだけど、灯りってのがまた一つキーなんだろう。
やはり灯りの有無ってのが、その瀬戸内のピンと呼子の違いで、
底餌の溜まる外洋向きのストック場を見ていくのが今後の方針。
灯りの無いとこでも多少効くんだろうけど、灯り着いてるとこ…探すしかねぇな。と。
一通り、現場の地形と潮を見てみると、堤防先端からまっすぐ沖目に三角形の潮目が出ている。
出る潮入る潮、周回潮流。それらでバランスの良い流れのタイミングでキレイな三角形。
やはりこうだよね。京泊と同じやね。
手に取るように自然と釣りが見えてくる。
タックルは流れの強さ、地形も見ながら現場合わせ。
底餌も潮によって位置が変わるだろうから、それをイメージして、潮ヨレの壁、壁の延長線上にあるブレイクラインにメバルの群は着くだろう。
流速が変われば浮いてくる個体も居て、そいつらは潮の壁に沿ってホバリングして浮上してくる。(はず)
加来さんに色々とアドバイス貰いながら、レンジとフォール姿勢を気にしながら、重さとラインの太さを流速に合わせてジグをリフト&フォール。
初日は潮も良く流れて、ストロークの長いフォールにガッツンガツン当ってくれた。
上げ潮の止まる直前、潮目の奥、ボトムまで一貫してフリーなスピニングスローでのマダイを皮切りに、

その前後には良いサイズの白メバルがポンポンと。

軽いラッシュも堪能。

この体高。
ディープのシロメバル、しっかりイカナゴに付いてるのもあって、
非常に良く引いてくれました。

ハイシーズンに少し遅れて釣ってるのもあってか、
少しのピン、立ち位置と流す角度の違いによっては、クロメバルも混じる。

加来さんの掛ける魚に結構クロが混じってたのを見ると、
ディープのオープンエリアにありながら、
コンディションの良いシロに狙いを絞ると、
打つべきピンはそう広くない様子。
群自体が潮で流れる餌に付いているので、スイッチの入る個体はその流れの一番良いトコに陣取ってるやつ。
彼ら自身が小規模な群で刻々と移動して定位ピンを変えるのか、
はたまた喰わないだけで、群自体は大きく潮向きの良い位置にいるヤツにだけスイッチが入っていたのかは、2日間では掴みきれなかった。
シーズン終盤である事を鑑みれば前者であるが、そこは想像の域を出ない。
それはともかく、どうもジグの動きの質で、
食う食わないってのも確かに出てきているようだった。
初日、やや活性の高い瞬間は、シーライドミニの得意とする、
スライド系の、割と動きの幅の大きめのアクションが効いているようだった。
イカナゴが追われてボトムや表層に向かって、3次元的にエスケープしている様子をイメージして演出した、長めの距離をバックスライドするような動きを入れた直後にバイトが集中した。
大幅なリフトから、ロッドストロークをしっかりと活かしての、
ほぼゼロテンションのロングフォール。
使ったジグはシーライドミニの9gとバイスライダーの10gだった。
より潮に噛ませたい時にシーライドミニ、潮を切って入れていきたい時にバイスライダーのリアウエイトセッティングっていう風な使い分け。
軽めでは潮の速い時間は釣りにならなかったのと、
例えそれを頑張ってレンジに入れてボトム潮流に乗せ、
小刻みに動かしながらヘコヘコとスローに漂わせながらドリフトを掛けていても、
アタリは少なく、ピンを外れたところで、狙いと違うコンディション、サイズの群が反応するばかりであったのだ。
潮がタルくなって、あまり流れない時間にボトムワインドを掛けると連発もした。
フォローベイトはやはりこれだろう。
(このワインドの釣りも、動画として残ってるのでDVDに入るはず)
ちなみに、急流の時のワインドは釣れなくないけど微妙で、圧倒的にジグに反応が良かった。
それに対して二日目は、状況が一転。
まとまった雨による、強めの水潮と、潮流も前日とは違い、とても緩かった。
他にも何か要素がありそうだったけど、魚の活性が極端に落ちていた。
この日、状況を見ながらワインドで始めた加来さんには良い魚が連発する。
その裏パターンに徹していた僕には、前半はアタリもほとんどなかった。
撮影中もジグにはミスバイトばかり。
潮が流れない中、シーライドミニのウエイトを3gまで落として、着底後、ワンピッチだけリフトした後は、テンションを入れてゆっくり流してみた。
それで最初の1匹目が出て、次のキャスト辺りで徐々に潮が流れ始める。
この日、キーとなる潮が動き出してから、釣りが続行不可能になる暴風に達するまでの小一時間。その終盤に見つけた魚は、ボトムから50cm程度のレンジを出来るだけキープしてドリフトを掛ける釣りが連れてきてくれたものだった。

ベイトタックルでより、レンジを細かくスローに刻むイメージで操作してたけど、
後から考えると、スピードを落としてもっと中層からその上までも、じっくり流してやれば、少し違った答えが出たのかもしれない。そんな時間はなかったけど(^^;
いよいよ暴風が吹く荒れ始め、それと同時に入ってきたアジの群。

それまでその位置、レンジには全く気配を感じなかったから、
吹き荒れだした風で押されたベイトを追って入ってきた群。
ポロポロと、非常にイージーだったから、コレはコレで楽しかった。
瀬戸内の変わりやすい潮流も考慮すると、この日の道具立ては4本になった。
リーダーの太さは細かいレンジを釣り分けようと試行錯誤。
マダイが出る事を考えれば、2号に固定しときたい感じでしたけどね。
スタンダードな流速1
rod GRF-85PEスペシャル
reel アブREVO-MGX2500
line PE0.5号+フロロ1.75~2.0号
スタンダードな流速2
rod プロトベイト65
reel アブREVO-LT
line PE0.4号+フロロ1.5~2.0号
潮がタルくてスローな時間用1
rod ウエダpro4ex 4S610SL/プロト60UL
reel ダイワ2004
line PE0.3号+フロロ1.5号
潮がタルくてスローな時間用2
rod ウエダpro4ex TFL-64EX-R
reel アブREVO-MGX2000
line フロロ0.6号直結
リグはメインがメタルジグ。
ボトムワインドも相当効くのは、状況的に間違いなくて、
フォローベイトとして常にスタンバイ。
潮流に合わせて魚の活性が変動していく事が多いはずなので、
それを目安に使い分けていくのが良いだろう。
使用したメタルは4種類。

右からシーライドミニ、爆釣ジグ、バイスライダーの3種に、
上はご当地メタルジグ、ブリスのメバジーも使用。
このメバジー、去年までは福岡唐津界隈でも買えたんだけど、
最近めっきり見なくなった。
この釣りには、どうしてもフロントバランスの並行姿勢で
ドリフトが決められるジグが選択肢の一つとして欲しくなる。
シーライドミニのテンション掛け気味バックスライドが割と近い仕事をするんで代用も出来なくはないんだけど、
潮流の強めのディープでレンジキープしながらのドリフトを、
より高次元にやっていくには、この4種類がどれも必要なんだなぁ。
補充しとこ。
- 2016年5月18日
- コメント(2)
コメントを見る
古賀 亮介‐snifさんのあわせて読みたい関連釣りログ
fimoニュース
登録ライター
- ヨーヅリ:トビマルJr.
- 1 日前
- ichi-goさん
- フィッシングショー大阪2026行…
- 5 日前
- ねこヒゲさん
- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…
- 16 日前
- hikaruさん
- 新年初買
- 22 日前
- rattleheadさん
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 24 日前
- 濵田就也さん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪
- ハマケン
-
- 流れの釣り
- Kazuma






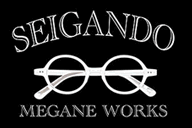
















最新のコメント