プロフィール
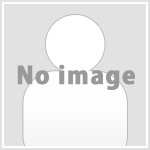
釣りバカ運送店
北海道
プロフィール詳細
カレンダー
検索
最近の投稿
アーカイブ
▼ 幸福ですぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!
- ジャンル:日記/一般
- (ハウツー?)
え・・・解りにくいネタ(タイトル)は置いといて
とりあえず、下をご覧くださいな
タイトル「色はどの深さまで見えるのかな?」
http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20080922/index.html
明るい色は、かろうじて見える程度ですね(汗
通常、太陽光は大まかですが「紫外線(以後UV=ウルトラヴァイオレットと表記します)→紫→藍→青→緑→黄色→オレンジ→赤→赤外線(同様にIR=インフラレッド)」に分けることができて、水中ではUV、IR、青系がそこそこ深い場所まで届いてくれて、中でもUVが一番深くまで届くと言われています
水中だけでなく、曇天でも、UVなら普通に地表まで届きますしね
「曇だから」って油断してると、意外と日焼けするんですよね・・・
なので、UVに反応して発光する蛍光色が、釣り道具の部材として効果がある事を昔から体感的に知っていたのでしょう
※この時、IRは“熱”として届くので、可視光とは少々違うんでしょうけど・・・
話を戻して
まぁ、上の動画の通り、一定の深さになると色も何も分からなくなりますし、良く水中映像を撮ったものを見ると水の中って青一色になってませんか?
「青1色の世界なので、特に色を認識する必要があるのか?」という事かどうかは分かりませんが、よく海水魚は“色盲だ”と言われています
あと、脳の体積・重量的に色覚まで処理しきれないだろうという事から色は分からないとも言われているようです
でも、ちょっと待ってください
深海に住むキンキやメヌケなどの赤い魚
色盲だと仮定しましょう
太陽光もイマイチ届かないので、赤い色は黒っぽくなり、周りと同化すると考えられます
保護色と考えればもっともな話だと思うのですが、ここで一つ問題が
“繁殖行動”の際、どうやって相手を見つける?
相手を見つけてから「恥ずかしいから、電気を消して♥」って訳ではないんです!はじめっから暗いんです!しかもお互いに保護色同士、見つけられませんがな
また、1年くらい前の「釣り新聞北海道」にも「魚が好む色はあるか」と言う特集記事では「赤い光以外を取り除くフィルターを通して海中を見たとき、微生物はもちろん魚すらも赤く発光している」と言う物でした
(2013年2月6日号 一部抜粋・要約)
まぁ、出典が出ている部分を間違えて捨ててしまったので、何の文献なのかはわからないのですが・・・(確か出ていたような気がするんですが・・・)
なので、多少なりとも色覚が、最低でも赤系の色は分かるんだろうと考えた方が良いのかなと思っております
実際にピンクシルバーとか、赤金とか、なんだかんだで赤系の色って外せないですもんね
とりあえず、下をご覧くださいな
タイトル「色はどの深さまで見えるのかな?」
http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20080922/index.html
明るい色は、かろうじて見える程度ですね(汗
通常、太陽光は大まかですが「紫外線(以後UV=ウルトラヴァイオレットと表記します)→紫→藍→青→緑→黄色→オレンジ→赤→赤外線(同様にIR=インフラレッド)」に分けることができて、水中ではUV、IR、青系がそこそこ深い場所まで届いてくれて、中でもUVが一番深くまで届くと言われています
水中だけでなく、曇天でも、UVなら普通に地表まで届きますしね
「曇だから」って油断してると、意外と日焼けするんですよね・・・
なので、UVに反応して発光する蛍光色が、釣り道具の部材として効果がある事を昔から体感的に知っていたのでしょう
※この時、IRは“熱”として届くので、可視光とは少々違うんでしょうけど・・・
話を戻して
まぁ、上の動画の通り、一定の深さになると色も何も分からなくなりますし、良く水中映像を撮ったものを見ると水の中って青一色になってませんか?
「青1色の世界なので、特に色を認識する必要があるのか?」という事かどうかは分かりませんが、よく海水魚は“色盲だ”と言われています
あと、脳の体積・重量的に色覚まで処理しきれないだろうという事から色は分からないとも言われているようです
でも、ちょっと待ってください
深海に住むキンキやメヌケなどの赤い魚
色盲だと仮定しましょう
太陽光もイマイチ届かないので、赤い色は黒っぽくなり、周りと同化すると考えられます
保護色と考えればもっともな話だと思うのですが、ここで一つ問題が
“繁殖行動”の際、どうやって相手を見つける?
相手を見つけてから「恥ずかしいから、電気を消して♥」って訳ではないんです!はじめっから暗いんです!しかもお互いに保護色同士、見つけられませんがな
また、1年くらい前の「釣り新聞北海道」にも「魚が好む色はあるか」と言う特集記事では「赤い光以外を取り除くフィルターを通して海中を見たとき、微生物はもちろん魚すらも赤く発光している」と言う物でした
(2013年2月6日号 一部抜粋・要約)
まぁ、出典が出ている部分を間違えて捨ててしまったので、何の文献なのかはわからないのですが・・・(確か出ていたような気がするんですが・・・)
なので、多少なりとも色覚が、最低でも赤系の色は分かるんだろうと考えた方が良いのかなと思っております
実際にピンクシルバーとか、赤金とか、なんだかんだで赤系の色って外せないですもんね
- 2014年3月5日
- コメント(5)
コメントを見る
釣りバカ運送店さんのあわせて読みたい関連釣りログ
fimoニュース
登録ライター
- 野生の本能を刺激する
- 1 日前
- はしおさん
- イズム:ビアマグ88F
- 5 日前
- ichi-goさん
- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…
- 10 日前
- hikaruさん
- リールにぴったりラインを巻く
- 12 日前
- papakidさん
- あなたが釣りをはじめた「きっ…
- 12 日前
- ねこヒゲさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!
- ハマケン
-
- 最近の釣果に感謝
- Kazuma



















1度魚に聞いてみたい気もしますけど、こうやって皆で議論してるのも楽しいですよね(^ ^)昔、PFJの人は『フィルムのネガみたいに見えている』と言ってましたね。本当のところは解りませんけど…
カペリン
北海道