プロフィール

つむ
東京都
プロフィール詳細
カレンダー
検索
タグ
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:1
- 昨日のアクセス:31
- 総アクセス数:202910
QRコード
対象魚
▼ 釣り場ゴミ問題②〜文献的考察〜
- ジャンル:日記/一般
さて、前回、好き勝手、釣り場ゴミ問題の私見を述べさせて頂いたわけですが、色々調べた結果、色々間違った考えであった事に気付かされたわけです。
マナーとモラルの問題である、と性悪説のせいにするべきではないようですし、
ゴミ拾いにも実は深い意味があった(そこまで考えてゴミ拾いしてるかは知らんが)!!
私見だけではなく、文献的考察をする事の大切さを改めて知りました。
ですから、波動が釣れる、ハイフローティングで強波動、テッパンバイブと樹脂バイブの違いは波動の違い、とか宣っている方は、ぜひ、文献的考察を加えて頂くと、説得力が増すと思いますよ(文献なんてないと思うけどw)。
主張には根拠が必要だし、
根拠のない主張は容易に論破されるし、
根拠の無い主張には説得力が無いって話は、以前しましたよね♪
ゴミ捨て行動の分類から、ゴミを捨てる人の心理、その対策まで論じられており、
釣り場ゴミ問題の対策にも有効だと思いました。
・ゴミ捨て行動の分類
ゴミ捨て行動には「集め捨て」と 「散らし捨て」がある!
ゴミの捨て方に分類がある事にまずびっくりなんですが。
「集め捨て」は、回収を目的として設置された容器へ人がゴミを自発的に投入することであり、集め捨て以外 はすべて「散らし捨て」になります。
散らし捨ての中には「ポイ捨て」「置き捨て」「隠し捨て」などがあります。
ゴミ捨て行動の視点からゴミ問題を考えるということは、
いかにして散らし捨てを防止できるか、
いかにして散らし捨てを集め捨てに導くことができるか、
さらにはいかにして 「分け捨て」(分別)させるか、などについて考えるということになる。
・ゴミの捨てられ方の規則性と"散らし捨て抵抗"
散らし捨てがされやすい場所は、
・U状部(凹部のある場所)
・T状部(置き捨て)
・L状部(壁ぎわ)
・エ状部(植え込みや柱の根元)
などが挙げられ、これらの場所に共通しているのは、散らし捨てをした時に目立ちにくい場所である、という事です。
「散らし捨て行為が
環境を変化させる度合が低い
と認識しうるような状況ほど
散らし捨てしやすい」
という事ができます。
このことから、人は散らし捨てを行うことに対 して何らかの心理的抵抗(="散らし捨て抵抗")を 有していることがわかります。
また、ある場所にゴミがすでに散らし捨てされていると"散らし捨て抵抗"は小さくなり、そこヘゴミが集中的に散らし捨てされやすくなる。
その場所がいわば"擬似ゴミ箱"と化すわけであり、これがいわゆる「ゴミがゴミを呼ぶ」 という現象であります。
ゴミアングラーがゴミアングラーを呼ぶ、とも言います。
チリ1つ落ちてないディズニーランドでポイ捨てする人が少ないのは、散らし捨て抵抗が高いからであり(秩序性の原則)、
ゴミだらけの釣り場で、ポイ捨てする人が多いのは散らし捨て抵抗が低いからなのでしょう。
ですから、釣り場のゴミ拾いなんてしたって根本的な解決にはならない、と言ってしまいましたが、
散らし捨て抵抗を高めるためには有用であると言えます。
ここまで考えてゴミ拾いしてるんだったら、マジ天才ですが・・・
瓢箪から駒、塞翁が馬ですな。
・最小エネルギーの法則
ゴミなんかを捨てるために人はエネルギーは使わない、使いたがらない、って法則です。
手が届く範囲にゴミ箱があればきちんとゴミ箱に捨てるし、
投げて届く範囲にゴミ箱があれば投げ入れる。
投げてゴミ箱を外れても、投げるようなやつはわざわざ拾いにはいかない。
ゴミを捨てるために何百メートルも離れたゴミ箱に捨てには行かないでしょ、って原理です。
・秩序性の原則
上でディズニーランドの例を挙げましたが、
「常にきれいな状態に保つことにより、人びとの"散らし捨て抵抗" を高める」ことは、散らし捨てを防止するために欠かせないことであり(秩序性の法則)、
利用者に散らし捨ての防止やゴミの持ち帰りを盛んに呼びかけたとしても、
その場がきれいな状態に保たれていなければ、 説得力をもちえないのである。
説得力ありますかね?
・インプット・アウトプットの原則
限られた範囲内であれば、秩序性の法則に基づいて、徹底清掃する事は可能ですが、広大な範囲(海、川、湖)をカバーする事は難しい。
このような場合には
「ゴ ミになる可能性のあるもの(潜在ゴミ)をできる限り少なくしてゴミの発生量そのものを減少させる」ことにより、散らし捨てを未然に防止する考え方が有効となる(「インプット・アウトプ ットの原則」)。
缶ジュースの自販機を置くという事は(インプット)、10分後の空き缶(アウトプット)を販売していると言うことである、と。
釣具のパッケージングには一考の余地があると言えますでしょうか。
簡易包装、自然分解、デポジットなど・・・
・便宜性の原則
人は集め捨てをする動機を潜在的に持ち合わせているものの、そのためにエネルギーを使いたがらないので、
ゴミが出やすい場所には、手が届きやすい場所に、適切に回収容器(ゴミ箱)を配置せよ、と。
ポイ捨てが問題となっている釣り場には、ゴミ箱が無いのではないでしょうか?
あっても、数が足りない、すぐに満杯になってしまっていたりして、適切に管理・回収されていない、などの問題が考えられます。
・見通しの原則
広域的な用地の場合には、回収容器の適正配置 による対応にも限界があるので、
利用者に対して「回収容器の所在場所についての情報を適切に与え、回収容器を心理的に近く感じさせる」考え方が採られる場合が多い(「 見通 しの原則」)。
人は一般に、自らの行動に"見通し"がつけば、そ れを目安としてなるべく計画的に行動しようとする。
人びとに回収容器がある場所をあらかじめ知らせることができれば、集め捨てへの「動機」を一定時間保持しつづけさせる、
すなわち、その回収容器の設置場所までゴミを発 生させることを控える、あるいはそこまでゴミを持ち歩いてもらうことができる、と考えられるのである。
・経済性の原則
ゴミはマイナスの価値を持つ商品、とされるが、
ゴミにプラスの価値を与える事で、集め捨てへ誘導する事ができる。
この考え方の代表がデポジット制度である。
ブルーブルーさんが行なっている、パッケージのポイントを集めて商品と交換、などはコレそのものだと思います!!
まとめ
ただ、ポイ捨てアングラーを取り締まったり、糾弾したり、ポイ捨て禁止!、
と言っているだけでは何も解決しない事がわかりました。
・秩序性の原則に則り、
ゴミ拾いを行い釣り場をキレイに維持する、これにより人の散らし捨て抵抗を高められると考えられる。
・インプット・アウトプットの原則に則り、
「ゴ ミになる可能性のあるもの(潜在ゴミ)をできる限り少なくしてゴミの発生量そのものを減少させる」ために、釣具のパッケージングを改良する必要がある(簡易包装、自然分解、デポジット(経済性の原則))
・便宜性の原則に則り、
釣り場に適切にゴミ箱を配置する。
たくさんあればあるほど、散らし捨ては回避できると思います。
この際、分別までは期待せずに、集め捨て、できた事だけでも良しとしましょう。
配置は適切であっても、回収・管理も適切に行われなければならない(土日など釣り人がたくさん来る日は、回収頻度を上げる、など)。
・見通しの原則に則り、
回収容器の所在場所についての情報を適切に与え、回収容器を心理的に近く感じさせる。
さてさて、
ある程度耐久性のあるゴミ箱であれば、
それこそ皆さんかfimoポイントを募ってw、
1回設置してしまえばそれで良いのですが、
問題は誰が回収して、誰が管理するか、ですね。
回収は、地方自治体にお願いしたいところですよね・・・そのお願いを誰がするのか・・・
ゴミ箱そのものの、清掃、管理については・・・
誰か頭がいい人、考えてください(笑)
あ、それか、fimoさんか、偉そうにメソッド語ってるメーカーさんとかが動いてくださっても良いですよ〜
- 2020年9月22日
- コメント(1)
コメントを見る
fimoニュース
登録ライター
- 野生の本能を刺激する
- 3 日前
- はしおさん
- イズム:ビアマグ88F
- 6 日前
- ichi-goさん
- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…
- 11 日前
- hikaruさん
- リールにぴったりラインを巻く
- 13 日前
- papakidさん
- あなたが釣りをはじめた「きっ…
- 13 日前
- ねこヒゲさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!
- ハマケン
-
- 最近の釣果に感謝
- Kazuma


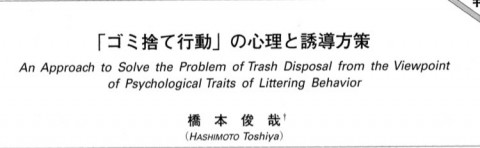
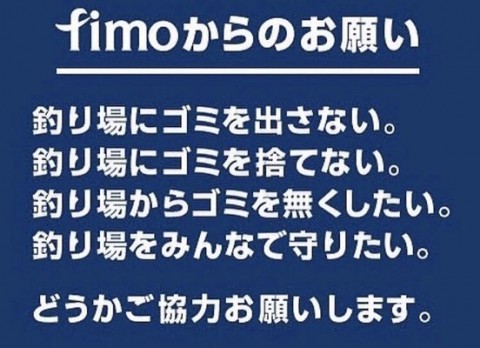















最新のコメント