プロフィール
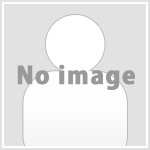
paltaro
神奈川県
プロフィール詳細
カレンダー
検索
タグ
タグは未登録です。
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:6
- 昨日のアクセス:167
- 総アクセス数:678836
QRコード
▼ リバーシーバスの上げ潮ゲームの考え方
- ジャンル:style-攻略法
さて皆様こんにちは。
本日は大潮だったので上げ潮で相模川に釣りに行ってきました。狙いはあげっぱなです。
相模川のハクパターン飽きたとかいいつつ、潮回りが良いと相模川へハクパターンで遊びに行ってしまう男、スパイダーマッ!
とネタはここまでにして本題。
本日は相模川で恐らく、現在一番ハクが溜まってる場所にエントリー。ココは多分、湘南エリアで一番ハクが溜まってるんじゃね?というポイント。とにかくもの凄い数のハクがいます。ちなみに流れがほとんどないのも特徴。
ベイトはいるけど流れはない。上げ潮。こんなんで釣りになるのかって?なります。上げ潮ゲーの時は流れとか僕は全く気にしません。下げ潮ゲーでは流れが第一ですが、上げ潮ゲーは地形と潮位が第一です。
先に釣果から書いときますが、5ヒット3キャッチ2バラシでした。久々のフィーバーです。ルアー?いつものロリベ48です。ハクパターンはロリベ48が全てですが何か。
釣れたのは、

コンディションが滅茶苦茶いい鱸サイズの62センチと、

いつものセイゴです。もう一匹釣ったのは小さすぎたので写真とらずにリリースしました。バラシた二匹もセイゴですね。引きからしてね。
さて、本日はちょっと趣向を変えて「リバーシーバスの上げ潮ゲーム」について書こうと思います。長くなるかもしれませんが、暇な人はおつきあいください。
と、その前に、ちょっと小説「神なるオオカミ」の話をはさみます。この小説は、文化大革命の時代、内モンゴルに下放された筆者の自伝的フィクションなんですが、その中のちょっとしたエピソードを紹介します。
「神なるオオカミ」って小説は、基本的にモンゴルのオオカミの生態を詳しく描写しているのですが、その中にオオカミによる黄羊(モウコガゼル)の狩りの話が出てきます。
この黄羊ですが、草原で一番足が速い生き物でして、オオカミがどんなに頑張っても追いかけっこでは捕まえることができません。ではオオカミ達はどうやって黄羊を狩るのか?
答えは地形と天候の利用です。オオカミは群れで雪が積もった崖に黄羊を追い込みます。雪が積もっているので崖があることに黄羊達は気づけません。黄羊達は、足下の雪が突然崩れ、崖の底に落ちていく時、初めて自分達が恐ろしい天然の罠にかけられた事に気付くんです。
なんでこんな話を挟むかというと、実は似たような事をシーバス達はしているからなんです。
僕はシーバス始めた頃、シーバスってのはブラックバスの仲間くらいに思ってました。実際、ブラックバスと共通している所もありますし、ストラクチャーについてる魚を捕る方法ってのはブラックバスもシーバスも一緒だったりします。
しかし、この二つは決定的に違っている所があります。それはシーバスは群れで狩りをするが、ブラックバスは単独でエサを取るって所です。
ここからは、僕のシーバス観を決定づけたエピソードになるのですが、ある冬の釣りの時でした。当時、僕は全然釣れないアングラーで、「今日も坊主だしラーメンでも食って帰るか・・・・」と寒い中、とぼとぼと相模川の河川敷を歩いていた訳です。
その日は大潮で時間的にはすでに上げ潮の一分くらいでした。その時の僕は「シーバスは下げで釣るもの」という固定観念に縛られていたのですが、不思議な光景を目にしたんです。
その場所は干潮になると完全に干上がってしまうシャローだったんですが、なんと水際でイナッコがざわつき始めたんです。
この話は二月の話で、二月といえば産卵後のアフターの時期です。アフターシーバスはガリガリでイナッコを追い回すような体力が残ってるはずがありません。僕としては「?????」という感じでした。イナッコがざわついてるけど、一体、何の魚がイナッコを追い回してるんだ?と。この時期のシーバスにイナッコ追い回す体力はないし、マルタ?
そうしていると、突如として、辺り一帯でボイルが起きたんです。僕が見た中でも最大級のボイルでした。逃げ惑うイナッコと、それを補食するシーバス達。
一体、何が起きたのか?
結論から言えば、「上げ潮でシャローに入ろうとするイナッコを、かけあがりにシーバスの群れが追い込んで補食していた」です。
その場所なんですが、冬場は干潮になると完全に干上がってしまうシャローでした。一方で、真冬でも生活排水なんかが流れ込むせいか、比較的水温が高く、イナッコなんかが真冬に集まってきたりします。
シーバス達は、そんなイナッコ達が大潮の上げ潮でシャローに移動しようとする、まさにその瞬間を待っていたんです。シーバスは群れでシャローに水が入るか入らないかのタイミングを見計らって、かけあがりにイナッコ達を追い込みました。イナッコ達はかけあがりに追い込まれ、逃げ場を失います。縦の移動は水が無くてできない。横の移動もかけあがりのせいで制限されている。シーバス達が仕掛けた恐ろしい、恐ろしい天然の罠。
僕はシーバス達の狩りをただ呆然と眺めるだけでした。
この時、僕は初めて、シーバスの群れでの狩りを目撃したんです。そして、この時から僕は「シーバスは群れで狩りをする魚」だという認識を持ったんです。ここが決定的にブラックバスと違います。
ちなみにシーバスの群れでの狩りの話はコアマンの泉さんの著書「シーバスノート2」にも載ってますので興味のある人はどうぞ。
そして、この日以来、僕のシーバス釣りは変わりました。
何が変わったかって、上げ潮でしょっちゅう釣行するようになったんです。リバーシーバスで。僕が今年釣ったシーバスは、ほとんど上げ潮で釣った魚です。相模川の場合、バチ抜けは小規模だから、冬~春は上げ潮で釣った方が効率が良い位なんです。
そして、上げ潮で釣る時の考え方は、上記のシーバス達の狩りが基本になっています。あの日、あの時、シーバス達は「地形」と「潮位」を利用してイナッコ達を狩っていました。二月のシーバスは産卵後で速く泳ぐことはできません。でも、地形と潮位を利用して、ド干潮時に水のないシャローのかけあがりにイナッコを追い込んでしまえば、あとは食い放題なんです。流れなんて必要ないんです。
今日の釣りも、まさにこの形での釣りです。上げ潮のハクパターンでしたが、ド干潮で本流に落ちたハクがシャローに戻ろうとしている所を、シーバスがストラクチャー際に追い込んで補食しているのを狙った訳です。
今日は狙いが綺麗にハマって、時合いがくるとポンポンと簡単に釣れました。流して釣った魚は一匹もいません。全部巻いて釣りました。流れが全くない場所でしたが、そんな所にも鱸サイズが入ってくるモンなんです。(テクトロで2ヒット、際を舐めるように巻いて3ヒット)
僕のシーバスの上げ潮ゲームの基本的な考え方は、これで大体分かって頂けたかと思います。
他にも上げ潮ゲーでは塩水くさびを利用した釣り方とかもあるんですが、それは相模川の超有名アングラーの久保田さんが説明しているので、久保田さんの記事をあたってみてください。久保田さんがメーターシーバス釣った記事です。探せばすぐ出てきます。
相模川には、上げ潮でシーバスがベイトを追い込んで補食する場所が幾つかあります。ヒントだけ書いておきますが、「干潮で干上がってしまうシャロー」と「護岸」もしくは「かけあがり」が隣接している場所になります。
これは相模川だけでなく、湘南エリアの河川であれば、どこでも通用するメソッドだったりするので、上げ潮ゲームをするのであれば、そういう地形を探してみてください。ベイトがそういう地形に追い込まれている時は、上げ潮ゲーが成立します。
それと、ロリベばっか使ってて、「お前タックルハウスの回しモンかよ」とか言われそうな勢いですが、しょうがないんです、これが一番釣れるんだから。ロリベって、あらゆるシーバスブログで創○学○における○田○作みたいに賞賛されていて気持ちが悪いルアーですよね。これほど、皆が口を揃えて「釣れる」と連呼してるルアーも珍しい。シーバス始めた頃、一番胡散臭いと思ったルアーです。はっきりいってステマとしか思えなかった。最初使った時は全然釣れなかったし。
でもね。一回使い方を覚えたら、他のルアーなんていらないじゃんって思う位よく釣れるです、このルアー。反則級に釣れる。他のあらゆるルアーが無効化するハクパターンで、コンスタントに魚連れてきてくれるのはロリベ48,48SSSだけです。
そんな訳ですので、僕はロリベ信者と呼ばれてもしょうがないと思ってます。ロリベがないとシーバス釣れません。以上!
本日は大潮だったので上げ潮で相模川に釣りに行ってきました。狙いはあげっぱなです。
相模川のハクパターン飽きたとかいいつつ、潮回りが良いと相模川へハクパターンで遊びに行ってしまう男、スパイダーマッ!
とネタはここまでにして本題。
本日は相模川で恐らく、現在一番ハクが溜まってる場所にエントリー。ココは多分、湘南エリアで一番ハクが溜まってるんじゃね?というポイント。とにかくもの凄い数のハクがいます。ちなみに流れがほとんどないのも特徴。
ベイトはいるけど流れはない。上げ潮。こんなんで釣りになるのかって?なります。上げ潮ゲーの時は流れとか僕は全く気にしません。下げ潮ゲーでは流れが第一ですが、上げ潮ゲーは地形と潮位が第一です。
先に釣果から書いときますが、5ヒット3キャッチ2バラシでした。久々のフィーバーです。ルアー?いつものロリベ48です。ハクパターンはロリベ48が全てですが何か。
釣れたのは、

コンディションが滅茶苦茶いい鱸サイズの62センチと、

いつものセイゴです。もう一匹釣ったのは小さすぎたので写真とらずにリリースしました。バラシた二匹もセイゴですね。引きからしてね。
さて、本日はちょっと趣向を変えて「リバーシーバスの上げ潮ゲーム」について書こうと思います。長くなるかもしれませんが、暇な人はおつきあいください。
と、その前に、ちょっと小説「神なるオオカミ」の話をはさみます。この小説は、文化大革命の時代、内モンゴルに下放された筆者の自伝的フィクションなんですが、その中のちょっとしたエピソードを紹介します。
「神なるオオカミ」って小説は、基本的にモンゴルのオオカミの生態を詳しく描写しているのですが、その中にオオカミによる黄羊(モウコガゼル)の狩りの話が出てきます。
この黄羊ですが、草原で一番足が速い生き物でして、オオカミがどんなに頑張っても追いかけっこでは捕まえることができません。ではオオカミ達はどうやって黄羊を狩るのか?
答えは地形と天候の利用です。オオカミは群れで雪が積もった崖に黄羊を追い込みます。雪が積もっているので崖があることに黄羊達は気づけません。黄羊達は、足下の雪が突然崩れ、崖の底に落ちていく時、初めて自分達が恐ろしい天然の罠にかけられた事に気付くんです。
なんでこんな話を挟むかというと、実は似たような事をシーバス達はしているからなんです。
僕はシーバス始めた頃、シーバスってのはブラックバスの仲間くらいに思ってました。実際、ブラックバスと共通している所もありますし、ストラクチャーについてる魚を捕る方法ってのはブラックバスもシーバスも一緒だったりします。
しかし、この二つは決定的に違っている所があります。それはシーバスは群れで狩りをするが、ブラックバスは単独でエサを取るって所です。
ここからは、僕のシーバス観を決定づけたエピソードになるのですが、ある冬の釣りの時でした。当時、僕は全然釣れないアングラーで、「今日も坊主だしラーメンでも食って帰るか・・・・」と寒い中、とぼとぼと相模川の河川敷を歩いていた訳です。
その日は大潮で時間的にはすでに上げ潮の一分くらいでした。その時の僕は「シーバスは下げで釣るもの」という固定観念に縛られていたのですが、不思議な光景を目にしたんです。
その場所は干潮になると完全に干上がってしまうシャローだったんですが、なんと水際でイナッコがざわつき始めたんです。
この話は二月の話で、二月といえば産卵後のアフターの時期です。アフターシーバスはガリガリでイナッコを追い回すような体力が残ってるはずがありません。僕としては「?????」という感じでした。イナッコがざわついてるけど、一体、何の魚がイナッコを追い回してるんだ?と。この時期のシーバスにイナッコ追い回す体力はないし、マルタ?
そうしていると、突如として、辺り一帯でボイルが起きたんです。僕が見た中でも最大級のボイルでした。逃げ惑うイナッコと、それを補食するシーバス達。
一体、何が起きたのか?
結論から言えば、「上げ潮でシャローに入ろうとするイナッコを、かけあがりにシーバスの群れが追い込んで補食していた」です。
その場所なんですが、冬場は干潮になると完全に干上がってしまうシャローでした。一方で、真冬でも生活排水なんかが流れ込むせいか、比較的水温が高く、イナッコなんかが真冬に集まってきたりします。
シーバス達は、そんなイナッコ達が大潮の上げ潮でシャローに移動しようとする、まさにその瞬間を待っていたんです。シーバスは群れでシャローに水が入るか入らないかのタイミングを見計らって、かけあがりにイナッコ達を追い込みました。イナッコ達はかけあがりに追い込まれ、逃げ場を失います。縦の移動は水が無くてできない。横の移動もかけあがりのせいで制限されている。シーバス達が仕掛けた恐ろしい、恐ろしい天然の罠。
僕はシーバス達の狩りをただ呆然と眺めるだけでした。
この時、僕は初めて、シーバスの群れでの狩りを目撃したんです。そして、この時から僕は「シーバスは群れで狩りをする魚」だという認識を持ったんです。ここが決定的にブラックバスと違います。
ちなみにシーバスの群れでの狩りの話はコアマンの泉さんの著書「シーバスノート2」にも載ってますので興味のある人はどうぞ。
そして、この日以来、僕のシーバス釣りは変わりました。
何が変わったかって、上げ潮でしょっちゅう釣行するようになったんです。リバーシーバスで。僕が今年釣ったシーバスは、ほとんど上げ潮で釣った魚です。相模川の場合、バチ抜けは小規模だから、冬~春は上げ潮で釣った方が効率が良い位なんです。
そして、上げ潮で釣る時の考え方は、上記のシーバス達の狩りが基本になっています。あの日、あの時、シーバス達は「地形」と「潮位」を利用してイナッコ達を狩っていました。二月のシーバスは産卵後で速く泳ぐことはできません。でも、地形と潮位を利用して、ド干潮時に水のないシャローのかけあがりにイナッコを追い込んでしまえば、あとは食い放題なんです。流れなんて必要ないんです。
今日の釣りも、まさにこの形での釣りです。上げ潮のハクパターンでしたが、ド干潮で本流に落ちたハクがシャローに戻ろうとしている所を、シーバスがストラクチャー際に追い込んで補食しているのを狙った訳です。
今日は狙いが綺麗にハマって、時合いがくるとポンポンと簡単に釣れました。流して釣った魚は一匹もいません。全部巻いて釣りました。流れが全くない場所でしたが、そんな所にも鱸サイズが入ってくるモンなんです。(テクトロで2ヒット、際を舐めるように巻いて3ヒット)
僕のシーバスの上げ潮ゲームの基本的な考え方は、これで大体分かって頂けたかと思います。
他にも上げ潮ゲーでは塩水くさびを利用した釣り方とかもあるんですが、それは相模川の超有名アングラーの久保田さんが説明しているので、久保田さんの記事をあたってみてください。久保田さんがメーターシーバス釣った記事です。探せばすぐ出てきます。
相模川には、上げ潮でシーバスがベイトを追い込んで補食する場所が幾つかあります。ヒントだけ書いておきますが、「干潮で干上がってしまうシャロー」と「護岸」もしくは「かけあがり」が隣接している場所になります。
これは相模川だけでなく、湘南エリアの河川であれば、どこでも通用するメソッドだったりするので、上げ潮ゲームをするのであれば、そういう地形を探してみてください。ベイトがそういう地形に追い込まれている時は、上げ潮ゲーが成立します。
それと、ロリベばっか使ってて、「お前タックルハウスの回しモンかよ」とか言われそうな勢いですが、しょうがないんです、これが一番釣れるんだから。ロリベって、あらゆるシーバスブログで創○学○における○田○作みたいに賞賛されていて気持ちが悪いルアーですよね。これほど、皆が口を揃えて「釣れる」と連呼してるルアーも珍しい。シーバス始めた頃、一番胡散臭いと思ったルアーです。はっきりいってステマとしか思えなかった。最初使った時は全然釣れなかったし。
でもね。一回使い方を覚えたら、他のルアーなんていらないじゃんって思う位よく釣れるです、このルアー。反則級に釣れる。他のあらゆるルアーが無効化するハクパターンで、コンスタントに魚連れてきてくれるのはロリベ48,48SSSだけです。
そんな訳ですので、僕はロリベ信者と呼ばれてもしょうがないと思ってます。ロリベがないとシーバス釣れません。以上!
- 2016年5月23日
- コメント(2)
コメントを見る
fimoニュース
| 12月25日 | 釣り人アルアル 『釣り師の悟り』 |
|---|
| 12月25日 | 眠るルアーたち2025 家にある全ストック紹介! |
|---|
登録ライター
本日のGoodGame
シーバス
-
- 一瞬の時合いを捉え⋯た!?
- SAGE愛好会
-
- 今夜は釣れた
- サカバンパスピス



















最新のコメント