プロフィール
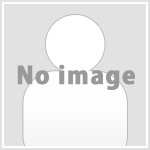
paltaro
神奈川県
プロフィール詳細
カレンダー
検索
タグ
タグは未登録です。
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:108
- 昨日のアクセス:151
- 総アクセス数:685083
QRコード
▼ ロープロのベイトリールは何故丸形を駆逐したのかって話
- ジャンル:日記/一般
最近、リールの話ばっかりですけど、今日もリールの話です。
先日はアブの6500の話でしたけど、今日はロープロベイトリールの話ですね。自分用に整理しとく事にしました。
BCスイングキャストの練習を続けるうちに、ベイトリールの機構について再勉強することになり、特にレベルワインドがなぜ、今の形に落ち着くことになったのか整理するためです。
アブが1952年にレコードアンバサダー5000を発表し、これが丸形ベイトリールの基本形となりました。遠心ブレーキ、レベルワインド、クラッチ、メカニカルブレーキ、ドラグといったベイトリールの基本となる機能が詰め込まれた製品でした。
丸形ベイトリールについては、これでほぼ完成していて、後に出てくるマグネットブレーキをつける位しか、あとは、ほとんどいじる所がないほどです。
現在に至るまでそうなのですが、丸形ベイトリールとしてはほぼこれで完成系なんですね。
こいつは世界最高のベイトリールという評価を受け、アブは世界最高のリールメーカーへと成長します。
しかし、アブと丸形ベイトリールの時代は1970年代後半に終わりを告げました。そう、日本メーカーの台頭です。
丸形ベイトリールの時代を終わらせたのは、1976年当時は全くの無名の存在だったシマノ社とルー社が共同開発したベイトリール、「スピードスプールBB」の登場です。日本ではBM-1ですね。
スピードスプールBBは、現在主流のロープロベイトリールの元祖といっていい存在です。
まず現在では当たり前の機能ですが「パーミングする側のサイドプレートでなくハンドル側にキャスコン」をつける事によって、パーミングしている時にキャスコンが手に当って痛い、なんて事がなくなりました。
そして一番の変更点であり、画期的だったのは丸形を捨てた事です。丸形を捨てた事で、スプールとレベルワインダーの距離を空ける事に成功したのです。
この結果として、スピードスプールBBはシンクロレベルワインダーを捨てる事が可能になりました。クラッチ切ったらスプールが回るだけ。
ラインとレベルワインダーの摩擦は増えましたが、スプールとレベルワインダーの距離が大幅に開いた結果、実際の釣りでは特に何も問題は無くなったのです。ラインとレベルワインダーの角度が丸形より緩やかになった事がこの結果を生んだのです。
先日も述べましたが、丸形ベイトリールはその構造的な問題からスプールとレベルワインダーの距離を大きく空けることができません。その結果、キャスト時にレベルワインダーを固定してしまうと、ラインとレベルワインダーの摩擦が酷いことになり、数多くのトラブルの原因になります。
その解決策としてアブが出した答えがシンクロレベルワインダー、スプールの回転とレベルワインダーが同調するシステムだったのです。
しかし、これは構造的な問題を孕んでいました。
まず一つ目。スプールの回転力を使ってレベルワインダーを動かすシステムのために、それ自体が強力なブレーキとして働いてしまうのです。そのため、ルアーの後半の飛距離が制限されてしまうという問題。常に強力なマグブレーキを搭載しているようなものなんですね。しかもこのブレーキは弱めることができません。
そして二つ目がメンテナンスにまつわる問題です。上記の問題から、丸形ベイトリールではレベルワインダーを常に綺麗にしておく事が非常に重要です。レベルワインダーに汚れが溜まると、ブレーキが強まったのと同じ状態になり、ルアーの飛距離が著しく落ちてくるのです。そのためレベルワインダーのメンテが欠かせないのです。
要するに、シンクロレベルワインダー搭載の丸形ベイトリールはメンテナンスが非常に面倒くさいリールなんです。
昔の釣り漫画とかだと、ベイトリールのレベルワインダーを磨いている描写があったりしますが、あれは丸形ベイトリールを使う際には非常に重要な事だったのです。
ところが、スピードスプールBBと、その後に主流になるロープロのベイトリールでは、レベルワインダーを磨き上げるなんて手間はいらないのですよ。レベルワインダー磨いた所で飛距離には影響ないわけだし。
こうしてロープロと丸形のメリットとデメリットを天秤に載せると、圧倒的にロープロのメリットがでかいんです。
だって、苦労してレベルワインダー磨き上げ、メンテを完璧にした丸形ベイトリールと、特にメンテしてないロープロベイトリールで飛距離がほとんどかわらないんですよ。そのうえ、ロープロは握りやすいときてる。
これだったら、ロープロをみんな使うでしょう。手間かからんしパーミング楽だし。
その結果としてロープロのベイトリールは丸形を駆逐して、ベイトリールの主流となった訳です。
こうしてベイトリールの歴史を紐解くと、何故丸形リールではシンクロレベルワインドが必要とされたのか、そして何故ロープロのベイトリールが主流になったのかを知ることができたわけです。
しかし、現在でもなお、ロープロのベイトリールはラインとレベルワインダーの摩擦が避けられないという構造的な問題を抱え続けているわけです。
この問題をどうにかしようとしたのがダイワでゼロフリクションだったりTWSを生み出してきたわけですね。
それはまた別のお話。
ではでは。
先日はアブの6500の話でしたけど、今日はロープロベイトリールの話ですね。自分用に整理しとく事にしました。
BCスイングキャストの練習を続けるうちに、ベイトリールの機構について再勉強することになり、特にレベルワインドがなぜ、今の形に落ち着くことになったのか整理するためです。
アブが1952年にレコードアンバサダー5000を発表し、これが丸形ベイトリールの基本形となりました。遠心ブレーキ、レベルワインド、クラッチ、メカニカルブレーキ、ドラグといったベイトリールの基本となる機能が詰め込まれた製品でした。
丸形ベイトリールについては、これでほぼ完成していて、後に出てくるマグネットブレーキをつける位しか、あとは、ほとんどいじる所がないほどです。
現在に至るまでそうなのですが、丸形ベイトリールとしてはほぼこれで完成系なんですね。
こいつは世界最高のベイトリールという評価を受け、アブは世界最高のリールメーカーへと成長します。
しかし、アブと丸形ベイトリールの時代は1970年代後半に終わりを告げました。そう、日本メーカーの台頭です。
丸形ベイトリールの時代を終わらせたのは、1976年当時は全くの無名の存在だったシマノ社とルー社が共同開発したベイトリール、「スピードスプールBB」の登場です。日本ではBM-1ですね。
スピードスプールBBは、現在主流のロープロベイトリールの元祖といっていい存在です。
まず現在では当たり前の機能ですが「パーミングする側のサイドプレートでなくハンドル側にキャスコン」をつける事によって、パーミングしている時にキャスコンが手に当って痛い、なんて事がなくなりました。
そして一番の変更点であり、画期的だったのは丸形を捨てた事です。丸形を捨てた事で、スプールとレベルワインダーの距離を空ける事に成功したのです。
この結果として、スピードスプールBBはシンクロレベルワインダーを捨てる事が可能になりました。クラッチ切ったらスプールが回るだけ。
ラインとレベルワインダーの摩擦は増えましたが、スプールとレベルワインダーの距離が大幅に開いた結果、実際の釣りでは特に何も問題は無くなったのです。ラインとレベルワインダーの角度が丸形より緩やかになった事がこの結果を生んだのです。
先日も述べましたが、丸形ベイトリールはその構造的な問題からスプールとレベルワインダーの距離を大きく空けることができません。その結果、キャスト時にレベルワインダーを固定してしまうと、ラインとレベルワインダーの摩擦が酷いことになり、数多くのトラブルの原因になります。
その解決策としてアブが出した答えがシンクロレベルワインダー、スプールの回転とレベルワインダーが同調するシステムだったのです。
しかし、これは構造的な問題を孕んでいました。
まず一つ目。スプールの回転力を使ってレベルワインダーを動かすシステムのために、それ自体が強力なブレーキとして働いてしまうのです。そのため、ルアーの後半の飛距離が制限されてしまうという問題。常に強力なマグブレーキを搭載しているようなものなんですね。しかもこのブレーキは弱めることができません。
そして二つ目がメンテナンスにまつわる問題です。上記の問題から、丸形ベイトリールではレベルワインダーを常に綺麗にしておく事が非常に重要です。レベルワインダーに汚れが溜まると、ブレーキが強まったのと同じ状態になり、ルアーの飛距離が著しく落ちてくるのです。そのためレベルワインダーのメンテが欠かせないのです。
要するに、シンクロレベルワインダー搭載の丸形ベイトリールはメンテナンスが非常に面倒くさいリールなんです。
昔の釣り漫画とかだと、ベイトリールのレベルワインダーを磨いている描写があったりしますが、あれは丸形ベイトリールを使う際には非常に重要な事だったのです。
ところが、スピードスプールBBと、その後に主流になるロープロのベイトリールでは、レベルワインダーを磨き上げるなんて手間はいらないのですよ。レベルワインダー磨いた所で飛距離には影響ないわけだし。
こうしてロープロと丸形のメリットとデメリットを天秤に載せると、圧倒的にロープロのメリットがでかいんです。
だって、苦労してレベルワインダー磨き上げ、メンテを完璧にした丸形ベイトリールと、特にメンテしてないロープロベイトリールで飛距離がほとんどかわらないんですよ。そのうえ、ロープロは握りやすいときてる。
これだったら、ロープロをみんな使うでしょう。手間かからんしパーミング楽だし。
その結果としてロープロのベイトリールは丸形を駆逐して、ベイトリールの主流となった訳です。
こうしてベイトリールの歴史を紐解くと、何故丸形リールではシンクロレベルワインドが必要とされたのか、そして何故ロープロのベイトリールが主流になったのかを知ることができたわけです。
しかし、現在でもなお、ロープロのベイトリールはラインとレベルワインダーの摩擦が避けられないという構造的な問題を抱え続けているわけです。
この問題をどうにかしようとしたのがダイワでゼロフリクションだったりTWSを生み出してきたわけですね。
それはまた別のお話。
ではでは。
- 2021年12月8日
- コメント(0)
コメントを見る
fimoニュース
登録ライター
- スミス:ディプシードゥMAX
- 1 日前
- ichi-goさん
- 新年初買
- 8 日前
- rattleheadさん
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 11 日前
- 濵田就也さん
- 野生の本能を刺激する
- 18 日前
- はしおさん
- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…
- 26 日前
- hikaruさん















最新のコメント