プロフィール
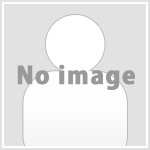
paltaro
神奈川県
プロフィール詳細
カレンダー
検索
タグ
タグは未登録です。
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:131
- 昨日のアクセス:179
- 総アクセス数:686051
QRコード
▼ シーバスフィッシングの道具のトレンドについて考える
- ジャンル:釣り具インプレ
今日の夜は暇なんで、たまには真面目な考察記事でも書いてみようと思う。
お題は「シーバスフィッシングの道具のトレンド」である。
現在のシーバスフィッシングなんだけど、スタンダートなロッド、リール、ライン、ルアーについてまとめると、
ロッド:8.7ft~9.6ft
リール:スピニングの2500~3000番
ライン:PEライン0.8~1.5+リーダー
ルアー:8~12㎝の移動重心ミノー、シンペン、バイブ
といった感じの道具が主流になっている。大体、どこの釣具屋にいっても、シーバスフィッシング売り場で売られているのはこんな道具達になる。
これらの道具を見れば一目瞭然なんだけれど、現在のシーバスフィッシングのトレンドは一言で表すと
「飛距離絶対主義」
である。
長い竿にスピニングリールつけて、PEラインを巻いて、移動重心のルアーをぶっ飛ばす。シーバスフィッシングの売り場で売られているのは、そんな道具達なのだ。
さて、こういった傾向はシーバスフィッシングの黎明期からあったのかと言われると、
石巻シーバスの歩みを振り返る【釣れないから面白い?辛いから楽しい?】
こちらに東北の巨匠こと村岡博之さんの石巻シーバスの歴史の記事があるけど、30年前の村岡さんが始めた頃のタックルは、6ft半のトラウトロッドに6lbのナイロン巻いたスピニングでシンキングミノーを巻く釣りだった。
シーバスフィッシングの黎明期は、まだ専用ロッドとかなくてバスロッドとかトラウトロッドを流用していた時代だ。ミノーもシンキングが主流でラパラCDとかボーマーのロングAとかが人気だった時代である。
ラパラCDは現在でも生き残っているけれど、ボーマーのロングAはシーバスで使っている人はいなくなった。バスの世界ではロングAはまだ使う人がいるんだけれど、シーバスの世界では誰も使わない。
理由は単純。移動重心ミノーの先駆けであるK-TENが発売され、ボーマーのロングAを使う必要がなくなったからだ。
ラパラCDは元々遠投する為に使われるルアーではなくて、飛距離はそんな必要ない、ストラクチャーの多い港湾でよく使われるルアーだった。これは現在でもそうだし、そういう場所では現在もなお、最強のルアーである。だからラパラは生き残った。(ストラクチャーの多い場所では固定重心のルアーが強い。この話は後でする)
一方で、ボーマーのロングAは河口部なんかのオープンエリアで使われていたルアーだったんだけど、より飛距離がでる移動重心ミノーが各社から発売され始めるとロングAは瞬く間に姿を消してしまったのである。
このロングAに起きた事は、ロッド、ライン、リールにも起きた。ロッドはどんどん長尺化し、ベイトリールは飛距離が出ないからシーバスの世界では主流にはなれず、ラインはナイロンとフロロを押しのけてPEが主流になったのである。
オープンエリアで、長い竿に、スピニングリールをつけて、PE巻いて、重心移動ルアーをぶっ飛ばす。
それが現在のシーバスのトレンドなのだ。だから飛距離が出るタックルがここまで人気がでる。
この対極にある釣りとしては、
「ショートロッドに
ベイトリールつけて
太いラインを巻き
軽いルアーを投げる釣り」
となるだろう。この釣りとはよーするにブラックバスのベイトフィネスだ。延々とカバーを探る釣りで、オープンエリアを探る釣りの対極にある釣りといっていい。
こういった障害物についてる魚を取る釣りは、シーバスフィッシングではボートシーバスが主流で、おかっぱりでは殆ど行われていないと言って良い。
原因は主に二つ。
一つめは2004年の改正SOLAS条約のせいで、港湾部への立ち入りが規制され、港湾のシーバス釣りがもの凄く難しくなったこと。そして二つ目だけど、陸っぱりから狙えるストラクチャーってのは目立つので、どこにいっても人的プレッシャーが強くて魚がスレてしまい、釣りにくいのだ。
その結果、現在のシーバスフィッシングの主流は河川のオープンエリアとなり、オープンエリアで強いロングロッド、スピニング+PE、重心移動ルアーがメインストリームになったと言えるだろう。
具体的な例をだすと、9.6ftのロッドに0.8のPEをスピニングに巻いて、オープンエリアでX-80ぶっ飛ばすのが、おかっぱりのシーバスである。そして大概hogeる。
一方で、ボートシーバスなんかは6.6ftのロッドに12LBのフロロをベイトに巻いて、ビーフリーズで穴撃ちする。滅茶苦茶釣れる。
こうやって書くと、ショートロッドと太いライン、ベイトリール、ビーフリのが優れているように見えるかもしれないけど、ボートシーバスの穴撃ちでは、
「ボート上からの正確なキャストの為のショートロッドとベイトリール、
摩擦で切れにくいフロロ12ポンド、
ストラクチャーに当てても壊れず
水中で障害物に当たっても泳ぎ続ける固定重心ルアー」
のが向いてるからそーなるってだけなのだ。
それに、オープンエリアの釣りって、そんな釣れるモンでもないのだ・・・・これは昔っからそーだった・・・・。比較的釣りやすい港湾部から釣りにくいオープンエリアが主戦場になった訳でそりゃ釣れなくなるって話だ。
結局、現在のシーバス釣りのトレンドについて考えていくと、河川下流部のオープンエリアでの釣りが主流になった事で、ロッドの長尺化、PEと移動重心ルアーの隆盛、ミノーのリップレス化が進んだって事になる。
ショートロッド、ベイトリール、太いナイロンorフロロライン、固定重心ルアーが釣れない訳ではない。ただ、おかっぱりでのオープンエリアの釣りには向いてないというだけなのだ。
逆にいえば、オープンエリアでない場所なら、現在でもなお、ショートロッド、ベイトリール、太いライン、固定重心ルアーが強いシチュがあるのである。
少々長くなりすぎたので、この辺りで今回は止めておく。眠いし。個人的に、川はそろそろシーズンオフだし(条件がよい日でないともう釣れない)、時間が出来るから、次からはロッド、リール、ルアー、ラインの話でも掘り下げて書いてみようと思う。
ではでは。
お題は「シーバスフィッシングの道具のトレンド」である。
現在のシーバスフィッシングなんだけど、スタンダートなロッド、リール、ライン、ルアーについてまとめると、
ロッド:8.7ft~9.6ft
リール:スピニングの2500~3000番
ライン:PEライン0.8~1.5+リーダー
ルアー:8~12㎝の移動重心ミノー、シンペン、バイブ
といった感じの道具が主流になっている。大体、どこの釣具屋にいっても、シーバスフィッシング売り場で売られているのはこんな道具達になる。
これらの道具を見れば一目瞭然なんだけれど、現在のシーバスフィッシングのトレンドは一言で表すと
「飛距離絶対主義」
である。
長い竿にスピニングリールつけて、PEラインを巻いて、移動重心のルアーをぶっ飛ばす。シーバスフィッシングの売り場で売られているのは、そんな道具達なのだ。
さて、こういった傾向はシーバスフィッシングの黎明期からあったのかと言われると、
石巻シーバスの歩みを振り返る【釣れないから面白い?辛いから楽しい?】
こちらに東北の巨匠こと村岡博之さんの石巻シーバスの歴史の記事があるけど、30年前の村岡さんが始めた頃のタックルは、6ft半のトラウトロッドに6lbのナイロン巻いたスピニングでシンキングミノーを巻く釣りだった。
シーバスフィッシングの黎明期は、まだ専用ロッドとかなくてバスロッドとかトラウトロッドを流用していた時代だ。ミノーもシンキングが主流でラパラCDとかボーマーのロングAとかが人気だった時代である。
ラパラCDは現在でも生き残っているけれど、ボーマーのロングAはシーバスで使っている人はいなくなった。バスの世界ではロングAはまだ使う人がいるんだけれど、シーバスの世界では誰も使わない。
理由は単純。移動重心ミノーの先駆けであるK-TENが発売され、ボーマーのロングAを使う必要がなくなったからだ。
ラパラCDは元々遠投する為に使われるルアーではなくて、飛距離はそんな必要ない、ストラクチャーの多い港湾でよく使われるルアーだった。これは現在でもそうだし、そういう場所では現在もなお、最強のルアーである。だからラパラは生き残った。(ストラクチャーの多い場所では固定重心のルアーが強い。この話は後でする)
一方で、ボーマーのロングAは河口部なんかのオープンエリアで使われていたルアーだったんだけど、より飛距離がでる移動重心ミノーが各社から発売され始めるとロングAは瞬く間に姿を消してしまったのである。
このロングAに起きた事は、ロッド、ライン、リールにも起きた。ロッドはどんどん長尺化し、ベイトリールは飛距離が出ないからシーバスの世界では主流にはなれず、ラインはナイロンとフロロを押しのけてPEが主流になったのである。
オープンエリアで、長い竿に、スピニングリールをつけて、PE巻いて、重心移動ルアーをぶっ飛ばす。
それが現在のシーバスのトレンドなのだ。だから飛距離が出るタックルがここまで人気がでる。
この対極にある釣りとしては、
「ショートロッドに
ベイトリールつけて
太いラインを巻き
軽いルアーを投げる釣り」
となるだろう。この釣りとはよーするにブラックバスのベイトフィネスだ。延々とカバーを探る釣りで、オープンエリアを探る釣りの対極にある釣りといっていい。
こういった障害物についてる魚を取る釣りは、シーバスフィッシングではボートシーバスが主流で、おかっぱりでは殆ど行われていないと言って良い。
原因は主に二つ。
一つめは2004年の改正SOLAS条約のせいで、港湾部への立ち入りが規制され、港湾のシーバス釣りがもの凄く難しくなったこと。そして二つ目だけど、陸っぱりから狙えるストラクチャーってのは目立つので、どこにいっても人的プレッシャーが強くて魚がスレてしまい、釣りにくいのだ。
その結果、現在のシーバスフィッシングの主流は河川のオープンエリアとなり、オープンエリアで強いロングロッド、スピニング+PE、重心移動ルアーがメインストリームになったと言えるだろう。
具体的な例をだすと、9.6ftのロッドに0.8のPEをスピニングに巻いて、オープンエリアでX-80ぶっ飛ばすのが、おかっぱりのシーバスである。そして大概hogeる。
一方で、ボートシーバスなんかは6.6ftのロッドに12LBのフロロをベイトに巻いて、ビーフリーズで穴撃ちする。滅茶苦茶釣れる。
こうやって書くと、ショートロッドと太いライン、ベイトリール、ビーフリのが優れているように見えるかもしれないけど、ボートシーバスの穴撃ちでは、
「ボート上からの正確なキャストの為のショートロッドとベイトリール、
摩擦で切れにくいフロロ12ポンド、
ストラクチャーに当てても壊れず
水中で障害物に当たっても泳ぎ続ける固定重心ルアー」
のが向いてるからそーなるってだけなのだ。
それに、オープンエリアの釣りって、そんな釣れるモンでもないのだ・・・・これは昔っからそーだった・・・・。比較的釣りやすい港湾部から釣りにくいオープンエリアが主戦場になった訳でそりゃ釣れなくなるって話だ。
結局、現在のシーバス釣りのトレンドについて考えていくと、河川下流部のオープンエリアでの釣りが主流になった事で、ロッドの長尺化、PEと移動重心ルアーの隆盛、ミノーのリップレス化が進んだって事になる。
ショートロッド、ベイトリール、太いナイロンorフロロライン、固定重心ルアーが釣れない訳ではない。ただ、おかっぱりでのオープンエリアの釣りには向いてないというだけなのだ。
逆にいえば、オープンエリアでない場所なら、現在でもなお、ショートロッド、ベイトリール、太いライン、固定重心ルアーが強いシチュがあるのである。
少々長くなりすぎたので、この辺りで今回は止めておく。眠いし。個人的に、川はそろそろシーズンオフだし(条件がよい日でないともう釣れない)、時間が出来るから、次からはロッド、リール、ルアー、ラインの話でも掘り下げて書いてみようと思う。
ではでは。
- 2016年11月15日
- コメント(0)
コメントを見る
fimoニュース
登録ライター
- スミス:ディプシードゥMAX
- 8 日前
- ichi-goさん
- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…
- 9 日前
- hikaruさん
- 新年初買
- 14 日前
- rattleheadさん
- 温室育ち24セルテ、逆転す
- 17 日前
- 濵田就也さん
- 野生の本能を刺激する
- 24 日前
- はしおさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪
- ハマケン
-
- 流れの釣り
- Kazuma















最新のコメント