プロフィール
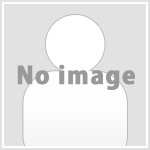
paltaro
神奈川県
プロフィール詳細
カレンダー
検索
タグ
タグは未登録です。
アーカイブ
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:31
- 昨日のアクセス:211
- 総アクセス数:668956
QRコード
▼ イナッコの成長と生息域とシーバスの微妙な関係
- ジャンル:日記/一般
こないだから河川の調査を続けていて気付いた事があるので、まとめておこうと思う。
湘南河川でシーバスの最も重要なベイトはボラで、2~3㎝のボラの幼魚から15㎝のイナッコまで幅広くシーバスに補食されている。
湘南河川において、ボラの幼魚であるハクの遡上が始まるのが3月頃で、この時のハクの大きさは2~3㎝といった所。
ハクは大体一ヶ月で1㎝大きくなるので、4月には4㎝、5月には五㎝、6月には六㎝という感じで大きくなる。
3月頃は河口域にハクが溜まるケースが多くて、河口域あたりでハクパターンで楽しめる事が多い。ただし、4月あたりからハクは大規模な群れを作って河川を遡上し始め、河川の淡水域のシャローに入ってくる。
面白い話だけど、例年、4月中旬あたりにはシーバスは河口域では釣れなくなってきて、一方で河川の淡水域で釣れ始めるのだ。
そして5月から6月にかけての湘南河川の主戦場は主に淡水域で、淡水域に遡上したハクや稚鮎についている魚を狙う形になる。
この釣りは大体7月になると機能しなくなってくる。何故かというと稚鮎は河川の上流部の堰の上に遡上していなくなってしまう。
そしてもう一つ。これが先日気付いた事なんだけど、ハクが成長して7㎝くらいになりイナッコになると、イナッコ達は大挙して湘南河川を下り始めるようなのだ。
イナッコ達は河川下流部の比較的塩分濃度の低いエリアに群れで移動して、そこに居着くのだ。これが7月から8月にかけて起こる。そして淡水域からベイトが一気に抜ける。
5~6月、稚鮎とハクはほぼ同じエリアにいる。だが、7月になると稚鮎が水温の低い河川上流域に移動するのに対して、イナッコは塩分濃度が比較的低い河川下流域へ移動するのである。
これはシーバスのメインベイトが二つのエリアに分かれる事を意味している。
そして、こっからが又面白いのだけれど、7~8月あたりになると、春に生まれたシーバスの新子が河川の上流域に入ってくるのである。
相模川を例にだすと、現在の所、神川橋から銀河大橋にかけてのエリアに相当量のセイゴが入ってきていて、夜にライトで岸際のシャローを照らすと、ハゼ、テナガエビに混じって、15㎝前後のセイゴがうじゃうじゃいる。ハゼと同じく、セイゴも十分に大きくなるまでは淡水域でエサを取るのである。
一方で、シーバスの成魚は下流域に移動するのだ。イナッコを追って。そしてシーバスの成魚が淡水域に戻って来るのは、みんな大好き落ち鮎シーズンからになる。落ち鮎シーズンが始まると、今度はセイゴが下流域に落ちる。これは共食いを避ける為のメカニズムなんだろう。
夏場に入ると、何故淡水域からハクが消えるのか、何故セイゴが急に上流域に増えるのか、何故秋になると下流域でセイゴが急激に増えるのかってのは前々から疑問だったけれど、最近の河川調査と、幾つかのブログの記事のおかげでそれが解けた。
湘南河川のリバーシーバスは5~6月は淡水域が強いけど、7~8月は汽水域が強い。湘南では5~6月にバチ抜けが起きず、鮎の遡上とイナッコの成長に合わせてシーバスが移動するため、こういう循環になるんだと思う。
ま、今日はそんな所で。
湘南河川でシーバスの最も重要なベイトはボラで、2~3㎝のボラの幼魚から15㎝のイナッコまで幅広くシーバスに補食されている。
湘南河川において、ボラの幼魚であるハクの遡上が始まるのが3月頃で、この時のハクの大きさは2~3㎝といった所。
ハクは大体一ヶ月で1㎝大きくなるので、4月には4㎝、5月には五㎝、6月には六㎝という感じで大きくなる。
3月頃は河口域にハクが溜まるケースが多くて、河口域あたりでハクパターンで楽しめる事が多い。ただし、4月あたりからハクは大規模な群れを作って河川を遡上し始め、河川の淡水域のシャローに入ってくる。
面白い話だけど、例年、4月中旬あたりにはシーバスは河口域では釣れなくなってきて、一方で河川の淡水域で釣れ始めるのだ。
そして5月から6月にかけての湘南河川の主戦場は主に淡水域で、淡水域に遡上したハクや稚鮎についている魚を狙う形になる。
この釣りは大体7月になると機能しなくなってくる。何故かというと稚鮎は河川の上流部の堰の上に遡上していなくなってしまう。
そしてもう一つ。これが先日気付いた事なんだけど、ハクが成長して7㎝くらいになりイナッコになると、イナッコ達は大挙して湘南河川を下り始めるようなのだ。
イナッコ達は河川下流部の比較的塩分濃度の低いエリアに群れで移動して、そこに居着くのだ。これが7月から8月にかけて起こる。そして淡水域からベイトが一気に抜ける。
5~6月、稚鮎とハクはほぼ同じエリアにいる。だが、7月になると稚鮎が水温の低い河川上流域に移動するのに対して、イナッコは塩分濃度が比較的低い河川下流域へ移動するのである。
これはシーバスのメインベイトが二つのエリアに分かれる事を意味している。
そして、こっからが又面白いのだけれど、7~8月あたりになると、春に生まれたシーバスの新子が河川の上流域に入ってくるのである。
相模川を例にだすと、現在の所、神川橋から銀河大橋にかけてのエリアに相当量のセイゴが入ってきていて、夜にライトで岸際のシャローを照らすと、ハゼ、テナガエビに混じって、15㎝前後のセイゴがうじゃうじゃいる。ハゼと同じく、セイゴも十分に大きくなるまでは淡水域でエサを取るのである。
一方で、シーバスの成魚は下流域に移動するのだ。イナッコを追って。そしてシーバスの成魚が淡水域に戻って来るのは、みんな大好き落ち鮎シーズンからになる。落ち鮎シーズンが始まると、今度はセイゴが下流域に落ちる。これは共食いを避ける為のメカニズムなんだろう。
夏場に入ると、何故淡水域からハクが消えるのか、何故セイゴが急に上流域に増えるのか、何故秋になると下流域でセイゴが急激に増えるのかってのは前々から疑問だったけれど、最近の河川調査と、幾つかのブログの記事のおかげでそれが解けた。
湘南河川のリバーシーバスは5~6月は淡水域が強いけど、7~8月は汽水域が強い。湘南では5~6月にバチ抜けが起きず、鮎の遡上とイナッコの成長に合わせてシーバスが移動するため、こういう循環になるんだと思う。
ま、今日はそんな所で。
- 2017年8月29日
- コメント(1)
コメントを見る
fimoニュース
登録ライター
- レガーレ:ディモル70
- 6 時間前
- ichi-goさん
- 『何が違うんでしょうね?』 2…
- 1 日前
- hikaruさん
- ふるさと納税返礼品
- 7 日前
- papakidさん
- 夏の景色の中で
- 8 日前
- はしおさん
- 43rd ONE ON ONE
- 9 日前
- pleasureさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- 清流鱸を追って38
- 金森 健太
-
- 続・ありがとうサミー100スズキサイ…
- そそそげ



















最新のコメント