プロフィール
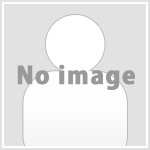
釣りバカ運送店
北海道
プロフィール詳細
カレンダー
検索
最近の投稿
アーカイブ
▼ つづき(鈎の話)
- ジャンル:日記/一般
- (ジギング, スローピッチジャーク, ボートフィッシング)
前回の続きですよ~
まぁ、佐藤統洋大先生の受け売りなんですけどね・・・。
“②ジグのバランスをとる”からでしたね
えっと
「水の中」という事で、いろいろな物に抵抗が掛かる訳ですが
当然ながら鈎もその中に含まれます
普通に考えれば
・大きい・軸が太い=抵抗が大きい
・小さい・軸が細い=抵抗が小さい
となります
また
・アシストラインが長い・太い=抵抗が大きい
・アシストラインが短い・細い=抵抗が小さい
なので
・ゴツイアシストフック=抵抗が大きい
・小さいアシストフック=抵抗が小さい
と言えます
これを利用して、ジグの動きをある程度調節することができます
軽いジグを使う時は顕著に差が出てきますよ(^^
まず、前後、同じフックを付けた時を基準として
・フォールスピードを速くする=前後を小さくする(ただし、前後のサイズは同じ)
・ 〃 を遅くする=前後を大きくする(ただし、前後のサイズは同じ)
また
・スライド幅を長くしたい=後ろを小さくする、または外す(後ろでブレーキをかけないようにするため)
・ 〃 短くしたい=前を小さくする、または外す、もしくは後ろを大きくする(後ろのブレーキを大きくする)
事も可能ですし
加えて、前後、同じフックを付けた時に水平フォールをする時
・頭からフォールさせたい=後ろの抵抗を増やす(→頭から落ちていく)
・バックスライドさせたい=前の抵抗を増やす(→後ろから落ちていく)
という芸当も可能なわけですね
さらに、もっと抵抗を増やすために「タコベイトを付ける」と言う方法もあります
偶に、スローピッチジャークの釣行写真で鈎にタコベイトを付けているのがあります
確かに、タコベイトを食っても来ますけど
本来の狙いは「鈎の抵抗を増やす事」なんですね
よく、バスルアーのポッパーに付いているトリプルフックで、リアだけ羽がタイインングされたものがありますが、あれは“抵抗になる物を付けて、必要以上に動かないようにする”という意図もあるそうです
また、タコベイトの副次的なものとして“根掛かり回避”が挙げられます
なぜか
いくら抵抗があるとはいえ、ジグが着底→フックが着底という順番であることは想像に難しくないと思います
この時、ジグが着底してからフックが着底するまでの時間のラグが長ければ、どっかに鈎が引っかかる前に、底を切ることができますよね?
まぁ・・・ジグが引っかかったらオシマイなんですが・・・。
あと、アシストラインの話もチョロッとしましたが
絡み防止や、鋭い歯を持つ魚に対応するために中芯としてフロロやワイヤーを入れることがあるのですが
それだけでもジグに対する抵抗が変わりますし、魚の喰い込み(吸い込み)にも影響が出てきます
ちなみに
・抵抗大(吸い込み悪)ワイヤー>フロロ>芯なし(吸い込み良)抵抗小
となっていますので参考まで
まぁ・・・知っているからと言って、魚がボコボコ釣れるようになる訳ではないのですけどね・・・。
まぁ、佐藤統洋大先生の受け売りなんですけどね・・・。
“②ジグのバランスをとる”からでしたね
えっと
「水の中」という事で、いろいろな物に抵抗が掛かる訳ですが
当然ながら鈎もその中に含まれます
普通に考えれば
・大きい・軸が太い=抵抗が大きい
・小さい・軸が細い=抵抗が小さい
となります
また
・アシストラインが長い・太い=抵抗が大きい
・アシストラインが短い・細い=抵抗が小さい
なので
・ゴツイアシストフック=抵抗が大きい
・小さいアシストフック=抵抗が小さい
と言えます
これを利用して、ジグの動きをある程度調節することができます
軽いジグを使う時は顕著に差が出てきますよ(^^
まず、前後、同じフックを付けた時を基準として
・フォールスピードを速くする=前後を小さくする(ただし、前後のサイズは同じ)
・ 〃 を遅くする=前後を大きくする(ただし、前後のサイズは同じ)
また
・スライド幅を長くしたい=後ろを小さくする、または外す(後ろでブレーキをかけないようにするため)
・ 〃 短くしたい=前を小さくする、または外す、もしくは後ろを大きくする(後ろのブレーキを大きくする)
事も可能ですし
加えて、前後、同じフックを付けた時に水平フォールをする時
・頭からフォールさせたい=後ろの抵抗を増やす(→頭から落ちていく)
・バックスライドさせたい=前の抵抗を増やす(→後ろから落ちていく)
という芸当も可能なわけですね
さらに、もっと抵抗を増やすために「タコベイトを付ける」と言う方法もあります
偶に、スローピッチジャークの釣行写真で鈎にタコベイトを付けているのがあります
確かに、タコベイトを食っても来ますけど
本来の狙いは「鈎の抵抗を増やす事」なんですね
よく、バスルアーのポッパーに付いているトリプルフックで、リアだけ羽がタイインングされたものがありますが、あれは“抵抗になる物を付けて、必要以上に動かないようにする”という意図もあるそうです
また、タコベイトの副次的なものとして“根掛かり回避”が挙げられます
なぜか
いくら抵抗があるとはいえ、ジグが着底→フックが着底という順番であることは想像に難しくないと思います
この時、ジグが着底してからフックが着底するまでの時間のラグが長ければ、どっかに鈎が引っかかる前に、底を切ることができますよね?
まぁ・・・ジグが引っかかったらオシマイなんですが・・・。
あと、アシストラインの話もチョロッとしましたが
絡み防止や、鋭い歯を持つ魚に対応するために中芯としてフロロやワイヤーを入れることがあるのですが
それだけでもジグに対する抵抗が変わりますし、魚の喰い込み(吸い込み)にも影響が出てきます
ちなみに
・抵抗大(吸い込み悪)ワイヤー>フロロ>芯なし(吸い込み良)抵抗小
となっていますので参考まで
まぁ・・・知っているからと言って、魚がボコボコ釣れるようになる訳ではないのですけどね・・・。
- 2014年6月20日
- コメント(3)
コメントを見る
釣りバカ運送店さんのあわせて読みたい関連釣りログ
シマノ(SHIMANO) リール メンテナンス スプレー 2本セット(オイル&グリース) SP-003H 890078
posted with amazlet at 17.11.29
SHIMANO(シマノ)
fimoニュース
| 10:00 | 釣り開始25分で…自己記録更新! |
|---|
| 08:00 | 間違いなく僕には忘れられない魚 僕と清流鱸 |
|---|
| 00:00 | [再]ダイワの釣り専用くつの威力! |
|---|
| 11月21日 | 1日当たり700円? 去年買ったウェーダーが浸水 |
|---|
登録ライター
- アオリーQ NEO 3.0号
- 6 日前
- 濵田就也さん
- 『癖が強い・・・?』2025/11/…
- 8 日前
- hikaruさん
- UFMウエダ:PRO4スピリッツ・…
- 8 日前
- ichi-goさん
- 台風一過のエビパターン
- 19 日前
- はしおさん
- ふるさと納税返礼品
- 28 日前
- papakidさん
本日のGoodGame
シーバス
-
- 好きな釣り方で満足のできる1匹
- JUMPMAN
-
- 河川も秋…到来?!
- バイシュイ



















遅コメ失礼します。
難しいけど、フックってやっぱり神経質にならないと
獲れる魚も獲れなくなる大事なトコですよね。
私はジギングであんまり積極的に合わせをいれません。
スラッグをきっちりとって一回スイープするぐらい?
それでもそんなにばらさない方かな。
なので基本ジャーク中にかかってくれることを意識して、
なおかつ、抵抗を小さくするためにカルティバ早掛の
5/0、6/0を芯なしでで使っています。今のところ
ベストなセッティングかな?また変わると思うけど。
Terry
北海道